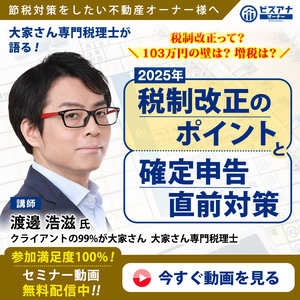アパート経営の減価償却とは?計算例と確定申告の手順を初心者向けに紹介

アパート経営をする上で減価償却の理解は欠かせません。家賃収入を得た際には確定申告を行うことになり、減価償却費を正しく入力する必要があるからです。
しかし、減価償却は計算方法やルールが複雑なので、理解するのに時間がかかることもあります。
初心者でもスムーズに処理できるよう、減価償却の概要から計算方法、確定申告の手順までわかりやすく解説します。
アパート経営の減価償却とは?

減価償却とは、一定の資産(建物、機械など)を購入した際にその資産の使用可能な期間にわたって分割し、費用を計上する会計処理です。
減価償却によって計上する費用を「減価償却費」といいます。
アパート経営の確定申告時に作成する青色申告決算書(または収支内訳書)には、減価償却費の記載欄があります。
アパート経営ではほとんどの場合で減価償却が発生するため、正しく理解することが必要です。
減価償却の概要や計算方法について詳しく解説します。
減価償却の概要
前述したように、減価償却は購入した資産の取得費用を一度に全額経費にするのではなく、使用できる年数に応じて分割し、毎年の経費として計上する方法です。
アパート経営のために購入するアパート、すなわち不動産も固定資産=減価償却資産です。
たとえば、あと20年使用できるアパートを2,000万円で購入した場合は2,000万円÷20=100万円なので、20年間は100万円で計上できます。
一括で2,000万円を計上してしまうと翌年から収益だけが発生している状態になるため、費用と収益を正しく計上するために減価償却は必要なのです。
そのため、アパート経営の確定申告を正しく行うためには減価償却を行う必要があります。
ちなみに、減価償却の対象になる資産を「減価償却資産」、資産が使用できる期間を「耐用年数」と呼びます。
ユーザー登録するだけで永年無料で収支管理が簡単にできる「ビズアナオーナー」では、ユーザー限定で、専門家が減価償却や確定申告についてわかりやすく解説するウェブ動画を無料公開しています。
アパート経営で発生する経費の例
アパート経営で発生する経費として以下の項目が挙げられます。
| 科目 | 概要 |
|---|---|
| 減価償却費 | その年に経費計上する減価償却費 |
| 租税公課 | 国や地方公共団体に納付する税金。物件購入時に発生する登録免許税や不動産取得税、アパートにかかる固定資産税などが該当 |
| 修繕費 | アパートの設備や内外装の修繕にかかる費用 |
| 借入金利子 | 物件の購入に際してローンを組んだ場合の利子部分 |
| 水道光熱費 | アパートの共用部分にかかる電気代など |
| 管理費 | 物件の管理にかかる費用。管理委託手数料などが該当 |
| 損害保険料 | 地震保険料や火災保険料など |
減価償却費を含め、上記で挙げた経費はアパート経営で発生する可能性が非常に高いです。
そのため、アパート経営するときは物件の価格だけでなく経費も計算しておきましょう。
減価償却の方法と税務上の特例
減価償却では、税法上の特例として「一括償却資産」と「少額減価償却」を利用して計上することも可能です。
減価償却の種類や減価償却の特例について詳しく解説します。
減価償却
減価償却では「定額法」と「定率法」の2種類の計算方法があります。
詳しい計算方法についてはこの後の章で解説しています。
一括償却資産の特例
一括償却資産とは、取得価額が10万円以上20万円未満の資産であれば、通常の減価償却をせずに、3年間で均等に費用計上できる制度です。
取得価額を3年間で3分の1ずつ計上できますが、一部のリース資産や貸付目的の資産は適用外です。
少額減価償却資産の特例
少額減価償却資産とは、取得価額が10万円以上30万円未満の資産を取得した年に全額を費用計上できる制度です。
ただし、青色申告を行っている事業者のみ適用され、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 取得価額が10万円以上30万円未満である
- 青色申告者である
- 本特例の適用を受けるのが、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの額である
この特例では、その年の少額減価償却資産の合計額が300万円までという上限があるため、利用する際は注意が必要です。
また、少額減価償却資産の特例を受けた固定資産は、通常通り固定資産税の対象になります。
参考:国税庁「少額の減価償却資産及び一括償却資産(令第138条及び第139条関係)」
減価償却の計算方法
減価償却の計算方法は複数ありますが、個人事業主はすべての減価償却資産について「定額法」を用いるのが原則です。
定額法とは、取得価額に定額法の償却率を乗じた額を減価償却費とする方法です。減価償却費の額が原則として毎年同額となります。
たとえば、取得価額が1,000万円、定額法の償却率が0.030の物件の場合、減価償却費は以下のようになります。
1,000万円 × 0.030=30万円
定額法の償却率は法定耐用年数ごとに定められており、国税庁による資料「減価償却資産の耐用年数表」で確認可能です。
法定耐用年数は固定資産の種類ごとに決められているので詳細は後述します。
減価償却をしないとどうなるのか
減価償却資産に該当する資産、すなわち時間の経過によって価値が減少する固定資産は、原則として減価償却が必要となります。
購入した年に全額を経費計上するのではなく、まずは取得価額で資産計上を行ってください。
そして減価償却で少しずつ費用処理をしていきます。
購入時に資産計上した固定資産について減価償却をせずにいると、以下のような事態が起こります。
- 時間の経過による価値の減少が正しく反映されない
- 減価償却費が計上されない分納付すべき税額が増えてしまう
節税の観点からも、アパート経営の確定申告において減価償却は必須です。
減価償却費を割り出すために必要な法定耐用年数

法定耐用年数とは、減価償却資産の資産価値が消滅するまでの期間として国が定めた年数です。
減価償却では法定耐用年数を用いて計算を行います。
アパートの法定耐用年数
法定耐用年数は資産の構造や用途ごとに細かく定められています。
アパートの構造別の法定耐用年数は以下の通りです。
| 構造・用途 | 法定耐用年数 |
|---|---|
| 鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 | 47年 |
| 重量鉄骨造 | 34年 |
| 軽量鉄骨造 | 骨格材の厚さが3mm超4mm以下:27年 骨格材の厚さが3mm以下:19年 |
| 木造 | 22年 |
また、アパート本体だけでなく以下のような設備も減価償却の対象です。
| 構造・用途 | 法定耐用年数 |
|---|---|
| 衛生設備、排水設備、ガス設備 | 15年 |
| アーケード・日よけ設備 | 金属製のもの:15年 その他の素材:8年 |
| 電気設備(照明設備を含む) | 蓄電池電源設備:6年 その他:15年 |
| 冷房用・暖房用機器 | 6年 |
| 冷蔵庫、洗濯機 | 6年 |
| インターホン | 6年 |
出典:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」
アパート経営では建物と設備は別々に資産計上し、それぞれで減価償却を行う必要があります。
アパート経営における減価償却のシミュレーション例
個人事業主が行う定額法での計算方法は以下の通りです。
・取得取得価額 × 定額法の償却率=減価償却費
定額法の償却率は法定耐用年数ごとに定められていると紹介しました。したがって、減価償却を行うには法定耐用年数の確認が必要です。
償却率は国税庁の「減価償却資産の償却率等表」という資料により確認することができ、例えば耐用年数が20年の場合は0.050となっています。
アパート経営の減価償却について、法定耐用年数を超える前・法定耐用年数が経過したアパート、それぞれのシミュレーション例を紹介します。
耐用年数を超える前のアパートの場合
耐用年数を超える前のアパートの場合、その物件が新築か中古かで考え方が異なります。
新築アパートの場合は通常の法定耐用年数をそのまま用います。
たとえば新築の鉄筋コンクリート造のアパートを3,000万円で購入した場合、耐用年数および減価償却費の計算式は以下の通りです。
- 耐用年数:47年(法定耐用年数をそのまま使う)
- 償却率:0.022
- 減価償却費:3,000万円 × 0.022=66万円
続いて中古の場合です。中古の場合、減価償却費の計算に用いる耐用年数は以下の計算式で求められます。
(新品の耐用年数-経過年数)+経過年数 × 0.2
たとえば、耐用年数が47年で築10年の鉄筋コンクリート造のアパートを2,000万円で購入した場合、耐用年数を求める計算式は以下のようになります。
(47年-10年)+10年 × 0.2=39年
耐用年数が39年の場合の償却率は0.026です。したがって、減価償却費は以下の通りです。
2,000万円 × 0.026=52万円
耐用年数を超えているアパートの場合
購入時点で耐用年数を過ぎていた物件の場合、法定耐用年数に0.2を乗じた年数を耐用年数として用います。
法定耐用年数のすべてを経過した木造アパートを2,000万円で購入した場合、減価償却に用いる耐用年数は以下の通りです。
22年 × 0.2=4.4年 1年未満切り捨てで4年
耐用年数4年の場合の償却率は0.250です。したがって、減価償却費は以下のようになります。
2,000万円 × 0.250=500万円
アパートの耐用年数が極端に短い場合、最低耐用年数で計算する方法もあるため税務署に相談すると確実です。
アパート経営で確定申告をするときの手順

最後に、アパート経営を始めた方が確定申告する方法について解説します。
確定申告するときの手順
アパート経営における確定申告の大まかな手順は以下の通りです。
- 必要書類を集める
- 青色申告決算書または収支内訳書を作成する
- 確定申告書を作成する
- 期日までに確定申告書および添付書類を提出する
2の書類ですが、確定申告の方法が青色申告の場合は「青色申告決算書」が、白色申告の場合は収支内訳書が必要となります。
アパート経営の場合は「不動産所得用」と明記された様式を使う点にも注意が必要です。
減価償却費を記載する箇所
減価償却費を記載するのは、青色申告決算書または収支内訳書の以下の2箇所です。
- 1ページ目 必要経費の該当欄
- 「減価償却費の計算」の欄※青色申告決算書の場合は3ページ目、収支内訳書の場合は2ページ目
確定申告書に減価償却費を個別で記載する欄はありません。確定申告では、減価償却費を含むすべての経費の合計額を記載してください。
確定申告の期日と提出方法
確定申告はその年の所得について、翌年2月16日から3月15日までに行う必要があります。
3月15日が土日の場合は翌平日が期日です。
提出方法は以下の3種類あります。
- 税務署に直接持参する
- 税務署へ郵送で提出する
- e-Taxで提出する(電子申告)
なお、確定申告書の提出先は居住地を管轄している税務署です。所有しているアパートを管轄する税務署ではない点にご注意ください。
確定申告の注意点
アパート経営の確定申告で、特に注意すべきポイントとして以下の3点が挙げられます。
- 確定申告をしなかった場合、無申告加算税や延滞税といったペナルティが発生する
- ローンの元本や所得税・住民税、スーツ代など、経費にできない支出も存在する
- 土地は減価償却の対象外
(時間の経過による価値の減少が起こらないため、減価償却の対象外となります)
期日までに確定申告を終わらせることはもちろん、経費計上や減価償却を正しく行うことも徹底しましょう。
確定申告に役立つ情報を知るなら「ビズアナオーナー」
当社が提供している無料の収支管理サービス「ビズアナオーナー」は、賃貸経営を行っているオーナーが利用する無料の収支管理サービスです。
月々の収支データを無料で簡単に自動でデータ化し、わかりやすいビジュアルで経営状況を把握することができます。
また、ビズアナオーナーの会員限定で、補助金や節税、空室対策に関する最新の情報やダウンロード資料なども随時配布しています。
その他にも、賃貸経営に役立つサービスも特別価格や無料で利用いただくことが可能です。
是非、「ビズアナオーナー」を無料登録してみてください。
【確定申告にも役立つ!ラクラク収支管理!】
- 収支報告書を事務局に送るだけ!毎月カンタンに収支管理ができる
- 確定申告対策など不動産オーナーのためのセミナーアーカイブ動画が無料で視聴できる
- AI賃料査定レポートサービスなど不動産投資に役立つメニューがお得に利用できる
ビズアナオーナーは、毎月ラクして収支管理を行いながら確定申告にも慌てず備えたい不動産オーナー様におすすめです!