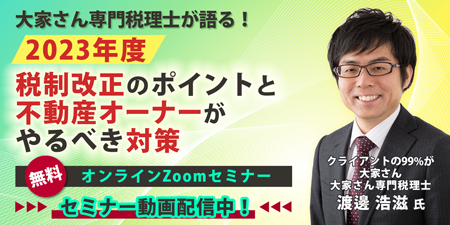青色申告で不動産所得の確定申告を有利に!書き方や経費について解説
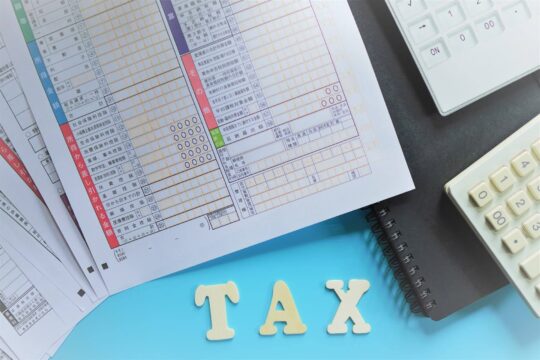
不動産経営で所得が発生すると必ず行うことになる、確定申告。少し調べてみると「青色申告のほうが有利」といった情報がでてきますが、そもそも青色申告とは何を指しているのでしょうか。
今回は、不動産所得の確定申告で損をしないために押さえておきたい、青色申告について解説します。
青色申告と白色申告との違い。 不動産所得にはどのような違いがある?
確定申告の青色申告と白色申告、聞いたことはあるけど違いがイマイチよくわからない、という方は多いようです。青色申告と白色申告の違い、そして不動産所得で青色申告をするにはどうしたらよいかについてみていきましょう。
青色申告と白色申告の違い
確定申告には、青色申告と白色申告があります。色の違いはかつての申告書類の色の名残であって、決して現在の書類を反映しているわけではありません。
青色申告は、帳簿を備えつけることを促進する目的で制定された制度です。帳簿を整備する代わりに税負担を軽くする、アメとムチの制度といえます。
青色申告と白色申告の違いを表にまとめると以下のとおりです。
| 青色申告 | 白色申告 | |
| 特別控除 | あり(65万円・55万円・10万円) | なし |
| 専従者給与控除 | あり | なし |
| 赤字の繰越 | できる(3年間) | できない |
| 事前申請の要否 | 必要 | 不要 |
| 帳簿作成の義務 | あり | 一部あり |
この中でメリットと呼べるのは、特別控除、専従者給与控除、赤字の繰越です。
特別控除は、所得から一定額の控除を受けられるものです。特別控除については、2021年に行う「2020年分の確定申告」から一部変更になるため、注意が必要です。詳しくは後述します。
専従者給与控除は、家族が事業を手伝っている場合に、その家族への給与を控除できる制度です。専従者が事業主の配偶者なら86万円、配偶者でない場合はひとりあたり50万円までの控除ができます。
赤字の繰越は、白色申告では行うことができません。青色申告ならば、3年間まで可能です。
不動産所得で青色申告をするには
不動産所得の場合は、所得だけではない不動産特有の基準もあります。
不動産所得で青色申告をするには、「青色申告承認申請書」を事前に提出しておく必要があります。この申請書は青色申告の適用を受けたい年の3月15日までに税務署に申請することが必要になります。
仮に、2020年分の確定申告から適用を受けたい場合は、2020年3月15日です。現在からは、2021年分からの適用になります。
また、収入と必要経費の記帳および関連する書類を、原則7年間は保存しておかなければいけません。もし、税務調査等が入り、帳簿類がない、記帳をしていないことが判明すると、さかのぼって税金を納めなければなりません。
青色申告の記帳については、白色申告と違い、複式簿記が要求されています。複式簿記とは、仕訳という方法で帳簿に記録する記帳方法です。商業高校などで習うものなので出身者はよく知っていると思います。少し勉強すれば簡単な帳簿作成はできるようになりますが、自信のない人は個人事業主用の会計ソフトもありますので利用するとよいでしょう。
不動産の事業的規模で異なる65万円控除と10万円控除とは
不動産所得の場合、他の所得と異なる「事業的規模」という考え方が導入されています。この事業的規模によっては、特別控除の金額が大きく変わるのです。
不動産所得特有の事業的規模と控除額の関係について、詳しくみていきましょう。
不動産所得の事業的規模とは
青色申告の事前申請を提出すれば、不動産所得のある人は特別控除を受けることができます。
ただし、不動産所得の場合、その所得が事業的規模にあるか否かでその控除額が決まります。国税庁のホームページ上の「No.1373 事業としての不動産貸付けとの区分」には事業的規模の判断基準が以下のように示されています。
1.貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
2.独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
賃貸マンションやアパートで10室以上の物件であれば事業的規模とみなされます。これは合計の部屋数でよいので、例えば、6室のアパートを1棟、4室のアパートを1棟の計2棟持っていてもクリア可能です。
2点目の独立家屋は一戸建てやマンションの1室の貸付けを想定しています。この基準によると、転勤などがあり、住んでいたマンションの1室を貸しているといった程度では事業的規模ではありません。そればかりか、不動産投資を始めて間もない人で、マンションの1室から賃貸を始めているような場合は、事業的規模と認められなくなってしまうのです。
控除額は10万円と65万円に加え55万円も
控除額の種類はこれまで65万円と10万円の2種類でしたが、2020年から55万円という新たな控除額も新設されました。事業的規模の判断結果によって控除額は大きく変わります。
不動産事業が事業的規模と認められない場合は、青色申告をしても控除額は10万円しか受けることができません。一方で不動産事業が事業的規模であれば、これまでは65万円控除が認められていました。
しかし、2021年3月15日までに行う2020年の確定申告からは、65万円控除を受けるために新たな条件が加わりました。e-Taxを利用することです。e-Taxを利用しない場合は、控除額が55万円となります。
e-Taxはマイナンバーカードやカードリーダーなど多少の手続きや設備が必要です。事前準備が若干かかるものの、e-Taxはパソコンやスマートフォンからでも申告ができるようになっています。多くの人はパソコンで帳簿管理を行っています。市販のソフトでもe-Taxへ簡単に申告できるようなものも増えてきました。これを機会にe-Taxで申告を始めるのもおすすめです。
不動産所得の税金計算。 経費算入できるもの・できないもの
ある出費が経費算入できるかどうかで、不動産所得の金額が変わってきます。上手に計上できれば、課税標準を下げることができ、節税にも貢献できます。反対に費用計上ができない場合には、税金を余分に支払うことも。場合によっては税務署の指摘を受けてしまいます。納税で不利にならないためにも経費については押さえておきましょう。
不動産所得で経費算入できるものは
確定申告の際の収支内訳書(不動産所得用)では、経費として計上できる科目が以下のように記載されています。
-
- 減価償却費
- 地代家賃
- 借入金利子
- 租税公課
- 損害保険料
- 修繕費
- 雑費
これらが不動産所得の経費として計上できる項目となります。不動産の維持管理に直接必要な科目が基本です。それぞれの注意点についてみていきましょう。
| 科目 | 注意点 |
| 減価償却費 | 建物が対象。土地には減価償却はない。仲介手数料は土地と建物を按分して建物分は減価償却の対象となる。 |
| 地代家賃 | 借地の場合や駐車場を借りている場合に支払う費用 |
| 借入金利子 | 対象は利子分だけで元金部分は対象外。元利均等返済の場合は、年々利子分の計上が少なくなる。 |
| 租税公課 | 毎年の固定資産税、都市計画税や物件取得時の不動産取得税、印紙税等が対象。所得税、法人税、住民税は対象外。 |
| 損害保険料 | 一括前払いであっても、当該年度分のみを費用計上。 |
| 修繕費 | 維持管理や原状回復のための費用。資本的支出は対象外。 |
| 雑費 | 管理会社への管理費、修繕積立金、広告宣伝費、書籍代、セミナー参加費等 |
不動産経営で生じた費用にはさまざまなものがあり、税制上の経費に該当するかどうかはわかりにくいものです。本などで調べたり、可能であれば税理士に相談したりしてみましょう。
経費算入できないもの
一方、経費に算入できないものも多数あります。うっかり計上してしまうと、税務署から指摘を受けてしまうこともあります。経費算入できないものは以下のようなものです。中には資本的支出といった、不動産特有の項目も含まれています。
-
- 所得税・法人税・住民税
- 反則金・罰金
- 資格取得のための費用
- 資本的支出
租税公課のうち、固定資産税等は経費算入できても、所得税や法人税、住民税は算入できません。理由として、他の所得との整合性があると考えられます。
スピード違反や駐車違反の反則金、罰金も経費になりません。これは個人に課せられるもので不動産投資の経費ではないからです。同様に資格取得のための費用も経費ではありません。
宅地建物取引士やマンション管理士など不動産系の資格は多くあります。これらの資格を取得するのは、不動産経営に役立つものではありますが、あくまで個人的な費用と考えられているからです。資本的支出は不動産の価値を向上させるようなリフォームや改造のことです。資本的支出は経費ではなく、資産に計上され、減価償却されます。広い意味では経費ですが、計上方法が異なることを覚えておきましょう。
【不動産経営をあらゆる方面から支援し節税対策も万全!】
- 確定申告対策など節税のコツが学べるセミナーにご招待
- 収支報告書を事務局に送るだけで毎月・毎年の収支状況が一目でわかる
- 月額利用料&登録料が0円だから必要経費が抑えられる
ビズアナオーナーは、PCやスマホで賃貸経営を賢く行いたい不動産オーナー様におすすめです!