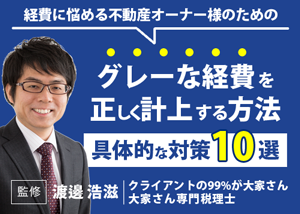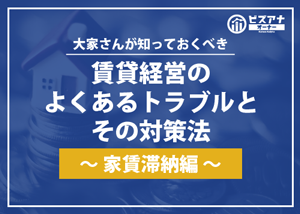敷金償却に関する特約とは?原状回復をめぐるトラブルを避けるための注意点

「敷金償却」という言葉をご存知でしょうか。
敷金償却とは賃貸契約時に入居者から支払われる敷金とは異なったお金で、主に西日本で賃貸借契約書の特約事項に盛り込まれている慣例です。
この敷金償却の意味や契約上の注意点、会計処理のポイントについて紹介します。
敷金償却とは
敷金償却とはどういったものなのでしょうか。
一般的な敷金との違いについて紹介します。
敷金のおさらい
敷金とは、部屋を借りたい賃借人と部屋を貸したい賃貸人のあいだで賃貸借契約にともない大家または管理者が預かるお金です。
敷金は、家賃の滞納の補填や退去時に部屋を明け渡す時点での原稿回復工事などに補填されます。そして、修繕費用などを差し引いて残った金額を退去者に返還します。
また、今まで曖昧であった原状回復のルールに対し、具体的な使用や適用方法についてはっきり文書で書き示すことで、これまでの問題点であったトラブルを抑制する効果として改正民法に基づき2020年4月に施工されました。
西日本特有の商慣習「敷金償却」
敷金償却とは、入居時に賃借人が支払った敷金や保証金のなかで、退去時に返還する必要が無いお金を指します。西日本の賃貸契約において特約に盛り込まれているケースがあり、「償却金」や「敷引き」とも呼ばれています。
一般的な敷金が退去時に部屋の原状回復に充てられて、差し引いた金額が入居者に返還されるのに対し、敷金償却はあらかじめ「敷金2ヶ月分のうち、1ヶ月分を償却する」といった特約が付いており、原状回復の費用が発生しない場合でも、敷金1ヶ月分は返還する必要はありません。
全国で一般的な、賃貸契約における「礼金」と同様のものと考えて差し支えありません。
敷金償却の相場
では、敷金償却の相場はいくらぐらいなのでしょうか。
不動産ポータルサイト「SUUMO」の調査によると、2018年1~3月にSUUMOに掲載された西日本の物件において、敷引きは家賃の役1.8ヶ月分程度だったと発表されています(参照元)。
このように、敷金償却には決められた価格はありません。しかし、あまりにも高い償却金だった場合は特約として認められないケースがあります。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、平成23年の最高裁判所の判例が記載されており、家賃の2.5~3ヶ月分までの償却金であれば問題ないと考えられています。
敷金償却の特約を盛り込む際の注意点
賃貸契約書は、賃貸人と賃借人が重要事項説明の読み合わせによる義務を果たして、その内容や注意事項などを理解した上で合意し契約を交わします。敷金償却のような特別な条件を必要とする場合には特約をプラスすることで対応が可能です。
敷金償却の特約を盛り込む際のポイントを3つ紹介します。
契約書面で、賃貸人・賃借人の双方が合意していること
敷金償却の特約は、賃貸人・賃借人、双方が合意しているかどうかがポイントになります。
前出した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の平成23年の判例の一部を以下に引用します。
“賃貸借契約に敷引特約が付され、賃貸人が取得する事ことになる金員(いわゆる敷引金)の額について契約書に明示されている場合には、賃借人は賃料の額に加え、敷引金の額についても明確に認識した上で契約を締結するのであって、賃借人の負担については明確に合意されている”
つまり特約事項が盛り込まれた契約書が取り交わされている時点で、賃貸人・賃借人の双方が、敷金償却に合意していると判断されます。
敷金償却金が適正かどうか
また、敷金償却金が法外に高額ではないこともポイントです。
前項で、「家賃の2.5~3ヶ月分までの償却金であれば問題ない」と紹介しましたが、こちらも先ほどの平成23年の判例の一部を紹介します。
”本件契約における賃料は 9 万 6000 円であって、本件敷引金の額は、上記経過年数に応じて上記金額の 2 倍ないし 3.5 倍強にとどまっていることに加えて、賃借人Xは、本件契約が更新される場合に1か月分の賃料相当額の更新料の支払い義務を負う他には礼金等他の一時金を支払う義務を負っていない。そうすると、本件敷引金の額が高額に過ぎると評価することはできず、本件特約が消費者契約法 10 条により無効であるということはできない。”
「消費者契約法 10 条」とは、規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。という法律で、賃借人は敷金償却が不当に消費者を害するものだとして訴訟を起こしました。しかし結果として、賃料の2~3.5倍までの敷金償却(敷引金)は、適正であるとは判決づけられています。
礼金を受け取っていた場合は認められない可能性がある
先ほど引用した判例の中で、”賃借人Xは、本件契約が更新される場合に1か月分の賃料相当額の更新料の支払い義務を負う他には礼金等他の一時金を支払う義務を負っていない。”という一文があります。
つまり、賃借人は礼金等の一時金を支払う義務を負っていないからこそ、敷金償却が認められたと解釈することができます。
つまり、入居時に礼金を支払う契約になっている場合は、敷金償却が認められない可能性があるため注意しなければなりません。
敷金償却の仕訳
仕訳とは、会計上で整理をするための取り決めであり実務的な分類方法によるものです。賃貸経営いおいて、敷金と敷金償却の意味の違いを理解して仕訳を分類していきましょう。
異なる勘定科目
勘定科目とは取引をわかりやすくするため内容によって種類ごとにまとめる見出しのようなものです。大きく分けると資産や負債、資本および費用や収益などがあり、さらに細かく分類したものに該当します。仕訳は複式簿記による処理をおこなう場合に「借方」と「貸方」で記帳される方法であり、その内容から異なる勘定科目で処理していきます。
仕訳のルール
複式簿記には記帳のためのルールとしてあるので計算が得意ではない大家や管理者もある程度の理解が必要です。表の左側に借方を記載し右側には貸方を記載する配置となっています。大まかにわけた5つの項目での取り決めは以下のルールです。
○資産および費用の増減
増えるときに借方に記載し減るときに貸方に記載します。
○負債の場合や資本および収益の増減
この場合に逆になり、増えるときに貸方となり減るときに借方です。
| 日付 | 借方 | (対象は記帳しない) | 貸方 |
| 例4月1日 | 資産の増加 | 【資産】 | 資産の減少 |
| 例4月2日 | 費用の増加 | 【費用】 | 費用の減少 |
| 例4月3日 | 負債の減少 | 【負債】 | 負債の増加 |
| 例4月4日 | 資本の減少 | 【資本】 | 資本の増加 |
| 例4月5日 | 収益の減少 | 【収益】 | 収益の増加 |
※実際の表での対象を省く
敷金償却による仕訳の会計処理
敷金の場合に返還される金額なので差入保証金の科目で資産として振りわけます。一方で、返還されない償却金については、繰延資産の意味を持ち長期前払費用の科目で資産として振りわけます。
契約上では返還しないことに対し前もって確定しているので、記帳する時期は契約時になっています。
この長期前払費用を月割償却により計上する場合として、償却期間は5年が原則ですが、契約の更新の必要がある場合に賃貸借期間に合わせて償却期間を決めています。この場合の金額が20万円未満になるときに経費にしています。
契約期間中や契約終了の会計処理
仕訳で注意したいのが、中途で契約を解除する場合や値下げなどで一部返還をする場合の処理について預かり金と同じように差入保証金の科目で処理をおこないます。
契約終了の場合に返金以外の敷金を計算したうえで、全額返還のときに収益とならないので費用の変動になりませんが、減額した費用の返還には減額分を収益とします。このように仕訳のルールを適用すれば敷金償却は「収益の増減」で会計処理をすることを理解しましょう。
【手間のかかる入力は一切不要で収支管理が可能に!】
- 毎月の収支や稼働状況を分析するためのデータ入力は事務局が代行
- 月額利用料&登録料が0円だから経費がかからない
- PCやスマホからいつでも賃貸経営の状況をチェックすることができる
ビズアナオーナーは、毎月の収支管理を無料で自動化したい不動産オーナー様におすすめです!