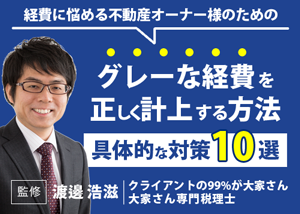不動産投資1年目の確定申告。初年度ならではの注意点とは

一般的な給与取得者の場合には勤務先により源泉徴収が行われるため、住宅ローン控除などの還付を目的とした申告以外に、確定申告を行うケースは多くありません。
しかし、不動産投資を開始した場合には、確定申告が必要になります。今回は、不動産投資1年目の投資家に必要な確定申告について解説します。
不動産投資1年目でも確定申告が必要か

まずは不動産投資1年目の方が押さえておくべき確定申告の注意点についてみていきましょう。
不動産投資1年目の確定申告の注意点
不動産投資を始めれば、個人・法人を問わず1年目から確定申告が必要になると覚えておきましょう。
場合によっては「赤字なのに確定申告が必要なの?」と気になるところですが、不動産収支が赤字の場合には、赤字申告による税金の還付が受けられるため、いずれにしても申告が必要です。還付申請については後述します。
不動産投資における所得税申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
初年度で、特に注意したいのは「青色申告」を行うかどうかです。
白色申告と比較すると、青色申告は「青色申告特別控除」や「青色専従事業者」の人件費を必要経費から差し引けるなど、税制上のメリットがあります。
一方で、青色申告をする際は、「現金出納帳」や「損益計算書」「貸借対照表」などの書類を、正確に記載して提出することが義務付けられています。そのため、税理士に確定申告を依頼する場合を除き、それなりの税務知識が必要とされます。
初年度から青色申告を行う場合には、開業から2か月を期限として「青色申告承認申請書」を、所轄税務署長あてに提出しなければなりません。
初年度を「白色申告」として、翌年度以降に「青色申告」に切り替えることもできますが、申告になれておく意味でも、当初から検討しておくのが望ましいでしょう。
初年度の税金計算
不動産所得は、総合課税が原則です。総合課税とは、対象となる所得を合算し、所定の税率をかけて総合的に税額を計算する方式のことです。
不動産投資の場合、家賃などの収入から必要経費を引いたものが所得です。原則として申告の種別を問わず帳簿作成や税額計算は、会計ソフトを利用するなどして自分で行います。これらを証明するような銀行通帳、領収書などの書類もきちんと保存しておきましょう。
なお、不動産所得に関する確定申告は毎年2月16日から3月15日です。所得計算は前年度1月1日から12月31日までとなりますので、初年度については事業開始月からの計算が必要となります。
2020年については、新型コロナウイルスによる影響により締切が延期されました。いつまでに申告しなくてはならないのか、事前に確認しておきましょう。
不動産投資1年目の方が知っておくべきポイント

不動産投資を始めて1年目の方にとって、確定申告は大きな関門となります。初めての確定申告では、収入の計上方法から経費の処理まで、多くの不安要素があるでしょう。
ここでは、特に重要なポイントについて詳しく解説していきます。
家賃収入が1年間で20万円以上の場合は確定申告が必須
不動産投資による家賃収入が年間20万円を超える場合、確定申告は法律で定められた義務となります。この基準額は、副業などの事業所得と同様の基準が適用されます。たとえば、月額2万円の家賃収入がある場合、年間では24万円となるため、必ず確定申告が必要です。
また、複数の物件を所有している場合は、すべての物件からの収入を合算した金額が基準となります。そのため、1物件あたりの家賃収入が少額であっても、合計で20万円を超える場合は申告が必要となることに注意が必要です。
収入として計上すべき項目と除外できる項目
不動産収入として計上すべき項目は、単純な家賃収入だけではありません。礼金や更新料なども課税対象となる重要な収入項目です。礼金は入居時の一時金として受け取りますが、これは確実な収入として認識され、受け取った年度の収入として申告する必要があります。
更新料についても同様で、契約更新時に受け取る更新料は、受け取った年度の収入として計上します。これらの収入は、通常の家賃収入と同様に課税対象となります。
一方、敷金や保証金については、状況によって収入計上の要否が変わってきます。原則として、これらは預り金として扱われ、退去時に返還することを前提としているため、受け取った時点では収入として計上する必要はありません。ただし、退去時に原状回復費用として充当する部分や、返還しない部分については、その時点で収入として計上する必要があります。
税務署による記載漏れの指摘について
多くの初心者が陥りやすい誤解として、「税務署が記載漏れを指摘してくれる」というものがあります。しかし、実際には税務署は必ずしもすべての誤りや漏れを指摘するわけではありません。確定申告は自己申告が原則であり、正確な申告を行う責任は納税者自身にあります。
そのため、日々の収支管理が非常に重要となってきます。特に収入に関する書類や経費の領収書などは、確定申告時に必要となるだけでなく、後日の税務調査の際にも求められる可能性があるため、適切に保管しておく必要があります。
不動産投資1年目の確定申告でよくある失敗

初めての確定申告では、経験不足から様々な失敗が発生しやすいものです。
ここでは、特に注意が必要な失敗例とその対策について詳しく解説していきます。これらの失敗を事前に理解することで、スムーズな確定申告が可能となります。
必要書類の不足や記載不備
確定申告において最も多い失敗が、必要書類の不足や記載不備です。特に不動産所得の申告では、収支内訳書の添付が必須となりますが、これを忘れてしまうケースが少なくありません。
また、減価償却の計算も複雑で誤りやすい項目の一つです。建物の取得価額や耐用年数の設定を間違えると、その後の申告にも影響が及ぶため、特に慎重な確認が必要です。
さらに、契約書や領収書の紛失も深刻な問題となります。これらの書類は、収入や経費の証明として非常に重要です。特に経費として計上する項目については、その裏付けとなる領収書等の保管が必須となります。
経費計上の見落とし
不動産投資における経費は多岐にわたります。物件の管理費用、火災保険料、固定資産税などの定期的な支出に加え、修繕費やメンテナンス費用なども経費として認められます。また、不動産取得時のローン関連手数料も、適切に処理することで経費として計上できる場合があります。
これらの経費を見落としてしまうと、必要以上に課税所得が多くなってしまい、結果として納税額が増えてしまう可能性があります。特に初年度は、どの項目が経費として認められるのか、十分な知識がない状態で申告を行うことになるため、注意が必要です。
収支記録の不備
確定申告を正確に行うためには、日々の収支記録が不可欠です。特に不動産所得の場合、毎月の家賃収入や経費の支払いなど、定期的な取引が発生します。これらを適切に記録し、管理することが重要です。
収支の記録は、専用の帳簿を用意して行うことをお勧めします。最近では、クラウド会計ソフトなどのデジタルツールも充実しており、これらを活用することで効率的な管理が可能です。特に青色申告を選択する場合は、複式簿記による記帳が求められるため、このようなツールの活用は非常に有効です。
青色申告の要件未達
不動産所得の確定申告では、青色申告を選択することで最大65万円の特別控除を受けることができます。しかし、この青色申告には厳格な要件があり、これを満たせないケースも少なくありません。
まず、青色申告を行うためには事前に申請手続きが必要です。この申請を忘れてしまうと、その年度は青色申告を行うことができません。また、複式簿記による記帳や期限内の申告書提出なども重要な要件となります。
不動産投資での節税方法とは

できる限り税金を少なく抑えたいと思うのは当然のことです。
ここでは、不動産投資初年度における節税の方法について紹介します。また、初年度のみならず、2年目以降にも大切な節税の考え方もあわせて確認しましょう。
不動産投資で赤字が出たときの損益通算
不動産投資の場合、それ以外に本業を持っている人もいます。サラリーマン大家さんなどが典型例でしょう。
物件の購入初年には、物件価格のほかにも多くの必要経費がかかるものです。費用がかさむと、その年は赤字になる可能性があります。
本業が黒字、不動産投資が赤字の場合に、不動産投資の赤字を本業の所得から差し引いて税金の計算をすることが可能です。それが損益通算です。
| 本業(給与所得) | 不動産所得 | 損益通算後の所得 |
| 1,000万円 | ▲300万円 | 700万円 |
上の例では、本来は給与所得1,000万円に対して課税がされるはずですが、不動産所得の赤字を控除して700万円にまで所得が減額されています。
不動産投資での損益通算の条件
不動産投資で損益通算をするにはいくつかの条件があります。主な条件は以下の2点です。
-
- 合算するのが給与所得、利子所得、配当所得、雑所得であること
- 不動産所得が赤字であること
1つ目は、決められた所得であることです。給与所得とは事業者などからの給与による所得です。利子や配当は貯金や株式の配当による所得のことです。雑所得は他の所得に入らないような、年金、印税、講演料などです。
他の事業を営んでいる場合の事業所得や、売買で得た譲渡所得は対象外です。
2つ目は、不動産所得が赤字であることです。実際の赤字だけでなく、会計上の赤字も含みます。つまり、減価償却費のような実際の支出をともなわない費用を含めて、赤字となっていることが条件です。
2年目以降もできる節税方法
費用を、正しく記録して計上するのが節税の基本です。
必要経費に算入できる物は、その根拠も含めて正しく記録しましょう。必要経費には、以下のような項目があります。
-
- 管理費
- 共益費
- 修繕費
- 租税公課(固定資産税、都市計画税、登録免許税、不動産取得税、印紙代、事業税など)
- 建物減価償却費
- 損害保険料
- ローンの金利(ローンで収益物件を購入した場合の金利のみ。元金は算入できません)
- 交通費や交際費(建築や管理会社との打ち合わせに要した交通費や、飲食費など支出目的が明確なもの)
- 通信費(運営に関しての電話代やネット通信費、プロバイダ代、切手代など)
- 広告宣伝費(賃借人を応募するために要した広告費など)
- 書籍代(運営に必要とされる調査などに要した書籍や新聞代など)
- 消耗品費(広告に必要な写真撮影費用や印刷代など)
- 税理士費用
- 水道光熱費(建物維持管理に要した水道費費や光熱費など)
- 青色専従事業者人件費(青色申告のみ)
一見すると関係のない費用でも必要経費として認められるものもあります。これらの項目を精査し、不動産投資に関連するものは必要経費として計上しましょう。
また、「青色申告」の場合には、以下のような控除が認められています。
-
- 青色申告特別控除(青色申告のみ・最大65万円の特別控除)
- 3年間の赤字繰り越し(青色申告のみ)
- 少額減価償却資産の特例(青色申告のみ・30万円未満の固定資産原価償却を一括処理できる)
- 貸倒引当金の一括評価(青色申告のみ)
確定申告を怠った場合のペナルティ

確定申告は法律で定められた義務であり、これを怠ると様々なペナルティが課されることになります。
ここでは、申告を行わなかった場合や、不適切な申告を行った場合のペナルティについて解説します。
加算税・延滞税について
確定申告を行わなかった場合、まず課されるのが無申告加算税です。これは本来納めるべき税額の15%から20%が追加で課税されるものです。また、納付が遅れた場合には延滞税も加算されます。
過少申告の場合も同様に、過少申告加算税が課されます。これは、申告額が実際の税額より少なかった場合に、その差額に対して課される追加の税金です。特に意図的な過少申告と判断された場合は、加算税率が高くなる可能性があります。
重大なケースの処罰
特に悪質な場合、脱税として刑事罰の対象となることもあります。故意に所得を隠ぺいしたり、虚偽の申告を行ったりした場合は、最高で10年の懲役刑が科される可能性があります。また、情状により罰金刑が科されることもあります。
これらの処罰は、単なる過失による申告漏れとは異なり、意図的な脱税行為に対して適用されるものです。そのため、確定申告は常に誠実に行い、不明な点がある場合は税理士等の専門家に相談することが推奨されます。
ペナルティが軽減されるケース
一方で、すべての申告漏れや遅延が厳しく罰せられるわけではありません。例えば、自主的に修正申告を行った場合や、期限超過に正当な理由がある場合は、比較的寛容な対応を受けられる可能性があります。
特に初回の無申告で、その金額が軽微な場合は、加算税が減免されることもあります。ただし、これはあくまでも例外的な措置であり、確定申告は原則として期限内に正確に行うことが求められます。
不動産投資の確定申告での還付について
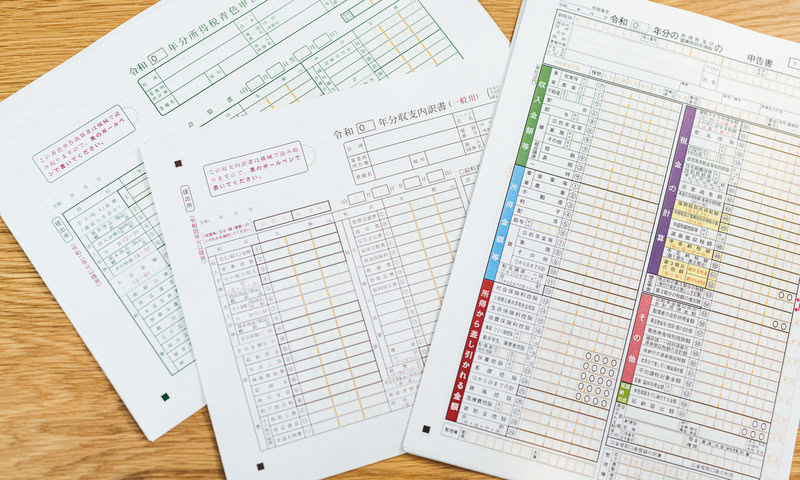
不動産投資における確定申告では、適切な申告を行うことで税金の還付を受けられる場合があります。
ここでは、特に重要な還付のケースについて解説します。
損益通算による還付
先述のように、不動産所得が赤字になったときに確定申告をすると、不動産所得と給与所得を合算して計算をするため、全体の所得が下がります。
給与所得は源泉徴収されているため、損益通算によって還付金を受けることができます。
消費税の還付
不動産投資初年度は、建物に大きな消費税が課されています。そのため、消費税の還付が考えられます。簡単な例で説明します。
年間1,000万円の課税売上がある事業者が、新たに5,000万円の投資物件を購入した場合、受け取った消費税100万円に対して、支払った消費税は500万円です。この差額が、還付金として戻るのです。
「所得税の還付」
所得税は、例年2月16日から3月15日が申告期間ですが、還付の場合は対象年の翌年1月1日を起算日として5年間まで申請が可能です。
そのため、税務署や税理士が混雑する時期を避けて申請書を作成することもできますが、申請が遅れれば当然として還付される時期も遅れます。還付の申請については、自分で時期を定めておくなど管理しておくと良いでしょう。
還付金は、還付されるまでに時間を要します。電子申告e-Taxを活用すれば、紙の申告より早く還付がされるので、急ぎの方はe-Taxがおすすめです。また、還付金の主な受け取り方法は銀行振り込みや郵便局の窓口です。
住民税の還付(2年目以降)
住民税は前年度の所得に基づいて課税されるため、不動産投資による損失が発生した場合、翌年度の住民税が還付される可能性があります。これは特に2年目以降の投資家にとって重要な還付機会となります。
還付を受けるためには、適切な損益通算を行い、確定申告時に必要な手続きを行う必要があります。還付申請の手続きは比較的簡単ですが、必要書類の準備や計算方法については、事前によく確認しておくことが推奨されます。
以上、不動産投資1年目の確定申告における重要なポイントについて解説しました。これらの知識を踏まえ、適切な申告を行うことで、不要なペナルティを避け、可能な還付も受けることができます。不明な点がある場合は、必ず税理士等の専門家に相談することをお勧めします。
確定申告に役立つ情報を知るなら「ビズアナオーナー」
当社が提供している無料の収支管理サービス「ビズアナオーナー」は、賃貸経営を行っているオーナーが利用する無料の収支管理サービスです。
月々の収支データを無料で簡単に自動でデータ化し、わかりやすいビジュアルで経営状況を把握することができます。
また、ビズアナオーナーの会員限定で、補助金や節税、空室対策に関する最新の情報やダウンロード資料なども随時配布しています。
その他にも、賃貸経営に役立つサービスも特別価格や無料で利用いただくことが可能です。
是非、「ビズアナオーナー」を無料登録してみてください。
【確定申告に役立つコンテンツをラインナップ!】
- 収支報告書を事務局に送るだけで毎月の収支管理ができる!しかも無料!
- 確定申告対策など不動産オーナーのためのセミナーアーカイブ動画が無料で視聴できる
- AI賃料査定レポートサービスなど不動産投資に役立つメニューがお得に利用できる
ビズアナオーナーは、毎月ラクして収支管理を行いながら確定申告にも慌てず備えたい不動産オーナー様におすすめです!