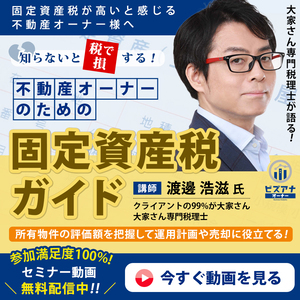固定資産税の節税方法を分かりやすく解説!計算方法や安くするポイントとは

賃貸経営において、毎年発生する固定資産税の負担が大きいと感じる方は多いかもしれません。
しかし、固定資産税の仕組みを理解し、自分に合った節税方法を選択することで税負担を軽減することができます。
税額の計算方法や経費への計上、さらに活用できる特例まで、オーナーだからこそ知っておきたい実践的なポイントをまとめました。記事の情報を活用して賢く節税することは、利益を増やすことにつながるでしょう。
固定資産税の節税に必要な基本情報
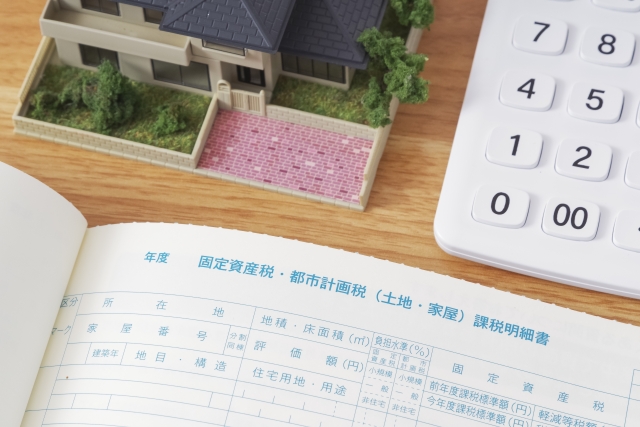
賃貸物件のオーナーにとって、固定資産税は毎年必ず発生するコストです。適切に節税対策を行うためには、まず固定資産税の基本的な仕組みを理解することが重要になります。
固定資産税の概要から計算方法、賃貸経営における特徴まで、節税を検討する上で欠かせない基本情報を詳しく解説いたします。
固定資産税とは何か
固定資産税は、毎年1月1日時点の土地、家屋または償却資産などの固定資産を所有している人に対して、市町村から課税される税金です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課税対象者 | 1月1日時点で不動産を所有している人 |
| 対象物件 | 土地・建物・事業用設備など |
| 標準税率 | 1.4% |
| 納付回数 | 年4回 |
固定資産税は物件の所有者に課税されるため、賃貸物件に入居者が住んでいるかどうかに関係なく、オーナーに課税されます。
納付は基本的に年4回の分割納付となりますが、一括での納付も可能です。資金繰りに合わせて選択するとよいでしょう。
参考:総務省 | 地方税制度|固定資産税の概要
固定資産税の金額の内訳
固定資産税の税額は、以下の計算式により決定されます。
【固定資産税の計算式】
固定資産税額 = 固定資産税評価額× 税率(1.4%)
「固定資産評価額」は、総務省が定めた固定資産評価基準を基準に市町村が決めますが、土地と建物によって評価方法は異なります。
以下の表にそれぞれの評価方法をわかりやすくまとめました。
| 区分 | 評価方法 | 特徴 |
|---|---|---|
| 土地 | 路線価方式 | 街路ごとの単価×面積で算出 |
| 建物 | 再建築価格方式 | 同じ建物を新築する費用から経年劣化を差し引き |
固定資産評価額では、一般的に土地と建物は別々に評価されます。
土地は公示価格(国土交通省が公表している土地の取引基準)の約70%といわれています。一方、建物については再建築価格(同じ場所に新築した場合の標準的な評価額)を基準とし、工事費の50〜60%程度に設定されています。
ただし、地域や個別の事情によって価格は大きく異なるため、あくまで目安と考えてください。
仮に、固定資産税評価額が3,500万円だった場合の固定資産税は以下のとおりです。
3,500万円×1.4%=49万円
ちなみに固定資産税評価額は、原則3年ごとに評価額が見直されています。つまり、不動産の評価は3年に1度変わるということです。
参考:総務省|地方税制度|固定資産税
賃貸経営では固定資産税を経費にできる
賃貸物件のオーナーは、固定資産税を経費として計上できるため、節税効果を得ることができます。
なぜなら、不動産所得を計算する際、固定資産税は「租税公課」として経費に含まれるからです。経費として計上することで課税所得が減少し、最終的には所得税や住民税の負担が軽減されます。
この仕組みを活用することで、オーナーは実質的に手元に残る利益を増やすことが可能です。
固定資産税が50万円の場合、経費計上したときの具体的な効果を以下にまとめました。
| 項目 | 税率(仮置き) | 金額 |
|---|---|---|
| 所得税 | 20% | 10万円 |
| 住民税 | 10% | 5万円 |
| 合計 | 15万円 |
また、固定資産税以外にも以下の税金を経費として計上できます。
- 固定資産税
- 都市計画税
- 不動産取得税
- 印紙税(賃貸借契約書など)
賃貸物件のオーナーは、税金を適切に経費計上することで利益を残すことができます。
参考:国税庁 | No.2215 固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合
関連記事:アパート経営の年間経費。経費で落とせるものには何がある?
収益物件における固定資産税の計算方法
収益物件の場合、固定資産税の計算方法に注意しなければなりません。住宅用地の固定資産税を計算する際の課税標準は以下の通りです。
| 項目 | 対象 | |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地 | 住宅1戸につき200㎡以下の部分 | 価格×1/6 |
| 一般住宅用地 | 住宅1戸につき200㎡を超える部分 | 価格×1/3 |
住宅用地(賃貸アパートやマンションを含む)の場合、200㎡以下の小規模住宅用地であれば課税標準額が最大1/6まで軽減されます。200㎡以上ある一般住宅用地の場合は最大1/3まで軽減が可能です。
上記はあくまで住宅用地の特例であり、事業用地や商業地の場合は適用されないため注意してください。
参考:東京都主税局 | 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)|不動産と税金
固定資産税を節税するための具体的な方法

固定資産税は不動産の所有者に毎年発生するため、少しでも費用を抑えたい方は多いのではないでしょうか。
固定資産税を節税する方法を3つご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
共同住宅用の特例制度を利用する
固定資産税を節税する方法の1つ目は、「共同住宅用の特例制度の利用」です。
例えば、新築住宅の場合、固定資産税を3年間(マンションなどの場合は5年間)、2分の1に減額されます。
| 建物 | 減額期間 | 減額割合 | 対象面積 |
|---|---|---|---|
| 一般住宅 | 3年間 | 2分の1 | 120㎡まで |
| マンション | 5年間 | 2分の1 | 120㎡まで |
| 認定長期優良住宅 | 5年間 | 2分の1 | 120㎡まで |
なお、4年目以降(マンションなどの場合は6年目以降)は、元の税率が適用されます。
最後に、この特例は建築時期によって適用される時期が変化します。なぜなら、固定資産税は1月1日時点の所有者に課税される税金だからです。
不動産の所有時期が1月1日より後になる場合、適用される時期は翌年度からとなります。
参考:東京都主税局 | 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)|不動産と税金
土地を分筆(土地を複数に分ける)する
固定資産税を節税する方法の2つ目は、「土地の分筆」です。
土地の分筆とは、1つの土地を複数の土地に分割することを指します。
特に、所有している土地面積が大きい場合、分筆することで小規模住宅用地の特例適用面積を増やすことが可能です。
1,000㎡の土地に10個のアパートを建築する場合に、分筆する場合としない場合を比較してみました。
| 状況 | 土地の面積 | 特例の適用範囲 |
|---|---|---|
| 分筆をしない場合 | 200㎡以下 | 小規模住宅用地特例が適用(価格×1/6) |
| 201~400㎡ | 一般住宅用地特例が適用(価格×1/3) | |
| 分筆をする場合 | 各部屋(200㎡以下) | 各部屋に小規模住宅用地が特例(価格×1/6) |
上記の表のとおり、分筆することで固定資産税の大きな節税効果が見込めます。
ただし、土地の分筆をするためには測量費用や登記費用などの初期コストが発生します。また、賃貸物件の売却を考えている場合は、将来売りにくくなる可能性もあるため、事前によく検討することが大切です。
参考:国税庁 | 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に係る相続税の申告書の記載例等について(情報)」(令和3年4月1日)
法人化を検討する
固定資産税を節税する方法の3つ目は、「法人化」です。賃貸事業の規模が大きくなると、法人化することで節税効果が期待できます。
理由は、個人と法人では税務上の取り扱いが大きく異なるためです。
| 項目 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 所得税率 | 最大45% | 23~34% |
| 経費の範囲 | 限定的 | 広い |
| 減価償却 | 限定償却 | 任意償却 |
| 欠損金の繰越 | 3年間 | 10年間 |
固定資産税自体の税率は個人・法人で差はありません。法人化することで経費の範囲が広がり、所得分散による税負担の軽減など節税効果が期待できます。
ただし、法人設立費用や税理士費用、社会保険料負担などの維持コストも発生するため、年間所得が1,000万円を超える規模になってから検討するのが一般的です。
固定資産税を節税するときの注意点

節税により固定資産税のコストを抑えられますが、気をつけるべきことも多数あります。
賃貸物件のオーナーが理解しておくべき注意点について詳しく見ていきましょう。
固定資産税が確定する前に対応する
先述したように、固定資産税は原則として3年ごとに見直されます。そのため、以下の軽微な変更の場合、翌年の固定資産税を節税できない可能性があります。
- 小規模なリフォーム
- 原状回復の範囲内修繕
- 建物の部分的な用途変更
直近では令和6年に固定資産税の見直しが発生したため、次の評価替えは令和9年です。上記の変更を行っても固定資産税に影響は出ないでしょう。
一方、土地の分筆や建て替えといった大規模な変更が発生した場合は、年度の途中でも固定資産税が再計算されます。
固定資産評価額は3年に1回の見直しになることを念頭に置いておきましょう。
参考:総務省|地方税制度|固定資産税の令和3年度評価替えへの対応
節税コストと初期費用を比較する
固定資産税を節税するためにはコストがかかることが多いため、節税効果と発生するコストを比較する必要があります。
節税するためのコストや初期費用の方が高くなってしまう場合は、節税対策を見送るのも一つの選択肢です。参考として、節税対策で発生する主なコストを表にまとめました。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 分筆・測量費 | 50~100万円程度 |
| 法人設立費用 | 20~30万円 |
| 法人の年間維持費 | 100万円程度 |
| 専門家相談 | 月額5~10万円程度 |
また、節税対策をすることで将来的なデメリットが発生するケースもあるため注意が必要です。例えば、土地の分筆は節税効果がある一方で、売却時に買い手が見つかりにくくなる可能性があります。
固定資産税の節税対策をする際は、必ず発生するコストと比較しましょう。
固定資産税の支払いを滞納しないようにする
節税の方法ではありませんが、固定資産税の支払いを滞納しないことも重要です。もし滞納してしまうと、以下のペナルティが発生してしまい、必要以上のコストが発生してしまいます。
- 督促状の送付
- 最大14.6%の延滞金の発生
- 不動産や預貯金などの財産の差し押さえ
固定資産税は、毎年4月〜5月ごろに市町村から通知が届きます。支払い期限が記載されているため、期日までに必ず納付してください。
振り込み忘れが不安という方のために、銀行口座からの引き落としにすることもできます。最悪の場合、所有する不動産を競売にかけられてしまうため、固定資産税は必ず納付するようにしましょう。
参考:国税庁 | 延滞税の計算方法
固定資産税に役立つ情報を知るなら「ビズアナオーナー」
当社が提供している無料の収支管理サービス「ビズアナオーナー」は、賃貸経営を行っているオーナーが利用する無料の収支管理サービスです。
月々の収支データを無料で簡単に自動でデータ化し、わかりやすいビジュアルで経営状況を把握することができます。
また、ビズアナオーナーの会員限定で、補助金や節税、空室対策に関する最新の情報やダウンロード資料なども随時配布しています。
その他にも、賃貸経営に役立つサービスも特別価格や無料で利用いただくことが可能です。
是非、「ビズアナオーナー」を無料登録してみてください。
【賃貸経営にも役立つコンテンツをラインナップ!】
- 収支報告書を事務局に送るだけで毎月の収支管理ができる!しかも無料!
- AI賃料査定レポートで設備による賃料の増減を簡単に把握できる
- 固定資産税・確定申告などの税対策のコツが学べるセミナーが見放題!
ビズアナオーナーは、賃貸経営のスキルを身につけたい不動産オーナー様におすすめです!