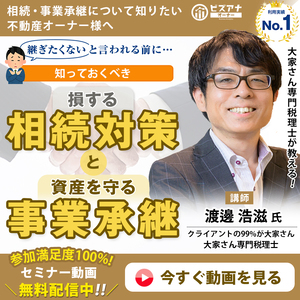不動産を活用した相続税対策とは?基礎から具体的な節税方法まで解説

相続では、現金を多く残すと相続税の負担が大きくなることがあります。そこで注目されているのが「不動産による相続税対策」です。土地や建物は現金よりも評価額が低く算出されるため、相続税を抑えられる可能性があります。
さらに、国の特例制度を活用することで、大幅な節税効果を得られるケースも少なくありません。相続後に慌てることのないよう、仕組みを理解しながら最適な方法を考えましょう。
不動産の取得が相続税対策になる理由

「現預金をそのまま遺すよりも、同額の不動産を購入して相続財産にするほうが相続税対策になる」と聞いたことがある人も多いでしょう。
結論として、不動産の取得が相続税対策になる可能性が高いのは事実です。その理由として、相続税評価額の計算方法が挙げられます。
相続税を計算するためには、最初に課税対象となる相続財産の評価額の計算が必要です。評価額の計算方法は財産の種類ごとに決められています。
相続税計算において、不動産は時価ではなく「相続税評価額」とよばれる評価額を用いています。不動産の相続税評価額は、時価の7〜8割程度の金額になるのが一般的です。仮に1億円の不動産を購入した場合、相続税評価額は7,000万円〜8,000万円ほどになるということです。
1億円を現預金のまま相続した場合、1億円全額が相続税の課税対象になります。価値としては同じ1億円でも、現預金の状態より不動産の方が課税対象が少ないため、税額も低くなるのです。
以上の理由から、現預金を相続財産として遺すよりも、同額の不動産を取得する方が相続税対策になるといわれています。
不動産の相続税評価額を決める要素とは?
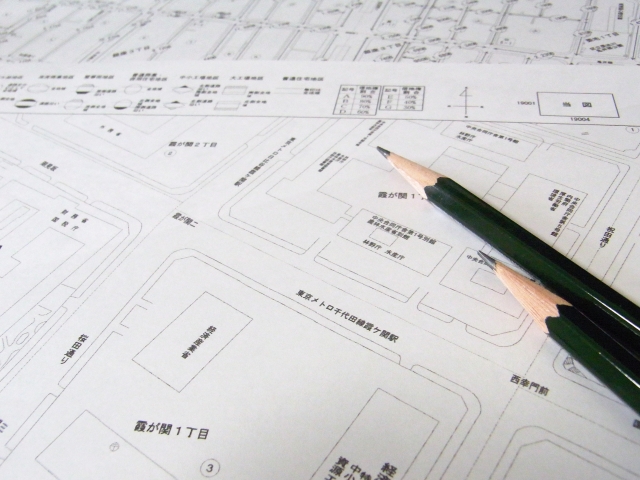
不動産の相続税評価額の計算方法は土地と建物で異なります。それぞれの評価方法や、相続税評価額の計算において重要な要素について解説します。
土地の評価方法
土地の評価方法は「路線価方式」と「倍率方式」の2種類があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
路線価方式
路線価とは、路線(道路)に面する土地1平方メートルあたりの評価額のことで、国税庁が公表している「路線価図・評価倍率表」で確認できます。路線価方式は、路線価が定められている土地の相続税評価額を計算する方法で、計算式は以下の通りです。
土地の相続税評価額=路線価 × 各種補正率 × 土地の面積
路線価は一般的に公示価格の8割に設定されています。各種補正率とは、土地の形状などに応じて評価額を調整するために用いる値です。
補正対象となる土地としては以下の例が挙げられます。
- 奥行きがある
- 間口が狭い
- 不整形(長方形や正方形でない)
- 地積が一定規模を超える
何らかの理由により使い勝手が悪い土地は、補正対象になると考えてよいでしょう。補正率の適用により土地の相続税評価額は低くなります。
補正の適用可否および使用する補正率の判断には専門知識が必要であり、計算ミスや漏れが起こりやすい部分です。補正対象となる条件を満たしている場合、相続税に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
倍率方式
倍率方式とは、路線価の設定がない土地の相続税評価額を計算する方法です。倍率も前述の路線価と同じく、国税庁の「路線価図・評価倍率表」で確認できます。
倍率方式による相続税評価額の計算方法は以下の通りです。
土地の相続税評価額=固定資産税評価額 × 倍率
たとえば、固定資産税評価額が5,000万円、倍率が0.9の土地の場合、相続税評価額は5,000万円 × 0.9=4,500万円になります。
一般的に、固定資産税評価額は土地の形状や使い勝手などの個別的事情を考慮した上で算出されます。そのため前述の路線価方式と違い、倍率方式では原則として補正の適用による評価減は行いません。
建物の評価方法
建物の相続税評価額を算出するときは以下の計算式を使用します。
建物の相続税評価額=固定資産税評価額 × 1.0
上記の方法は、相続税評価額の計算方法として定められてはいるものの、実際は固定資産税評価額と同額になります。つまり、固定資産税評価額=相続税評価額ということです。
なお、固定資産税評価額は時価(公示地価)の70%程度が目安です。したがって建物の相続税評価額も時価の70%程度となります。
固定資産税評価額は以下の方法で確認できます。
- 自治体から送付される固定資産税の課税明細書で確認する
- 役所で固定資産課税台帳を閲覧する
- 役所に申請して固定資産税評価証明書を取得する
確認の仕方が分からない場合は、役所の担当者に相談してみるとよいでしょう。
不動産を取得したときのおすすめ相続税対策

不動産は性質上、相続税評価額が高額になるケースがあります。相続不動産の評価額や現預金の額によっては「相続財産は多いけれど、現金が少ないために納税資金が足りない」といった事態も起こり得ます。
一方で、相続税には不動産の評価額を減額できる仕組みや特例が多く設けられています。活用することで税額が変わり、大きな節税効果を得ることが可能です。
不動産を取得したときの相続税対策としておすすめの手法をご紹介します。
小規模宅地等の特例を利用する
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たす宅地を相続や遺贈によって取得した場合に、評価額を最大80%減額できる国の特例です。
評価額の減額割合は宅地等の種類別に以下のように定められています。
| 相続開始直前における宅地等の利用区分分類 | 限度面積 | 減額される割合 | |
|---|---|---|---|
| 居住用 | 特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
| 貸付事業用 | 貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
| 貸付事業以外の事業用 | 特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
| 特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡ | 80% | |
出典:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁
貸付事業用の宅地は50%、それ以外の宅地は80%の減額を受けられます。
小規模宅地等の特例が適用される要件は、宅地の種類や相続人の状況などによって異なります。詳しくは国税庁の公式サイトをご確認ください。
住宅取得等資金の贈与の特例を利用する
住宅取得等資金の贈与の特例とは、以下の要件を満たす場合に適用を受けられる制度です。
- 父母や祖父母など直系尊属からの贈与である
- 自己(受贈者)の居住用財産の取得や増改築などの金銭の贈与である
取得する居住用財産が省エネ等住宅(国の基準に一致する住宅)の場合は1,000万円まで、それ以外の住宅は500万円までが非課税になります。
なお、住宅取得等資金の贈与の特例は、名前のとおり贈与税の特例制度です。また、不動産そのものを取得した場合ではなく、不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合に利用できる制度です。そのため厳密には「不動産を取得したときの相続税対策」ではありません。
しかし、以下の理由から相続税対策としても活用できる制度といえます。
- 同額の不動産を相続するよりも特例制度を活用して取得資金を贈与する方が、結果として相続税が軽減される可能性がある
- 「住宅取得資金贈与の特例」を適用した部分は、相続財産に加算する生前贈与に含まれない
自己の居住用財産の取得や増改築などによる金銭の贈与では、相続開始前3年以内(法改正後は7年以内)に行われた生前贈与の場合、原則として相続税の課税価格に加算されます。しかし、住宅取得資金贈与の特例の適用を受けた部分は、相続財産の加算対象とはなりません。
税負担なく金銭の贈与ができるため、結果として節税につながるのです。
参考:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁
納税の資金を借り入れる
「不動産の相続によって高額の相続税が発生したため納税資金が足りない」という事態の対処法として、不動産の売却による現金化が挙げられます。
しかし、相続税の納付期限は相続開始の日の翌日から10カ月以内です。不動産の相続手続きが完了してから売却活動を始めても、納付期限までに売却が成立せず現金化が間に合わない可能性があります。
納付期限を過ぎないようにするためには、売却の成立可否に関係なく納税資金の借入が効果的な手段となります。納税資金の借入をすれば「納付期限までに売却を成立させなければ」と焦る必要がありません。
この方法は厳密には節税対策ではありませんが、相続税に関する負担を軽減する方法といえるでしょう。時間的・金銭的な余裕ができることで、より好条件での売却や心理的な負担の軽減が期待できます。
賃貸物件の場合は評価額をより圧縮できる
賃貸物件の相続税評価額は、借地人や借家人の権利である「借地権割合」および「借家権割合」を控除して計算します。賃貸借契約を締結している以上、不動産の使用や売却に制限が生じるためです。
賃貸物件の評価額は以下のように計算します。
-
- 貸宅地:借地権などが設定されている土地
自用地の評価額 -(自用地の評価額 × 借地権割合)
-
- 貸家建付地:貸家の敷地として使用されている土地
自用地の評価額 -(自用地の評価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
-
- 貸家:賃貸している家屋
固定資産税評価額-(固定資産税評価額 × 借家権割合)
参考:No.4614 貸家建付地の評価|国税庁、No.4602 土地家屋の評価|国税庁
利用していない不動産がある場合、放置せずに賃貸物件として活用することで、節税につながります。相続税は計算方法や特例制度の要件が複雑なため、不安がある場合は税理士や不動産会社などの専門家に相談することをおすすめします。
賃貸経営に役立つ情報を知るなら「ビズアナオーナー」
当社が提供している無料の収支管理サービス「ビズアナオーナー」は、賃貸経営を行っているオーナーが利用する無料の収支管理サービスです。
月々の収支データを無料で簡単に自動でデータ化し、わかりやすいビジュアルで経営状況を把握することができます。
また、ビズアナオーナーの会員限定で、補助金や節税、空室対策に関する最新の情報やダウンロード資料なども随時配布しています。
その他にも、賃貸経営に役立つサービスも特別価格や無料で利用いただくことが可能です。
是非、「ビズアナオーナー」を無料登録してみてください。
【賃貸経営にも役立つコンテンツをラインナップ!】
- 収支報告書を事務局に送るだけで毎月の収支管理ができる!しかも無料!
- AI賃料査定レポートで設備による賃料の増減を簡単に把握できる
- 統計調査レポートで周辺の商業施設・教育施設やハザードマップなどの情報が得られる
ビズアナオーナーは、賃貸経営の最新情報を知りたい不動産オーナー様におすすめです!