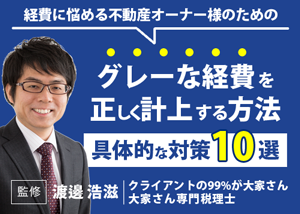家賃収入を確定申告をしていないとどうなる?問題点や対処法

不動産投資をしていると避けて通れないのが確定申告。年度末には「確定申告をしよう」とTVコマーシャルも流れます。この確定申告、家賃収入があると必ずしないといけないのでしょうか。また、確定申告をしないとどうなるのでしょうか。
家賃収入確定申告していない
まずは家賃収入と確定申告の関係についてみていきましょう。
家賃収入の確定申告はいくらから必要か
確定申告の要否にはいくつかの条件があるため、家賃収入があったとしても確定申告そのものが不要の場合もあります。
例えば、不動産所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。
ただし、「家賃収入」ではなく、家賃から経費などを差し引いた「不動産所得」が対象である点に注意です。仮に、家賃や礼金の収入が年間100万円あったとしても、50万円の必要経費がかかっており、さらに基礎控除38万円を引くと不動産所得は12万円です。下表でもう少し詳しくみていきます。
■所得が不動産所得のみの場合の計算例
| ① 年額の家賃収入や礼金 |
② 必要経費 |
③ 基礎控除 |
④ 不動産所得 ①-②-③ |
確定申告の要否 | |
| 例1 | 100万円 | 50万円 | 38万円 | 12万円 | 不要 |
| 例2 | 100万円 | 40万円 | 38万円 | 22万円 | 必要 |
年額の家賃収入や礼金の収入が同じ100万円でも、必要経費が少なければ確定申告が必要な場合もあるのです。収入ではなく、不動産所得で判断することが必要です。
家賃収入の確定申告しないとバレるのか
誰もが、税金は少なくしたいし、できれば払いたくないものです。そのため「家賃収入も少ないし、確定申告しなくてもバレないのではないか」と考えてしまうこともあります。
しかし、この考え方は大変リスクが高いといえます。不動産には多くのステークホルダー(利害関係者)が関わっています。貸主であるあなた以外にも、借主、管理会社、修繕を請け負う会社、金融機関などです。税務署が管理会社や金融機関に調査に入れば、お金の流れや仕事の内容はたちどころにわかってしまいます。
「家賃収入の確定申告しないとバレる?」という質問には、「いつかはバレるからリスクが高い」という返答になるのです。
もし確定申告しなかったらどうなるか
確定申告しないと最悪の場合、脱税(納税義務違反)に該当します。
まず、申告義務のある確定申告を怠ると「過少申告加算税」や「無申告加算税」が課されます。自分で修正申告をすると過少申告加算税は5%、税務署から指摘を受けて修正すると、未納税額が50万円以下の部分が10%、50万円超の部分は20%です。
この他、意図的に脱税した場合には重加算税35%、さらには延滞税もかかります。
それだけではありません。罰金には前科がつきますので、会社員でも免職の可能性があります。再就職しようとしても、履歴書に罰金刑の履歴を書く義務が生じるのです。自分の経歴にキズをつけてしまうことを考えると、絶対に税金は納めておくべきという結論になります。
マイナンバー制度で家賃収入は特定される
鳴り物入りで導入されたマイナンバー制度は、行政の効率化を図るために必要なものとされています。
このマイナンバーは導入時にもさまざまな憶測が流れました。申告していない家賃収入が税務署にバレるのではないか、副業が会社にバレるのではないか、といったものです。こうした不安は、制度開始から5年を経過してどのような結果となったか、検証します。
マイナンバーは結局何ができるのか
2015年からマイナンバーは運用が開始されました。2020年現在は、開始から5年も経ちますが、それほど普及しているとはいえません。マイナンバーを会社に提出してそれっきり、という人もいます。
そもそもマイナンバーは行政手続きの効率化や簡素化を目指して導入されました。2020年現在、マイナンバーカードを持っているとできることは、コンビニで住民票や印鑑証明が入手できる、オンライン認証時に本人確認書類が少なくて済む、マイナポイントがもらえる可能性がある、といったことくらいです。
しかし、2021年からはもう少しマイナンバーカードが必要になる機会が増えます。それが確定申告です。マイナンバーカードで電子申告すると、青色申告の65万円の特別控除が減額されるのです。マイナンバーカードがないと55万円の控除にとどまります。個人事業主には、無視できない話です。
マイナンバーで家賃収入が税務署にバレるか
マイナンバーは、支払調書にも記載されるものです。つまり、税務署はマイナンバーを検索するだけで、その人へのお金の流れを以前よりも容易に把握することができます。
そのため、無申告の家賃収入は税務署にいずれバレると考えたほうがよいでしょう。
税務署がその気になれば、わずかな金額の過少申告や無申告も把握できます。ただ、税務署も多忙です。すべての人の収入を追いかけられるわけではありません。まずは収入の多い人や長期にわたって悪質な脱税行為をしている人をターゲットにすることが多いようです。
マイナンバーで副業が会社に見つかることは?
マイナンバーで副業が会社にバレるかもしれない、と不安になる人もいます。
しかし、国はこの点については否定しています。内閣府のホームページにも掲載されている事項です。
いくつか理由がありますが、一つは行政から会社へ社員が副業している旨の通知を行うことはないからです。また、会社側からの問い合わせにも応じることがないというのも理由の一つです。
政府広報からすれば、制度上、マイナンバーで副業が会社にバレることはないようです。これまで通り、副業は住民税の徴収方法によって発覚するケースが多数を占めると予想されます。
過去の家賃収入を、遡って確定申告したい場合は
「確定申告はしないとマズいようだ、でも過去にさかのぼって申告することができるのか」という疑問を持つ人もいるでしょう。
過去の家賃収入をさかのぼって申告することもできます。また、過去の家賃収入の計算に間違いがあり、納税額を修正したい場合は、更正の請求や修正申告での対応をします。詳しくみていきます。
無申告であった過去の家賃収入を確定申告する場合は
所定の手続きで、無申告の家賃収入を確定申告することができます。
しかし、先述したような加算税や延滞税を課せられるのは避けて通れません。また、過去の申告を行うと、所得税や住民税の支払いが発生します。
さらに、個人事業主の場合は事業税も課せられます。事業税の課税にはタイムラグがあり、確定申告に基づいて税務署が自治体に通知し、その後各自治体で計算されます。
確定申告の間違いを修正できるのか
確定申告の修正や払いすぎた税金を返してもらうことはできるのでしょうか。
確定申告はしたけれど、税金を多く払いすぎた場合は「更生の請求」という手続きを行います。必要書類として更生の請求書があり、この請求書を提出して納税額を修正することが可能です。
逆に、計算を間違えて納税額が少なかった場合もあります。この場合の手続きは「修正申告」です。修正申告で納税額を修正しますが、この場合は修正申告書の提出日までに足りない税額を納付しておく必要があります。
さらに、サラリーマンなど確定申告していない人は、寄付金控除や医療費控除などを確定申告以外でも5年以内であれば取り戻す方法があり、これが「還付申告」です。
確定申告の時効は何年?
確定申告の時効は、申告をしたかどうか、不正の疑いがあるかによって変わってきます。時効の期限は以下のようになります。
| 期限内に申告を行った場合 | 申告期限の翌日から3年 |
| 申告をしなかった場合 | 申告期限の翌日から5年 |
| 不正の疑いがある場合 | 申告期限の翌日から7年 |
通常の確定申告を行っていれば、3年で時効を迎えます。確定申告をしていない場合や期間外に申告をした場合の時効は5年です。脱税などの不正の疑いがある場合は7年に延長されます。
ただし、これらの期間は税務署からの督促状が届くとリセットされます。単純に期間が過ぎれば時効になるものではないので注意が必要です。
【不動産経営をあらゆる方面から支援し節税対策も万全!】
- 確定申告対策など節税のコツが学べるセミナーにご招待
- 収支報告書を事務局に送るだけで毎月・毎年の収支状況が一目でわかる
- 月額利用料&登録料が0円だから必要経費が抑えられる
ビズアナオーナーは、PCやスマホで賃貸経営を賢く行いたい不動産オーナー様におすすめです!