原状回復トラブルの原因は?オーナーが負担する範囲や対処法についても解説
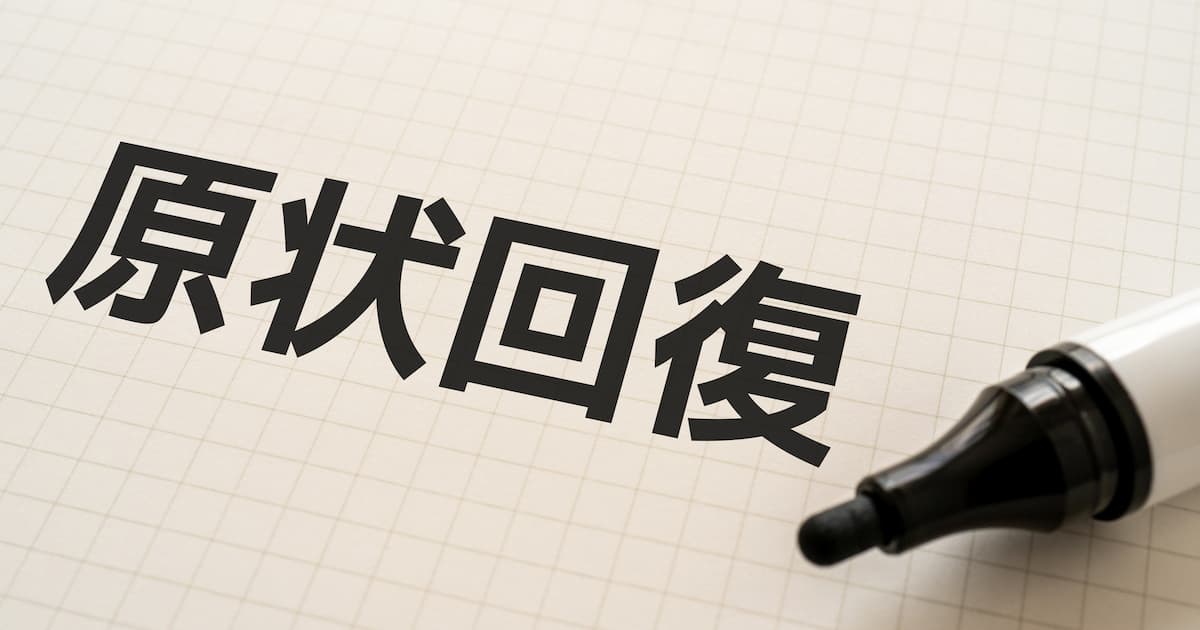
入居者の退去時に発生する原状回復トラブルは、オーナーにとって大きな課題です。
経年劣化による損耗はオーナー負担とされる一方、故意・過失による損傷は借主負担となるため、判断に迷うケースも少なくありません。
トラブルを未然に防ぐには、原状回復の基本ルールや契約時の取り決めを把握しておくことが不可欠です
スムーズな退去手続きと原状回復のトラブルを回避するため、押さえておくべきポイントを解説します。
原状回復の基礎知識とオーナーの負担範囲

原状回復とは、賃貸借契約が終了し借主が退去する際に、物件を通常使用した範囲で適切な状態に戻すことです。
部屋の状況によっては原状回復を行うために高額な費用が発生し、トラブルの原因となることがあります。
契約時に原状回復の範囲や負担割合を明確に定め、入居者にしっかりと説明しておくことは、無用なトラブルを防ぐことにもつながります。
まずは、オーナーとして押さえておくべき原状回復の基礎知識や負担の範囲、トラブル事例について解説します。
賃貸物件における原状回復とは?
原状回復では経年劣化や通常の使用による損耗はオーナーが負担し、入居者の故意や過失による損傷は入居者が修繕費を負担するルールが基本です。
ただし、元の状態に完全に戻すという意味ではなく、通常の使用による経年劣化や自然損耗についてはオーナーが負担し、借主の故意・過失や過度な使用による損傷は借主が負担するという考え方が基本です。
これは国土交通省が定めた「原状回復をめぐるガイドライン」に基づき、一般的に適用されるルールです。
なお、原状回復の範囲については地域や契約条件によって異なる場合があるため、オーナーは事前に契約書を精査し、管理会社や専門家と相談しながら対応を進めることが望ましいでしょう。
参照|国土交通省「住宅:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について」
オーナーが負担するケースと負担しないケース
国土交通省の「原状回復をめぐるガイドライン」では、基本的に通常の生活による経年劣化や自然損耗はオーナーが負担するとあります。
一方、「借主の故意や過失、注意を怠った損害による損傷」は入居者が負担するとしています。
以下に、具体的な負担例をわかりやすく表にまとめました。
| 項目 | オーナー負担(経年劣化・自然損耗) | 入居者負担(故意・過失・管理不足) |
|---|---|---|
| 壁・天井 | 壁紙の色あせ、通常の使用による汚れ | タバコのヤニ汚れ、ペットによる傷や臭い |
| 床・畳 | フローリングの軽度な摩耗、畳の変色 | 物を落としてできたへこみや深い傷 |
| 設備・家電 | 給湯器やエアコンの故障(耐用年数超過) | 乱暴な使い方による故障 |
| 水回り | 水道管や排水管の老朽化による水漏れ | 適切な換気や清掃を怠ったことによるカビの発生 |
| 改装・DIY | 許可された範囲のリフォーム | 無断での改装やDIYによる損傷 |
ただし、すべての負担が一方的に決まるわけではなく、設備や内装の耐用年数も考慮されるため、経過年数に応じた費用負担の割合を適正に判断することが大切です。
関連記事:ペットの飼育による原状回復はオーナーが負担すべき?過去の判例も解説
入居者と原状回復のトラブルになった事例
賃貸物件の退去時には、原状回復をめぐるトラブルが発生することが少なくありません。
以下に代表的な事例を紹介し、対処法についても詳しく解説します。
クリーニング費用の支払いを拒否されたケース
契約時に「退去時のクリーニング費用は借主負担」と明記していた場合でも、請求の妥当性が問題になることがあります。
部屋のクリーニング費用は、原則としてオーナー負担とするのがガイドラインの基本的な考え方だからです。
ただし、「特約」として契約書に明記され、借主が納得した上で契約した場合は、借主負担とすることが認められるケースもあります。
そのため、クリーニング費用を借主に負担してもらう場合は、契約書に明確に記載し、口頭でも説明しておくことが重要です。
経年劣化を理由に修繕費を拒否されたケース
経年劣化による壁紙の汚れやフローリングの摩耗について、借主に修繕費を請求したところ、国土交通省のガイドラインを持ち出されて拒否されたケースもあります。
オーナーは契約内容を明確にし、ガイドラインに沿った対応を行うことで、不要なトラブルを避けることが可能です。
一方、入居時からあった傷や汚れを退去時に修繕費として請求したところ、入居者から異議を申し立てられた事例もあります。
このようなトラブルを防ぐためには、入居時に物件の状態を記録し、双方で確認しておくことで防止できるでしょう。
参照|国民生活センター「賃貸住宅の「原状回復」トラブルにご注意」
原状回復ガイドラインを守らない場合のリスクと対策
オーナーが国土交通省の「原状回復をめぐるガイドライン」を遵守しない場合、オーナーにとってさまざまなリスクが発生します。
特に、入居者とのトラブル、法的な問題、物件の評判悪化といった影響が懸念されるので、詳しく見ていきましょう。
入居者とのトラブルにより訴訟されるリスクがある
国土交通省のガイドラインでは、経年劣化や通常使用による損耗はオーナー負担としています。
しかし、これに反して入居者に修繕費を請求すると、支払いを拒否されるだけでなく、弁護士や消費生活センターへ相談される可能性があります。
また、最終的には訴訟に発展する可能性があるため注意が必要です。
裁判になった場合、原状回復のガイドラインに沿わない請求はオーナー側に不利な判決が下されやすく、結果的に余計な時間と費用をかけることになります。
物件の評判が悪化して空室リスクが高まる
原状回復のガイドラインを無視し、入居者への過剰な請求が問題視されると、評判が悪化して次の入居者募集が難しくなることもあります。
近年はインターネット上での情報共有が進んでおり、不当な請求を受けた入居者が悪評を投稿することも考えられます。
口コミサイトやSNS、賃貸情報サイトのレビューにネガティブな評価を書き込まれると、物件のイメージが悪くなり、長期的な空室リスクが高まる可能性もあるでしょう。
管理会社と信頼関係が崩れて運営に支障が出る
管理会社を通して賃貸物件を運営している場合、ガイドラインに反する対応を行うことで、管理会社との信頼関係が損なわれる可能性があります。
管理会社は法令やガイドラインに基づいた対応を重視するため、不当な請求を強要するとオーナーの要望に応じなくなるかもしれません。
また、管理会社がオーナーとの契約を解除するリスクも考えられます。
原状回復のルールを正しく理解し適切に運用することは、トラブルを防ぎ安定した賃貸経営を続けるために大切です。
原状回復のトラブルを防ぐためにすべきこと
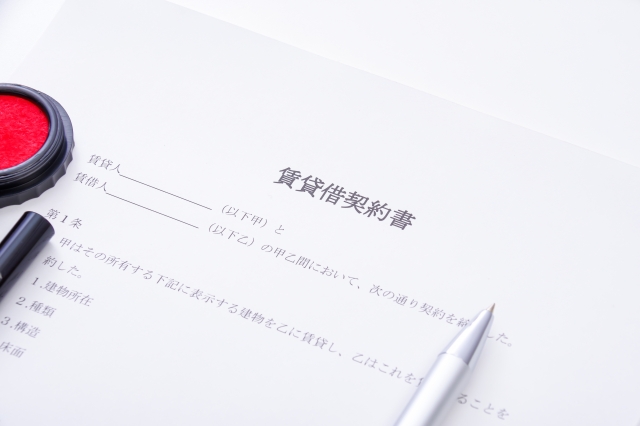
原状回復に関するトラブルを防ぐには、オーナー側が契約時に対策を講じ、入居者と適切なコミュニケーションを取ることが不可欠です。
具体的には、契約書に修繕費用の負担範囲を明記する、入居時に物件の状態を記録する、退去時にオーナーが部屋をチェックするなど、段階ごとの対策を徹底してください。
オーナーが行うべき具体的な対策について詳しく見ていきましょう。
入居前・入居後にすべき対策
原状回復に関するトラブルを未然に防ぐためには、入居前の契約段階から適切な対策を行うことが重要です。
契約時に修繕費用の負担範囲を明確にし、入居者にも納得してもらうことが欠かせません。
また、入居時に物件の状態を入居者自身にも確認してもらうことも不可欠です。
契約書に費用負担を明記する
原状回復のトラブルを防ぐには、契約書に修繕費用の負担範囲を明記しておくことが最も重要です。
多くのトラブルは、「どこまでがオーナー負担で、どこから入居者負担なのか」が明確になっていないことが原因で発生しています。
契約書には、経年劣化や通常使用による損耗はオーナー負担であること、故意や過失による損傷については入居者が修繕費用を負担する、という旨を記載しておきましょう。
その際、「タバコによる壁紙の黄ばみは借主負担とする」「ペットによる床や壁の損傷は借主負担とする」など具体的な条項を明記することが大切です。
原状回復の特約を設ける場合は、ガイドラインの範囲を超える内容にならないよう慎重に検討してください。
入居者自身に不備がないか確認してもらう
原状回復トラブルを防ぐために、入居者自身に室内の状態を確認してもらう方法が確実です。
入居時からすでにある傷や汚れ、設備の不具合を把握して記録に残しておくことで、退去時に入居前からあったのか、入居者によるものか判断できます。
具体的には、入居時のチェックリストをオーナーや管理会社が準備し、入居者と一緒に物件の状態を確認することが効果的です。
壁紙や床、設備の状態を細かくチェックし、気になる点があれば撮影して記録に残しましょう。
また、エアコンや給湯器などの設備についても、問題がないかを確認してもらい、不具合があればすぐに報告するよう伝えておきます。
オーナーはこうした確認作業を通じて、入居者に物件を適切に管理する意識を持ってもらうことが大切です。
退去時にすべき対策
入居者が退去する際、オーナー自身で物件のチェックを行い、傷や汚れが入居時からのものかどうかを正確に判断することが求められます。
さらに、修繕の責任を明確にするために、設備の耐用年数を確認し、適正な修繕費用の請求を行うことが大切です。
退去時のトラブルを防ぐために、オーナーが取るべき対策について解説します。
オーナー自身で部屋のチェックをする
退去時のトラブルを防ぐためには、オーナー自身が部屋の状態をしっかりと確認しましょう。
管理会社に任せきりにするのではなく、実際に自分の目でチェックすることで、修繕の必要性や費用負担の判断を正しく行えます。
チェックの際は、壁紙や床、窓などの状態を細かく確認し、傷や汚れが入居時のものか、退去後に発生したものかを判断する必要があります。
可能であれば、入居時に記録した写真と比較し、明らかに入居者の使用によって発生した傷や汚れであれば、修繕費用を請求する根拠として提示しましょう。
設備の耐用年数を確認する
原状回復の負担を適正に判断するために、設備の耐用年数を正しく把握することも大切です。
国土交通省の「原状回復をめぐるガイドライン」では、設備や内装には耐用年数があり、これを超えた設備の修繕費を借主に全額負担させることはできないとされています。
例えば、壁紙の耐用年数は6年とされており、6年以上経過した壁紙の張り替え費用を全額借主に請求することは認められません。
家電や家具の場合、エアコンの法定耐用年数は6年、カーテンは3年としています。
耐用年数を超えている場合は、故障が自然劣化によるものと判断される可能性が高くなるでしょう。
設備の耐用年数については国税庁が公表していますので、オーナーは一度確認しておくことをおすすめします。
参照|国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」
明確な理由がない状態で費用を請求しない
原状回復における費用請求は、明確な根拠に基づいて行ってください。
オーナーの判断だけで修繕費用を請求すると、入居者とのトラブルにつながりやすく、最悪の場合訴訟や消費者センターへの相談に発展する可能性もあります。
費用を請求する場合は、入居者に対して具体的な説明を行い、修繕の必要性と負担割合を明確にしましょう。
入居時と退去時の写真を比較し、修繕が必要な箇所を客観的に示すことで、説得しやすくなります。
また、管理会社や専門家と相談し、請求の正当性を確認してから入居者に通知することで、不要なトラブルを未然に防げます。
原状回復でトラブルが発生した場合の対処法

原状回復でトラブルが発生した場合、まずは修繕の責任がどちらにあるのかを明確にし、事実関係を整理してください。
そのうえで、管理会社や弁護士、第三者機関などを活用しながら、法的な観点を踏まえた解決策を検討します。
原状回復のトラブルが発生した場合に、オーナーが取るべき具体的な対処法を解説します。
まずは責任がどちらにあるのか確認する
原状回復をめぐるトラブルが発生した場合、最初に修繕の責任がオーナー側なのか、入居者側なのかを明確にします。
責任の所在が不明確なまま請求を進めると、入居者との交渉が難航し、トラブルがさらに大きくなる可能性があるからです。
責任の判断を行う際は、入居時の写真や記録を確認し、損傷が入居前からあったものなのか、入居後に発生したものなのかを検証しましょう。
また、修繕が必要な設備の耐用年数を考慮し、耐用年数を超えている場合には自然劣化とみなされ、入居者に費用を請求することが難しくなります。
オーナーは修繕責任がどちらにあるのかを冷静に判断し、適切に対応することが求められます。
管理会社に相談する
オーナー自身での解決が難しいときは、管理会社に相談するのも一つの方法です。
管理会社は原状回復に関する専門的な知識があるため、トラブルの内容を整理し、解決に向けたアドバイスを提供してくれるでしょう。
入居者が修繕費の支払いを拒否している場合や、費用負担の範囲について意見が食い違っている場合、第三者である管理会社を介することで解決につながることがあります。
また、入居者との直接対立を避け、トラブルの拡大を防ぐ効果も期待できます。
ただし、管理会社には裁判を起こしたり、債権回収を行ったりする権限はありません。
管理会社はあくまで物件の管理がメインですので、法的措置を取れないということは覚えておきましょう。
弁護士に相談して法的な対応をする
原状回復のトラブルが深刻化した場合は、弁護士に相談し法的な対応を検討しましょう。
弁護士に相談することで、費用の請求が法的に正当であるかを確認できるだけでなく、入居者との交渉を進めるための助言を受けられます。
また、内容証明郵便を送付して支払いを促す、法的措置を検討するといった対応により、入居者の支払い意識を高める効果も期待できます。
ただし、裁判に発展すると訴訟費用や弁護士費用の負担が発生し、解決までの期間も長くなることがあります。
そのため、まずは弁護士の助言を受けながら、入居者と交渉による解決を優先するのが望ましいでしょう。
少額訴訟は60万円以下の請求に適用され、比較的迅速に解決が見込めるため、原状回復費用の回収を目的とする場合に有効な手段です。
第三者機関を利用した調停や仲裁を活用する
原状回復をめぐるトラブルで入居者との話し合いが難航した場合には、第三者機関を利用して調停や仲裁を行うことも有効です。
公正な立場にある第三者を介することで、スムーズに解決を図れる場合があります。
例えば、国民生活センターや消費生活センターでは、賃貸契約に関する相談を受け付けており、入居者が原状回復について相談するケースも少なくありません。
オーナー側としてもこうした機関を活用することで、公平な解決を目指せます。
また、住宅紛争審査会(住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく機関)や宅地建物取引業協会なども、賃貸契約や原状回復に関する紛争の調停を行っています。
専門家のアドバイスを受けながら解決の糸口を探ることで、訴訟に比べて費用や時間の負担を抑えながら、公正な解決を目指せます。
賃貸経営に役立つ情報を知るなら「ビズアナオーナー」
当社が提供している無料の収支管理サービス「ビズアナオーナー」は、賃貸経営を行っているオーナーが利用する無料の収支管理サービスです。
月々の収支データを無料で簡単に自動でデータ化し、わかりやすいビジュアルで経営状況を把握することができます。
また、ビズアナオーナーの会員限定で、補助金や節税、空室対策に関する最新の情報やダウンロード資料なども随時配布しています。
その他にも、賃貸経営に役立つサービスも特別価格や無料で利用いただくことが可能です。
是非、「ビズアナオーナー」を無料登録してみてください。
【賃貸経営にも役立つコンテンツをラインナップ!】
- 収支報告書を事務局に送るだけで毎月の収支管理ができる!しかも無料!
- AI賃料査定レポートで設備による賃料の増減を簡単に把握できる
- 統計調査レポートで周辺の商業施設・教育施設やハザードマップなどの情報が得られる
ビズアナオーナーは、賃貸経営の最新情報を知りたい不動産オーナー様におすすめです!





