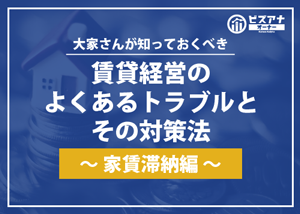家賃滞納の時効について解説。何年放置すると家賃請求できなくなる?

賃貸住宅オーナーは入居者から家賃を滞納されても簡単には退去させることができません。また滞納された家賃が回収できなくなる時効があるため、賃貸経営を続けるために滞納家賃の時効については正しく理解しておくことが大切です。
今回は、家賃滞納と時効の関係についてみていきます。
家賃滞納にも時効はある?

滞納された家賃には、この日までに回収の動きをしなれば時効になる、という期日があります。
滞納家賃の時効は5年か10年か
借主が家賃を滞納していても一定期間、賃貸オーナーが対処しなければ、借主が時効を主張できるようになります。
2020年4月1日に改正された民法にて、時効までの期間は、以下のいずれか早い方が到達した時点で完成すると定められています。
-
- 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しない時(改正民法166条1項)
- 権利を行使することができる時から十年行使しない時(改正民法166条2項)
しかし、賃貸取引における債権は、契約時点で、権利行使日が明確になっています。そのため、家賃の滞納における時効は5年であると考えておくとよいでしょう。
時効の起算点
家賃の滞納期間には、「いつの時点から数えて5年とする」という起算点があります。
借主が滞納している家賃の起算点は、各月の家賃の支払日です。家賃の支払日に所定の金額が支払われず、かつ賃貸オーナーが何もしなかった場合、その日から5年経過した時点で時効が完成します。
また、複数月で滞納をしている場合は、1番古い滞納家賃から順番に時効が訪れます。
例えば、滞納した家賃が2021年1月と2月の家賃だった場合は、5年後の2026年1月と2月にそれぞれが時効になります。
家賃滞納での強制退去は難しい
借主を強制退去させるには、それなりの証拠を揃え、裁判所に認めてもらわなければなりません。したがって、滞納家賃があることを理由に退去して欲しいと思っても、それまでにはかなりの時間を要します。
賃貸契約は多様であるため、こうなれば強制退去が必ず認められる、というような明確な基準はありません。過去の事例などを参考にして、適宜、見極めていく必要があるのです。
◯参考事例
100万円を超える家賃を、9ヶ月に渡り滞納した借主に対し、立ち退き請求をした事例があります。借主は、信頼関係が続いていることや家賃を少しづつ返済していること、そして返済の見通しがあることを主張し、退去を拒みました。しかし判決では、滞納が恒常化していたことやそれ以前にも家賃支払いの遅延があったことを理由に、信頼関係の喪失を認め、立ち退きを命じています。
一つの事例をみても、ケースバイケースであることがわかります。問題が長期化、複雑化する前に対処するようにした方がよいでしょう。
家賃滞納を請求するための対処法

家賃の文字と家の模型家賃滞納が発生した場合、オーナーが取れる法的な対応にはいくつかの選択肢があります。ここでは具体的な対処方法とその手順について詳しく解説していきます。
滞納者に対して支払督促を行う
支払督促は、裁判所を通じて債務者に支払いを求める手続きです。申立手数料は請求額によって異なり、10万円以下の場合は1,000円、以降10万円ごとに1,000円がプラスされていきます。
参考:裁判所「手数料」
支払督促の手順としては、まず督促状を作成し、相手方の住所地の簡易裁判所に提出します。続いて裁判所への申立てと手数料の納付、裁判所からの督促状送達、そして債務者からの異議申立期間(2週間)の経過を待つことになります。
相手方が異議を申し立てた場合は民事訴訟に移行します。請求額が140万円以下なら簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所で訴訟が行われます。
異議申し立てがなく、2週間が経過した場合は、仮執行宣言申立書を裁判所に提出します。仮執行宣言申立書が裁判所を通じて相手に送達されたあとも、支払がない場合は、差し押さえ等の強制執行の申し立てを行います。
少額訴訟を起こす場合の実務
60万円以下の滞納金額の場合、少額訴訟という手続きを利用できます。
少額訴訟の特徴は、通常の訴訟と比べて手続きが簡素で、一般的に1回の期日で審理が終了し、証拠の提出が比較的容易である点です。また、判決までの期間も短く、通常1〜2カ月程度で結論が出ます。
家賃滞納の時効を更新(中断)する方法

家賃滞納の時効は存在しますが、それは賃貸オーナーが対処をしなかった場合です。きちんと対処することで、時効は中断することができます。
時効の中断とは
時効の中断とは、それまでの時効期間が完全にリセットされ、また新たな時効がスタートすることを指します。これにより、時効は10年延長されます。
しかし、普通郵便や口頭による催促では、時効を中断することはできません。中断するためには、債務者による債務の承認や裁判上の請求などが行なわれなくてはなりません。
なお、2020年の民法改正で「中断」は「更新」という名称に置き換えられました。
賃貸オーナーが時効の中断ですべきこと
具体的にはどのようなことを指すのか、みていきます。
借主に家賃の未払いを承認してもらう
時間やお金がかかるため、貸主も借主も、なるべく裁判にはしたくないはずです。そのため、もし借主に支払う意思がある場合は、債務を承認してもらう方法が一番簡単です。
債務の承認とは、滞納していることを借主が認めることです。これにより、時効を中断することができます。
具体的には、借主が一部の家賃を支払うことで、債務の承認が行なわれたことになります。
借主に強制執行を行う
債務の承認が行なわれない場合は、裁判所に請求をすることで、進行している時効を中断することができます。
具体的には、支払督促により債務名義(強制的に退去させるために必要な公文書)を取得したり、訴訟を起こしたりすることで、時効は中断されます。
時効は停止することもできる
時効を一時的に止める方法もあります。
内容証明などにより家賃支払いの催告を行なうことにより、最大6ヶ月の執行猶予を得られます。内容証明とは、郵便局と差出人に、相手に送ったものと同じ控えが残り、書面を送ったことが正式な証拠として残る郵便のことです。
なお、以前は時効を一時的に止める方法を「停止」と呼んでいましたが、2020年4月の民法改正により「完成猶予」という言葉に置き換えられました。
賃貸オーナーが家賃滞納を請求するときの注意点

家賃滞納の請求を行う際には、法令遵守と適切な手続きの実施が不可欠です。請求時に特に注意すべき点について詳しく説明します。
早朝・深夜や高頻度での連絡
滞納者への請求は正当な権利ですが、その手段によっては法令違反となる可能性があるため、慎重な対応が求められます。
特に問題となりやすいのは、深夜帯や早朝における督促行為です。過去の判例では、午前0時を過ぎての督促活動により、入居者側の慰謝料請求が認められたケースが存在します。
この点について、例えば貸金業法では明確な基準を設けています。具体的には、夜間21時から翌朝8時までの時間帯における、正当な理由のない電話、FAX、訪問による督促行為は、社会通念上不適切とされ、禁止対象となっています。
電話や訪問による催促は避け、文書での連絡を心がけましょう。また、連絡頻度にも配慮が必要で、過度な催促は違法となる可能性があります。
勤務先への対応と法的リスク
滞納者の勤務先への連絡なども深刻な法的リスクを伴います。信用毀損による損害賠償では、数百万円程度の賠償命令が下される可能性があります。さらに、業務妨害による刑事責任や個人情報保護法違反にも注意が必要です。
マンションの共用部分での告知に関する規制
物件共用部での告知行為も、プライバシー侵害にあたるため注意が必要で、こちらも損害賠償が認められるケースがあります。さらに、名誉毀損による刑事告訴のリスクも考慮する必要があります。
保証人や保証会社に滞納された家賃を請求する

保証人や保証会社に申し立てることで、滞納家賃が返ってくる可能性があります。
保証人がいる場合の時効の扱い
民法446条1項には「保証人は、主たる債務者がその債務を履行しない時に、その履行をする責任がある。」とあります。これは、もし借主が滞納家賃を支払わないまたは支払えない場合、保証人が代わりに支払いましょうというルールです。
両親や親族が保証人になっている場合、保証人に債務の承認や裁判上の請求することで、滞納している家賃の時効を中断させられます。
ただし、保証人が債務を承認した場合は、保証人の時効のみ中断されます。なぜなら、主債務(借主の債務)が保証債務(保証人の債務)に従属していないからです。
保証会社と契約している場合
賃貸経営者にとって、家賃滞納は大きなリスクです。保証会社がついている場合、滞納家賃を保証会社が支払ってくれるのでリスク回避に役立ちます。
家賃を支払った場合は、家賃回収のプロである保証会社が、借主に滞納家賃の督促を行ないます。
家賃滞納に対する適切な対応のために

家賃滞納問題への対応には、法的知識と適切な予算計画が必要不可欠です。初期対応費用として内容証明郵便等で2万円程度、支払督促手続きで3万円〜5万円、少額訴訟手続きで5万円〜10万円、強制執行手続きでは30万円〜50万円程度の費用が見込まれます。
これらの費用は最終的に借主から回収できる可能性がありますが、一時的な立替えが必要となります。そのため、資金計画を立てた上で、段階的な対応を検討することが推奨されます。
予防的措置として、入居審査の厳格化や保証会社の活用、家賃保証保険への加入、定期的な入居者とのコミュニケーションなどが重要です。これらの対策により、家賃滞納のリスクを最小限に抑えることができます。
状況が複雑化した場合は、早期に法律の専門家に相談することをお勧めします。弁護士相談料は初回30分で5,000円〜1万円程度から、着手金は20万円〜30万円程度が一般的です。
本コラムで紹介したポイントを参考に、各オーナーの状況に応じた適切な対応を検討しましょう。また、法改正や判例の変更により、対応方法や費用が変更される可能性もあるため、定期的な情報更新も重要です。
収支管理や経営状況を簡単把握できる「ビズアナオーナー」
「ビズアナオーナー」は、賃貸物件オーナー様に向けて無料で提供している収支管理サービスです。
毎月管理会社から送られてくる収支報告書をアップロードすると、各部屋の賃料や支出状況などをわかりやすく視覚的に表示することが可能で、収支状況などを簡単に把握することができます。
また、賃貸経営をサポートする様々なサービスを、ビズアナオーナー会員様限定の特別プランでご用意しています。
賃貸経営に関するお悩みや課題解決は、「ビズアナオーナー」にお任せください。
【賃貸経営に役立つコンテンツをラインナップ!】
- 賃貸経営のお悩みを専門家に相談できるセミナーや勉強会にご招待
- いつでも無料で過去のセミナー動画を視聴できるのはビズアナ会員だけ!
- AI賃貸査定レポートや、3点ユニットバスの改修など、ビズアナ会員価格で賢くお得に手に入る!
ビズアナオーナーは、賃貸経営のお困りごとやお悩みの解決策を知りたい不動産オーナー様におすすめです!