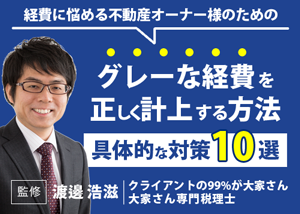130万円の壁に不動産所得は含まれるのか。不動産収入と扶養の関係
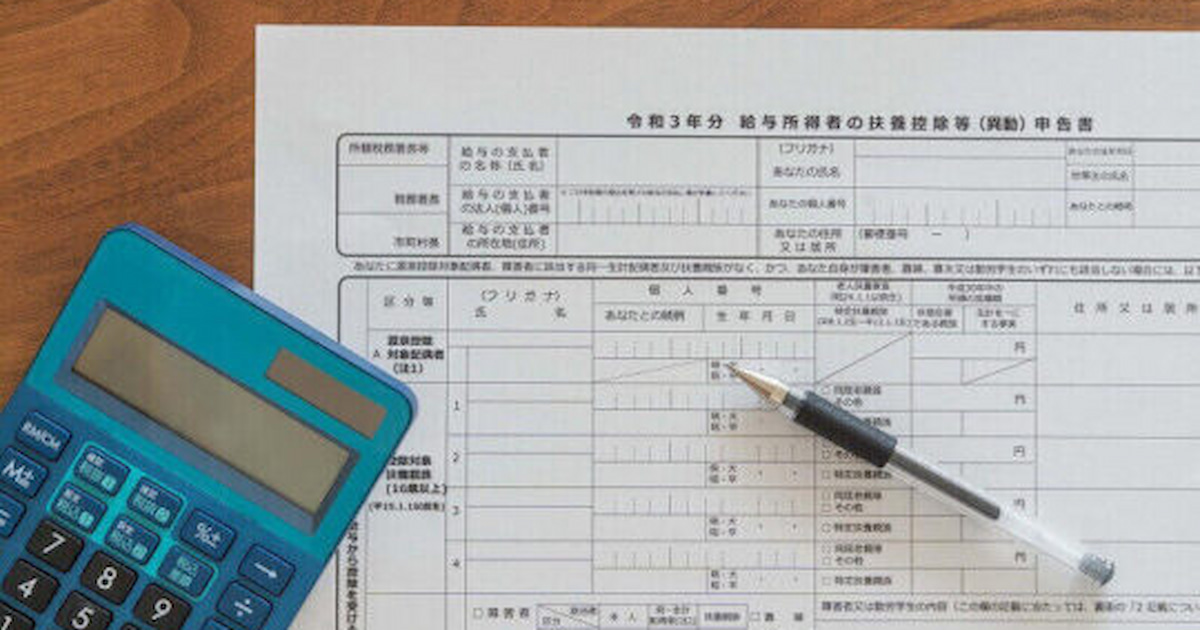
扶養内で働きたい方、すでに働いている方は「130万円の壁」という言葉を見聞きしたことがあるでしょう。収入によって扶養や社会保険などに影響が現れることを指しています。
では、アパートやマンションを経営していて家賃収入がある場合、その不動産所得は130万円の壁に含まれるのでしょうか。ここでは、不動産収入と扶養の関係について、詳しく解説します。
130万円の壁について
「130万円の壁」のほかにも「103万円の壁」「150万円の壁」という表現もあります。いったい、どれが何の壁を指すのか混乱してしまう方が多いようです。
ここでは、それらの言葉の元である「税法上の扶養」「社会保険上の扶養」の意味を解説します。
扶養とは
まず扶養とは、世帯の収入源である家族から、経済的な支援を受けることを指します。扶養に入ると、被扶養者は所得税や社会保険料の支払いが不要になる点が大きなメリットです。
ただし、だれでも扶養に入れる訳ではなく、一定の条件を満たす必要があります。
扶養は「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」に分類され、それぞれ扶養に入れる条件が異なります。
扶養の種類と基準
「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」、それぞれの違いをみていきましょう。
税法上の扶養
税法上の扶養は、所得税や住民税に関係します。
扶養者は自身の所得から、定められた金額を控除できるため、所得税が安くなります。そして被扶養者は、所得税や住民税の支払いが不要です。
被扶養者が子どもや親なら「扶養控除」、配偶者なら「配偶者控除」「配偶者特別控除」に該当します。これらを重複して計上することはできません。なお、扶養に入るのは納税者と生計をともにしていることが絶対条件です。
以下が、扶養控除の対象者です。
-
- 6親等以内の血族および3親等内の姻族
- 都道府県知事から養育を委託された児童
- 市町村長から養護を委託された高齢者
年齢は16歳以上で、年間の合計所得金額が48万円以下(給与所得のみは103万円以下)である必要があります。
扶養が配偶者の場合の「配偶者控除」と「配偶者特別控除」は、婚姻届を提出している民法上の配偶者が対象で、年齢による制限はありません。
配偶者控除の条件となる合計所得金額は、扶養控除と同じです。年収がオーバーして配偶者控除から外れた場合、配偶者特別控除が適用されることがあります。
配偶者特別控除の対象となる合計所得金額は、48万円超え133万円以下(給与所得:103万円超~201万円以下)です。
参考:
国税庁「扶養控除」
国税庁「配偶者控除」
国税庁「配偶者特別控除」
社会保険上の扶養
社会保険上の扶養は、年金保険や健康保険に関係する制度です。収入を得ている家族が加入する社会保険(社会保険や厚生年金)の被扶養者になり、社会保険料の納付は不要です。
対象範囲は、被保険者の配偶者や3親等以内の親族です。内縁関係にある配偶者や、その両親・子も含まれます。
しかし、75歳以上の方は後期高齢者医療保険制度の加入義務があるため、社会保険上の扶養にはなれません。
収入の基準は、年間130万円未満です。なおかつ、被保険者の収入の1/2未満が条件です。対象者が60歳以上、もしくは障害年金を受給する程度の障がいがある場合は、180万円が適用されます。
参照:
全国健康保険協会「被扶養者とは?」
130万円の壁とは
ここでは、「103万円・150万円・130万円の壁」の意味を解説します。
103万円・150万円の壁は税法上の扶養、130万円の壁は社会保険上の扶養に関係しています。
103万円の壁
給与所得が103万円以上になると、扶養控除・配偶者控除の対象から外れ、所得税の負担が発生します。
課税所得金額を計算する際、48万円の基礎控除と、給与所得には給与所得控除が適用されます。
妻が夫の扶養に入っており、パート収入が103万円だった場合の課税所得金額は0円です。
103万円-55万円(給与所得控除)-48万円(基礎控除)=0円
「103万円の壁」とは、自身の所得税負担がなく、なおかつ夫は配偶者控除を受けられる上限金額を表しています。
150万円の壁
納税者本人の合計所得額が900万円以下で、被扶養者の給与所得が150万円(合計所得金額:95万円)の場合、納税者は38万円の控除を得られます。
この38万円という金額は、配偶者特別控除で受けられる最大控除額であると同時に、配偶者控除と同じ控除額です。
給与所得が150万円を超えると、適用される控除額が段階的に少なくなります。ちなみに「201万円の壁」とは、配偶者特別控除が受けられなくなる給与所得額です。
130万円の壁
130万円の壁とは、社会保険上の扶養から外れるラインです。年収が130万円を超えると、社会保険の被扶養者の対象から外れてしまいます。
給与所得を得ている方は、パートやアルバイト先の社会保険に加入しなければなりません。また事業所得などを得ている場合は、国民健康保険料・国民年金保険料の支払い義務が発生します。
参考:
国税庁「給与所得控除」
国税庁「基礎控除」
不動産所得について
不動産所得は、所得税の計算に必要な所得のひとつです。不動産所得に該当する収入や、所得から差し引ける必要経費の種類について解説します。
不動産所得とは
不動産所得とは、以下のいずれかに該当する貸付け事業で得られた所得を指します。
-
- 土地や建物などの不動産の貸付け
- 地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付け
- 船舶や航空機の貸付け
引用:
国税庁「不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」
たとえばマンション・アパートを購入して第三者へ貸し出したり、土地に借地権を設定して借地権付き物件として貸し付けたりする事業が、不動産所得の対象です。
しかし、同じようなマンション・アパート経営だとしても、不動産所得ではなく譲渡所得・事業所得になる場合があります。
建物の所有を目的とした土地を貸し付ける際、借地権を設定する対価として、買主から売主に権利金が支払われます。権利金は原則として不動産所得ですが、その金額が土地の時価の1/2を超える場合などは、譲渡所得とみなされます。
また食事の提供を伴う下宿業を取り扱う場合は、不動産所得ではなく事業所得もしくは雑所得の対象です。
参考:
国税庁「権利金」
不動産所得は、その年の不動産所得にかかる総収入金額から、必要経費を差し引いて算出します。
不動産所得の金額=総収入金額-必要経費
家賃収入も不動産所得の対象
不動産所得には、不動産投資による家賃収入はもちろん、礼金・更新料・共益費なども含まれます。返還する必要がない敷金・保証金も対象です。
収入金額を計上する時期は、賃貸契約書などで決められている支払日です。とくに支払日が定められていない場合は、実際に支払われた日が計上時期です。
経費について
不動産所得の経費として認められているのは、以下のような費用です。
各種税金
固定資産税・登録免許税・不動産取得税・地価税・特別土地保有税・事業所税などが含まれます。
損害保険料
建物に対して火災保険料の契約をしている場合は対象です。
修繕費
建物や建物に付属している設備を、原状回復などを目的に修繕した際の費用は経費に含まれます。3年程度をめどに実施される修理や改良、1カ所にかかる費用が20万円未満の修理などが対象です。
ただし、修繕したことにより資産の使用可能期間が延びたり、資産価値を向上させるほど手を加えたりしてしまうと、修繕費の対象になりません。
たとえば建物に非常用の階段を作るなど、物理的に設備を付け加えた場合は、修繕費ではなく資本的支出です。固定資産として計上し、減価償却により経費計上する必要があります。
資本的支出か修繕費か判断がつかない金額の場合、経費として算入できる目安は、費用が60万円未満もしくは、前年末の不動産取得価額のうち約10%相当額以下です。
減価償却費
不動産の購入金額のうち、建物部分は減価償却の対象です。耐用年数や築年数に応じて、数年に分けて計上します。
なお、土地の購入金額は減価償却の対象外です。
参照:
国税庁「租税」
国税庁「修繕費にならない費用」
不動産所得で扶養は外れる?
「不動産所得を得ている=扶養に入れない」訳ではありません。
たとえば不動産投資による家賃収入を得ながらでも、被扶養者として生活することは可能です。しかし一定の金額を超えてしまうと、扶養から外れてしまうので気をつけましょう。
ここでは、不動産所得と扶養の関係について解説します。
家賃収入と税法上の扶養
税法上の扶養を受けられる合計所得金額は、扶養控除・配偶者控除は48万円、配偶者特別控除は133万円が上限です。
「103万円の壁」「201万円の壁」というのは、あくまでも給与所得のみの場合なので、混同しないように気をつけましょう。
また、収入ではなく所得を計上するのがポイントです。家賃収入の合計金額をそのまま計上するのではなく、必要経費を差し引いて所得を算出します。
仮に年間の家賃収入が50万円だった場合でも、2万円以上の経費を計上できれば扶養控除・配偶者控除の対象です。
50万円(家賃収入)-2万円(必要経費)=48万円
年間の家賃収入が140万円で、必要経費が7万円以上ある場合、配偶者控除を適用はできませんが、配偶者特別控除に該当します。
140万円(家賃収入)-7万円(必要経費)=133万円
不動産所得は、扶養の対象者が配偶者以外なら48万円、配偶者の場合は133万円を超過した際に税法上の扶養から外れてしまいます。
家賃収入と社会保険上の扶養
社会保険上の扶養は「130万円の壁」に気をつけなければなりません。税法上の扶養は「所得」を元にしていますが、社会保険上の扶養は「収入」を基準にしているのが注意点です。
保険者が必要経費として認めた費用は、収入から差し引けます。年間の家賃収入の合計からその経費を差し引き、金額が130万円に抑えられるなら扶養内です。
しかし不動産所得の計算時は必要経費に算入できた費用が、社会保険上の扶養では含められない可能性があります。
そのため税法上の扶養に比べて社会保険上の扶養は、基準の収入額を上回りやすいでしょう。
仮に家賃収入が140万円だった場合、10万円の経費計上がなければ扶養から外れてしまいます。
140万円(家賃収入)-10万円(必要経費)=130万円
扶養の金額を超えてしまった場合の手続き
万が一扶養の上限金額を超えてしまった場合、税法上の扶養は所得税や住民税、社会保険上の扶養は社会保険料の支払い義務が発生します。
税法上の扶養の適用外となってしまったら、確定申告を行って税金を納めましょう。
社会保険上の扶養の場合、納税者の勤務先に「健康保険被扶養者(削除)異動届」を提出しなければなりません。その後、自身の勤務先の社会保険もしくは国民健康保険へ加入します。
【不動産経営をあらゆる方面から支援し節税対策も万全!】
- 収支報告書を事務局に送るだけで毎月・毎年の収支状況が一目でわかる
- 月額利用料&登録料が0円だから必要経費が抑えられる
- 確定申告対策など節税のコツが学べるセミナーにご招待
ビズアナオーナーは、PCやスマホで賃貸経営を賢く行いたい不動産オーナー様におすすめです!