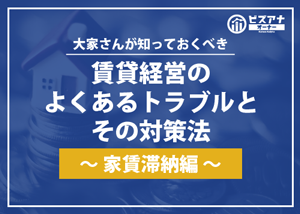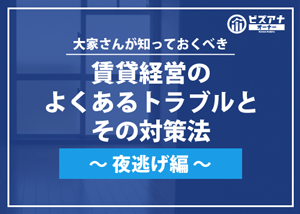賃貸物件を自主管理するデメリットとは?リスクについても解説

賃貸物件を自主管理することを検討したとき、どういったことに気をつける必要があるのでしょうか。
今回は、自主管理の具体的な業務やデメリット、リスクについて、管理会社に依頼する委託管理と比較しながら紹介します。
賃貸物件の自主管理にはどのような業務があるのか
不動産管理には大きく分けて「建物管理」「入居者・管理業務」「出納管理」の3種類の管理があります。
それぞれについて詳しく紹介します。
建物面の管理
建物管理とは、機械や設備に関する管理のことです。設備によっては、点検周期が法律で定められているものがあります。これを法定点検といい、必ず守る必要があります。また、法定点検ではなくても、人命にかかわる重要な機器がたくさんあります。故障や不調が人命に関わるものもあります。それぞれを管轄する監督官庁や行政へ要件に応じた確認や報告が必要です。
建物管理には、具体的にどういったものがあるのでしょうか。
消防設備
消火器・火災報知器・避難器具・消防ポンプ・排煙設備・誘導・屋内外消火設備などがあります。
例えば、消防設備の資格者による1年に1度の点検が必要で、3年に1度の消防署への報告が定められています。マンションの規模や建っている地域、構造、総戸数、収容人数、敷地面積、店舗の業種などにより区分され、必要な対応も異なります。
また、設備によって推奨される交換目安時期があり、交換は必須ではないもののメーカーの耐用試験から出された目安には従うべきでしょう。
例えば消火器は、耐用年数が8年~10年で、交換が推奨されています。
上下水道設備
水道法で、受水槽・高架水槽で10㎥以上のものは1年に1回の簡易専用水道検査が必要と規定されています。水槽内の色・汚れ・カビなどの状況や水質(色・カルキ臭)など、水道事業者は管理者に対して、行政の規定に従っていくつもの水質判断項目を測定し、報告するよう指導しています。
また、田舎など下水道設備が不十分な地域は、今でも浄化槽による、ろ過設備が残っている場合があります。定期的な汚泥の除去や資格者による保守点検など、個別に法定要件があるため水道局へ確認が必要です。
エレベーター設備
エレベーターは、建築基準法に基づいて1年に1度の定期点検が義務付けられています。
エレベーターは人が乗り降りするカゴが上下し、扉が半自動的に開閉します。こちらも消防設備と同様に、誤作動は人命にかかわります。常に住民を乗せて一日中動くため、消防設備よりもさらに慎重に扱わなくてはなりません。
点検結果の報告後に、エレベーター内の操作盤付近のよく見える場所に、定期検査報告済証を貼ります。自動車の自賠責保険のように、点検結果の有効期日が大きく表示され、誰でも判別できます。
その他設備
特定行政庁が指定する主に規模が大きい建物は、特殊建築物に分類されます。換気設備・排煙設備・非常用照明・給排水設備などを上記点検とは別に、特定行政庁へ定められた期間ごとに報告する義務があります。
また、総戸数が約80戸を超えるほどの中規模のマンションで契約電力が50kw以上だと、キュービクルと呼ばれる変圧設備を電気主任技術者が月次と年次に点検し報告する義務があります。
参照:公益財団法人マンション管理センター「マンションの法定点検」
入居者・管理業務
入居者・管理業務とは、人に関係する管理のことです。入居者の募集と契約書類事務、室内リフォーム、騒音・ゴミ・防犯、滞納督促、地域との関係構築などです。
以下では、それぞれ具体的に紹介します。
入居者の募集
空室へ入居者を斡旋する業務です。
顧客を空室へ案内するのは大体は仲介業者が行います。そのため、仲介業者に対して物件の概要や募集条件の情報を提供します。
募集条件は、例えば、敷金・家賃・室内設備・入居可能時期・必要書類・火災保険・滞納保証料金などです。
仲介業者が案内する際は、空室のカギの手配など、案内がスムーズにできるように準備します。
室内リフォーム
部屋の退去の立ち合いをしたあとに、次の入居が決まりやすいようにリフォームをします。
壁・床・天井の仕様は時代によってトレンドがあるため、それらを考慮した雰囲気をとりいれたり、旧式で劣化した不人気の設備は、時代に合った人気の設備に新しくします。
騒音・ゴミ・防犯問題に対する注意喚起
入居者同士の騒音問題があった場合、どの部屋からの騒音か確実には分からないため、文書の投函や電話や訪問などで、全戸に対して注意喚起をします。
また、ゴミは地域によって出し方が決まっています。マンション内に施錠できるゴミステーションがなく露店のゴミ置き場の場合、誤った曜日や、夜のうちにゴミを出すと悪臭や動物の食い荒らしに遭い不衛生になります。こちらも全戸に対して注意喚起をします。
防犯面では、地域からの不審者の目撃情報や入居者の通報があれば、全戸に対して注意喚起をします。さらに、防犯カメラの映像を適宜確認し、管轄の警察署へ巡回協力を要請します。
滞納督促
家賃支払期日が過ぎても支払いがされない場合、すぐに契約者に連絡し、早期の支払いを促します。電話に出ない場合は、メールや通知文を投函するなど次第に督促を強めていきます。
ひと昔まえのように、連帯保証人や勤務先に電話して協力を仰ぐのは難しくなりました。
契約者が賃貸保証会社に加入している場合には、本人ではなく賃貸保証会社に連絡します。
関連記事:家賃滞納にあった大家さんが知っておくべき上手な督促・取り立て方法
地域との関係構築
地域と仲良くするのも大切な仕事です。
多くの入居者を抱えていると、地域へご迷惑を掛けたりお世話になることもあるためです。
自治会費の支払いや清掃当番、地域行事の参加などをすることにより、関係構築をします。
出納管理
賃貸経営事業の最大の目的は利益を出すことです。適当な考えでうまく運営できるほど甘くはありません。
数年先までの大規模改修計画を、どの時期にどれだけの費用を投じるべきか税理士へ相談するために、具体的な出納データは欠かせません。銀行から追加融資を受けたり、金利の相談をする際も同様です。
さらに物件を売却する時は、事業全体を数字で説明して説得できる、特に詳細で正確な資料が必要です。少なくとも銀行や税理士へ適切な情報が提供できるくらいに、正確な出納データを準備しておきましょう。
自主管理のメリット
賃貸物件の自主管理には、オーナーにとって様々なメリットがあります。自主管理の利点を紹介します。
コスト削減
自主管理の最も大きなメリットに、コスト削減があります。管理会社に委託する場合に発生する月々の管理手数料を節約することができます。例えば、月額10万円の賃料で管理手数料が5%だとすると、年間で6万円のコスト削減になります。一棟の収益物件や複数の物件を所有している場合、この削減効果は更に大きくなります。
また、修繕や清掃などの日常的な管理業務を自ら行うことで、外部業者への支払いも抑えることができます。小規模な修繕や簡単な設備の交換などを自身で行うことで、都度発生する出費を減らせます。
賃貸経営は、キャッシュフローが重要なため、支出を抑えることで収益性向上に直接的に寄与します。特に、経営が軌道に乗るまでの初期段階や、収益が厳しい時期には、自主管理は効果的とも言われています。
入居者とのコミュニケーション
自主管理のもう一つの大きなメリットは、オーナーが直接入居者とコミュニケーションを取れることです。これにより、入居者のニーズや要望をより深く、そして迅速に理解し対応することが可能になります。入居者から設備の不具合の報告があった際、オーナーが直接確認することで、問題の緊急性や修繕の必要性をすぐに判断できます。
直接的なコミュニケーションは、入居者との信頼関係構築に大きく関係します。信頼関係が築かれることで、長期入居の促進、トラブルの未然防止、口コミによる新規入居者の獲得などの好循環が生まれます。
不動産知識・運営能力の向上
自主管理を通じて、オーナーは賃貸物件管理に関する幅広い知識やスキルを習得することができます。これは、不動産投資や経営の拡大に向けた貴重な資産となるでしょう。
建物のメンテナンス、法律や税務の知識、入居者対応のノウハウ、マーケティング能力、財務管理スキルなど、様々な知識や経験を身をもって学ぶことができます。
日常的な点検や簡単な修繕を通じて、建物の構造や設備に関する理解が深まったり、賃貸借契約の締結や更新、確定申告などを通じて、不動産関連の法律や税務について学ぶことができます。
経験を積むことで、オーナーは単なる物件所有者から、プロフェッショナルな不動産経営者へと成長することができると言っても過言ではありません。
自主管理のデメリット
自主管理には魅力的なメリットがある一方で、看過できないデメリットも存在します。自主管理のデメリットを十分に理解し、自身の状況と照らし合わせて検討しましょう。
時間と労力の負担
自主管理の最大のデメリットは、オーナーに課せられる時間と労力の大きな負担です。賃貸物件の管理は24時間365日の仕事であり、予期せぬタイミングで対応を求められることも少なくありません。
入居者対応、建物メンテナンス、書類作成と管理、家賃の集金と滞納対応、新規入居者の募集など、多岐にわたる業務が発生します。例えば、夜間や休日に設備トラブルへの対応を求められたり、季節ごとの作業(落ち葉の処理など)を行ったりする必要があります。また、賃貸借契約書の作成や更新手続き、各種届出書類の準備など、煩雑な事務作業も発生します。
特に物件数が多い場合や緊急対応が必要な場合に、オーナーの日常生活や本業がある場合には本業に、大きな影響を与えます。真夜中の水漏れトラブルや、長期休暇中の設備故障など、プライベートな時間を犠牲にしなければならないこともあるでしょう。
また、これらの業務に時間を取られることで、新たな投資機会を逃したり、より戦略的な経営判断に時間を割けなくなったりする可能性もあります。結果として、事業の拡大や収益性の向上が阻害されるリスクもあるのです。
安定的な自主管理の難しさ
自主管理では、管理の質にばらつきが生じる可能性があり、長期的な視点で見たときに、物件の評判や資産価値に大きな影響を与える可能性があります。
オーナー自身の健康状態の変化、本業の繁忙期、家族の事情、休暇や旅行、精神的なストレスなど、様々な要因により安定的な管理が難しくなることがあります。例えば、病気や怪我により一時的に管理業務に手が回らなくなったり、本業が忙しくなって賃貸管理にかける時間が制限されたりすることがあります。また、育児や介護など、個人的な事情により管理業務に集中できなくなることもあるでしょう。
これらの要因により、入居者からの問い合わせや苦情への対応の遅れ、定期的なメンテナンスの遅延や見落とし、新規入居者の募集活動の停滞、家賃の集金や滞納対応の遅れ、書類管理や会計処理の乱れなどの問題が発生する可能性があります。
24時間365日の対応が求められる賃貸管理において、これらの問題は入居者の不満を高め、退去につながる可能性があります。また、物件の評判が落ちることで、新規入居者の獲得も困難になるでしょう。さらに、長期的には建物の維持管理が行き届かなくなり、資産価値の低下につながる恐れもあります。特に、複数の物件を所有している場合、全ての物件に対して安定した管理を提供し続けることは、個人では非常に困難です。
資産価値低下のリスク
適切な管理ができないことにより、物件の資産価値が低下するリスクがあります。資産価値の低下は、将来的な売却や資金の借入などに大きな影響を与えます。
自主管理によって十分な対応ができず、建物の劣化、入居者の満足度低下、周辺環境への対応不足などによって資産価値が低下する恐れがあります。管理サービスの質が低下すると入居者の満足度が下がり、口コミ等を通じて物件の評判を落とし、将来的な入居率にも影響します。
長期的な視点での修繕計画の立案や実行が難しい場合、リスクはさらに高まります。大規模修繕のタイミングを逃したり、必要な投資を先送りにしたりすることで、建物の劣化が加速し、結果として資産価値が大きく低下する可能性があります。
また、不動産市場の動向や法規制の変化に適切に対応できないことも、資産価値低下のリスクとなります。省エネ基準の強化や耐震基準の見直しなどの法改正に対応できないと、物件の競争力が低下し、資産価値に影響を与える可能性があります。
賃貸物件の自主管理に潜むリスク
賃貸物件を自主管理することは、メリットもありますが、当然リスクも存在します。
ここでは、自主管理に潜むリスクについて、それぞれ紹介します。
建物管理に関するリスク
建物管理は、各設備ごとの保守点検ルールを規定する建築基準法や消防法、電気事業法などの法律に関する、幅広い知識を必要とします。
問題がある設備の補修や交換対応をその都度するだけではなく、設備によって推奨される交換目安の時期があり、数年先にわたって適宜対策していく計画性が必要です。
設備が急に故障したり、自然災害で建物に大きな被害が出ることで、停電や犯罪などが発生する場合があります。そういった緊急の対応に迫られる場面などを想定して、日ごろから対策を考えておきましょう。
入居者・管理業務に関するリスク
入居者・管理業務は人が関わりますので、対応を間違えると予想以上に問題を大きくしてしまうリスクがあります。そのため、初期対応などの重要性が高いのは建物管理よりもこちらです。
賃貸事業の中で最も大切な家賃収入に直結する要素が多いので気が抜けません。治安が悪い、騒音問題が解決していない、滞納者が住んでいるなど悪い情報が地域に広がると募集活動に影響が出ます。また、少々費用が掛かっても内装のセンスや設備の目新しさで、お客様への訴求効果の高い仕様にして競合物件に勝つための対策をしましょう。
仲介業者は不安要素の多いマンションを積極的に紹介してはくれません。反対に、お客様が喜びそうな物件であれば、進んで紹介してくれます。物件になにか目新しいプラス要素が加われば、進んで仲介業者に知らせるなど、普段からコミュニケーションを密にしておきましょう。話の分かるオーナーだと地域の仲介業者に認知されるようにしてください。
賃貸事業への向き合い方が時代と逆行するリスク
例えば、いま単身者に人気のマンション設備といえば、下記のようなものが挙げられます。
宅配ボックス / 録画機能モニター付きインターホン / 浴室暖房乾燥機 / 独立洗面化粧台 /
ウォークインクローゼット / 洗浄機能付きトイレ / 光インターネット無料 / 追い炊き機能 / 床暖房 / 24時間利用ゴミステーション / 2口コンロ / ディンプルキー / 非接触カードキー /
このような設備はあるに越したことがない程度で、契約を決める決定的な理由にはならないと思ってしまうと危険です。
市場や顧客の要望より経費削減意識が勝ちすぎて目の前の利回りしか見えなくなると、空室率が高くなる可能性があります。
実際、賃貸物件の空室率は上昇傾向にあります。
もちろん全ての人気設備を導入する必要はありませんが、世の中の動向を柔軟に受け入れる姿勢は持つべきです。
自主管理から管理委託へ切り替える際のポイント
自主管理のデメリットを感じた場合、管理委託への変更を検討することも一つの選択肢です。その際のポイントについて紹介します。
管理会社の選び方
管理会社を選ぶ際は、以下の点を重視して比較検討することが重要です。
まず、実績と評判を確認しましょう。管理実績や他のオーナーからの評判は、管理会社の信頼性を測る重要な指標となります。長年の実績がある会社や、口コミ評価の高い会社を選ぶことは重要です。
次に、サービス内容を詳しく確認しましょう。提供されるサービスの範囲と質を比較検討することが重要です。例えば、24時間対応の緊急サービス、定期的な建物点検、入居者募集のサポート、法務や税務のアドバイスなど、どこまでのサービスが含まれているかを確認します。自身の物件や管理の状況に合わせて、必要なサービスを提供している会社を選びましょう。
費用も重要な選択基準です。管理手数料や追加サービスの料金体系を確認し、自身の予算と照らし合わせて検討します。ただし、単に安いだけでなく、サービスの質とのバランスを考慮することが大切です。
コミュニケーション能力も見逃せないポイントです。担当者との相性や連絡体制を重視しましょう。迅速かつ丁寧な対応ができる会社を選ぶことで、スムーズな管理委託が可能になります。また、オーナーの要望や意見をしっかりと聞き入れ、柔軟に対応してくれる会社であることも重要です。
変更のタイミング
自主管理から管理委託への変更は、適切なタイミングを選ぶことで、よりスムーズに移行することができます。
空室期間
新規入居者募集前に変更することで、管理体制の移行がスムーズになります。空室期間中は、建物のメンテナンスや修繕を行うのに適した時期でもあるため、この機会に管理会社に物件の状態を詳しくチェックしてもらい、必要な対策を講じることができます。また、新規入居者の募集から管理会社に任せることで、より効率的な集客が期待できます。
個人的な生活環境の変化時
転職や家族構成の変化など、個人的な生活環境が大きく変わるタイミングも、管理委託への移行を検討するのに適しています。自主管理に割ける時間や労力が変化する際に、管理体制を見直すことで、より安定した賃貸経営が可能になります。
契約更新時
既存の入居者との契約更新のタイミングで変更すると円滑です。契約更新時には、賃貸条件の見直しや新しい契約書の作成が必要となるため、この機会に管理会社への移行を行うことで、入居者への説明もしやすくなります。また、新しい管理体制での契約を結ぶことができるため、後々のトラブルを防ぐことができます。
参考:賃貸物件の委託管理とは
自主管理の反対に、管理会社に管理を任せる委託管理があります。
民間賃貸経営の全体の80%が管理を管理会社に委託しています。
参照:国土交通省「参考資料」
ここでは、委託管理についてメリットやデメリットを紹介します。
委託管理のメリット
委託管理のメリットとして次のようなことが挙げられます。
-
- 法令の変化に対し敏感
- 書類やカギの管理など安心
- クレームを自分で解決しなくてもよい
- 物件が遠くても現地へ行かなくてよい
家主がすべきことは管理会社が全て代行するため、何もせず報告を受けるだけでよく、楽です。また管理水準は素人の比ではありませんし、数年先の改修予定を立てて節税時期に合わせた実施時期と費用の程度も提案してくれます。
委託管理のデメリット
毎月管理委託料がかかることが、最も大きなデメリットです。
また、管理会社の選定を誤ると自主管理より質が落ちる場合もあります。その理由の1つとして、業界の体質が関わっています。マンション管理業界は平均的に薄利で1人の担当者が抱える棟数は多いのが普通です。もし、問い合わせや見積もり依頼にすぐの返信がない場合には要注意かもしれません。
管理を任せるときのポイント
管理会社に管理を委託する際でも、業務を完全な丸投げする姿勢はおすすめしません。賃貸事業を将来に渡り、安定して経営をするためには、実務に即した経験と知識は大きなアドバンテージになります。
管理会社と有効なパートナーシップを築く必要があるのは、間違いありませんが、完全に任せっぱなしにするだけではいけません。
できる限り自分で情報収集をすること。不動産経営そのものへの興味関心は強く持ちましょう。
管理委託料は回収賃料の約3%~5% が目安だと言われますが、受託業務の内容・地域・会社の規模などで変わりますので、見積は数社に依頼して比較検討することをおすすめします。
賃貸物件の自主管理をする上で重要なポイント
自主管理におけるリスクや、委託管理のメリットをデメリットを紹介してきました。
ここでは、自主管理をするうえで重要なポイントを紹介します。
スピード感が重視される
昨今のネット中心の社会においては決定も反映もリアルタイムが主流です。じっくり考えて「再来週に返答します…」これでは遅すぎます。
事前にさまざまな想定をしておけば判断の精度とスピードが上がります。もし想定しづらい場合には、ネットや書籍で賃貸事業に関する記事を読み込めば、ある程度は自分の知識がつきます。
昔の感覚を引きずらない
前述のように人気の賃貸設備が変化しているほかにも、昔のように家主が有利な契約条件やたくさんの必要書類の提出が当たり前ではなくなりました。礼金、連帯保証人、勤務先への在籍確認、退去時補修費実費精算などもほとんど姿を消しました。時代に合った感覚に自分をアップデートしていきましょう。
自分で設備業者を手配できれば管理コストを下げられる
建物管理も入居者・管理業務も大変な労力ですが、努力した分だけコスト削減はできます。削減できたお金は賃貸設備の刷新に充てて、少しでも競合物件に勝てるように工夫しましょう。
実際賃貸物件の入居者の入居中の不満として、建物の手入れが不十分と感じる人も多いです。
このようなことにならないよう、設備業者を自分で手配することで、入居者の満足度をあげることに注力しましょう。
参照:国土交通省「民間賃貸住宅を巡る現状と課題」
確かな情報の窓口を持つ
監督官庁や専門機関ができて、ますます賃貸管理は複雑で厳格になり、苦労が増えました。しかし逆に、詳しく調べられる専門窓口ができたとも考えることができます。ネットからも新鮮な情報が得られるようになりました。
SNSによって、家主を見つけることも家主同士が交流をすることもとても簡単ですし、SNSなら賃貸の募集活動を仲介業者に頼らなくてもできる時代です。有料セミナーなども適宜活用して効率よく情報収集をしていきましょう。
賃貸事業について理解を深めよう
本業があって時間を割けないと自主管理をしていくのはなかなか難しいでしょう。そして自主管理は常に法令や業界研究、トレンドなどを勉強して知識を蓄えないと、間違った運営になりがちなので注意が必要です。
もし、小規模マンション(3階から5階までの中層住宅や2階建てのハイツタイプ)でエレベーターや貯水槽・高架水槽や加圧ポンプなどがない場合には、建物管理の部分がかなり少なくてすみます。そのため、自主管理でも負担は大きくないと考えられそうです。
逆に、入居者・管理業務については小規模なほど懸念材料が多い傾向にあります。その理由として、以下のようなことが考えられるからです。
-
- 共用部分が外と隔てられていないので防犯上の不安がある
- 壁が薄いため騒音問題が起こりやすい
- 築浅の鉄骨鉄筋コンクリートの物件と比較すると、物件の魅力が競り負けるので対抗するために知恵が必要
- 専任の管理人がいないので即時の現場対応ができない
このように物件の特徴・長所・短所を理解した上で何が足りなくて何を優先してどこまでやれば良いのか、また自分で管理する場合どこまでできるのかを判断し、場合によっては一部だけ管理委託にするのもひとつの方法です。
いつの時代も賃貸事業は投資事業の前線にいますので書籍やセミナーが豊富です。管理業務について何から勉強して良いのか分からない場合は、独学ではなくしっかりと体系的に教われる方法を選んで学ぶようにしましょう。
賃貸経営をスムーズに管理するなら「ビズアナオーナー」
当社が提供している無料の収支管理サービス「ビズアナオーナー」は、賃貸経営を行っているオーナーが利用する無料の収支管理サービスです。
月々の収支データを無料で簡単に自動でデータ化し、わかりやすいビジュアルで経営状況を把握することができます。
また、ビズアナオーナーの会員限定で、補助金や節税、空室対策に関する最新の情報やダウンロード資料なども随時配布しています。
その他にも、賃貸経営に役立つサービスも特別価格や無料で利用いただくことが可能です。
是非、「ビズアナオーナー」を無料登録してみてください。
【めんどうな入力は一切不要で収支管理が楽になる!】
- 年間収支や稼働状況を分析するためのデータは事務局が無料で代行登録
- 出納データもボタン一つでカンタンに出力できる
- 月額利用料0円で気軽にスタートできる
ビズアナオーナーは、毎月の収支管理を無料で自動化したい不動産オーナー様におすすめです