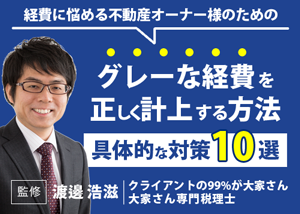賃貸オーナーができるベランダの喫煙対策。トラブルに発展してしまったら?

2020年4月、改正健康増進法が全面施行され、望まない受動喫煙の防止対策が強化されました。
非喫煙者からすると、多くの方がたばこのにおいに不快感を持つようです。アパートやマンションなどの賃貸物件の経営では、入居者の喫煙マナーがしばしば問題になります。
本記事では、ベランダでの喫煙が賃貸経営においてどのような影響があるのか、またどうすれば防げるかの具体的な方法を解説します。さらに、トラブルに発展してしまった場合の対処方法も紹介するので、賃貸経営の参考になれば幸いです。
ベランダでの喫煙が及ぼす影響
ベランダでの喫煙は入居者同士のトラブルや苦情につながります。具体的にどういった影響があるのか見ていきましょう。
そもそもなぜベランダでの喫煙はダメなの?
ベランダでの喫煙について、「自宅なんだから喫煙も自由じゃないの?」と考える方もいます。
しかし、マンションなど区分所有建物に関する法律である区分所有法では、ベランダは共用部分であると定められています。共用部分とは、複数の住民が使うスペースのことです。
-
- 家財道具を放置したままでいなくなる
- 家財道具も移動させて、もぬけの殻になっている
上記のような理由から、入居者が勝手に大きな荷物や工作物などを設置してしまうと問題になってしまいます。
通常ベランダでは、その部屋に住んでいる人だけが使用できる専用使用権が認められており、エントランスや廊下などの一般的な共用部とは区別されています。しかし、その使用方法はあくまでルールに従う必要があります。
そのため、賃貸物件のオーナーは、ベランダでの喫煙をやめるように入居者に対して求めることができます。
入居者同士のトラブルにつながる
ベランダでの喫煙を放置すると、入居者同士の近隣トラブルが起こるおそれがあります。
ベランダには洗濯物を干している人も多いため、喫煙により洗濯物ににおいがついてしまいます。たばこのにおいは喫煙しない人にとってはとても気になるため、近隣トラブルに発展しやすくなります。
また、コロナ禍以降在宅時間が増えたこともあり、気候のよい時期は窓を開けて換気していることも多いでしょう。入居者がベランダで喫煙している場合、風に乗って近隣の住戸にたばこの煙が届いてしまうことがあります。
禁煙の決まりがない物件でも、壁紙へのヤニ対策や家族への受動喫煙を避けるため、ベランダで喫煙するというケースもあります。「自分の家族に受動喫煙させないために、近隣の他人に迷惑をかけるのか!」と思う人がいるのも当然で、トラブルにつながるおそれがあります。
入居者からの苦情
近隣トラブルが起こると、入居者からの苦情はオーナーや管理会社に向けられます。
管理物件の入居者がベランダで喫煙していても、たまたまタイミングよく現場を目撃しなければ気づくことは難しいでしょう。そのため、ほとんどのケースでは近隣の入居者からの苦情で発覚します。
-
- 小さい子どもがいるからベランダでの喫煙をやめさせてほしい
- 洗濯物に臭いが付いて困る
上記のような苦情が寄せられると、オーナーとして対処する必要があります。
トラブルが大きくなってしまうと、退去する人まで出てきて、賃貸経営にも影響が出るおそれがあります。円滑な賃貸経営をするためにも、早めに対策を取りましょう。
ベランダでの喫煙対策
賃貸経営のオーナーが入居者に喫煙をさせない、やめさせるには具体的にどのような対策を取ればよいのでしょうか。
全面禁煙にする
ベランダでの喫煙対策で最も効果的なことは、そもそも喫煙者が入居しないようにするということです。
賃貸物件の場合、入居者を募集する段階でペットや喫煙についてのルールを定めることができます。近年、全面禁煙の賃貸物件は増加傾向にあり、普段から喫煙しない人にとってはメリットとして訴求できます。
賃貸契約の前に不動産会社に行ってもらう重要事項説明で、下記などをしっかりと伝えてもらいましょう。
-
- ベランダも含めて敷地内は全面禁煙である
- 友人の喫煙であってもルール違反になる
全面禁煙に納得した上で入居してもらうことが大切です。
賃貸契約書の禁止事項を確認する
万が一ベランダで喫煙する人がいるなら、やめてもらうよう働きかけなければなりません。
まずは、賃貸借契約書の禁止事項を確認しておきましょう。禁止事項にベランダでの喫煙が明記されていれば、喫煙者を注意するための重要な根拠になります。
禁止事項に明記されていない場合、「入居時にそんな話は聞いていない」と反論され、交渉が長引くおそれがあります。
しかし、たとえ賃貸借契約書の禁止事項に掲載されていなかったとしても、繰り返し注意されてもベランダでの喫煙をやめなかった場合は、不法行為と認められるケースもあります。その場合も粘り強く交渉することが大切です。
張り紙や回覧板で通知する
ベランダでの喫煙をやめてもらうには、まず第1段階として張り紙を掲示することが有効です。
特に問題がなくとも、普段から禁煙である旨の張り紙をしておくのもよいですが、タバコのトラブルが発生してしまった場合は下記の事項を明記するとよいでしょう。
-
- ベランダでの喫煙は禁止であること
- ベランダで喫煙している人がいること
- ベランダでの喫煙により苦情が発生していること
- ベランダでの喫煙をやめるよう警告
掲示板やエレベーター内、エントランスホールなど、共用部分の目につくところに掲示しましょう。入居者全体に周知することで、自発的に喫煙をやめてもらうよう働きかけます。
また、入居者全員のポストへ、お知らせのプリントを投函するのも効果的です。
自分の喫煙が苦情になっていることに気づいてもらえれば、この段階でやめてもらえるケースが多いでしょう。
トラブルに発展してしまったら?
上記で紹介した張り紙や対策を行ってもベランダでの喫煙をやめてもらえず、トラブルやクレームに発展してしまった場合はどういった対策をすればよいのでしょうか。
解決を急ぐあまり、急に罰金などの厳しい措置をとってしまうと後々別のトラブルにも発展しかねません。徐々に段階を踏んで進めていくことが大切です。
喫煙者に直接やめるように通知する
以下のような場合は、問題のベランダ喫煙者に直接やめるように通知する必要があります。
- 共用部への張り紙やポストへのお知らせ投函でも喫煙をやめてくれない
- すでに大きなトラブルになってしまっている
張り紙を見ていなかった場合や、吸っている時間帯などを理由に自分のことではないだろうと都合よく解釈している可能性もあります。
一般的には文書で通知しますが、それでもやめてもらえない場合は、電話や直接会って伝える方法も効果があります。
この際、苦情を言った人が誰なのかを喫煙者に悟られないように注意しましょう。
苦情の発信者が特定されてしまうと、喫煙者側が逆恨みして嫌がらせをするなどのトラブルに発展するおそれがあります。
たばこは依存性の強い嗜好品ですから、吸えない苛立ちが苦情を言った人に向かうことのないよう、十分に配慮する必要があります。
法的手段に出ることを伝え、警告する
張り紙や直接の通知でも喫煙をやめてくれない場合は、法的手段に出ると、より強い警告をする必要があります。
名古屋地裁が2012年に出した判例では、ベランダで喫煙した住民が損害賠償を命じられました。
この事例は住民同士の裁判でしたが、このような判例を調べて資料を添付した上で警告するのも非常に効果的でしょう。
また、賃貸借契約書にベランダでの禁煙が禁止事項として明記されている場合、ルールに従ってもらえない場合は退去を求める旨の警告をすることも有効です。
管理会社に任せる
喫煙者に直接通知したり、電話や口頭での注意などに、感情的な対応をしてくる入居者もいます。基本的にオーナーが自ら行うのではなく、賃貸管理会社に任せるのがおすすめです。
管理会社には、マナー違反の入居者に対する対処法などのマニュアルがあるため、対応に慣れたスタッフがいます。
また、警告や最終手段である退去を求めるという段階になった場合でも、管理会社のスタッフにお願いするのが安心です。
【不動産経営をあらゆる方面から支援!】
- 収支報告書を事務局に送るだけで収支管理を完全自動化
- 不動産経営のプロが講師を務めるセミナーに無料招待
- AI賃料査定・統計調査などのレポート提供
ビズアナオーナーは、PCやスマホで賃貸経営を賢く行いたい不動産オーナー様におすすめです!