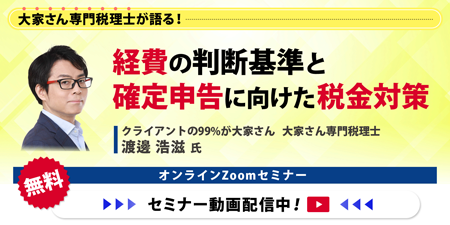不動産投資の確定申告で受け取れる還付金はいくら?必要な手続きも解説
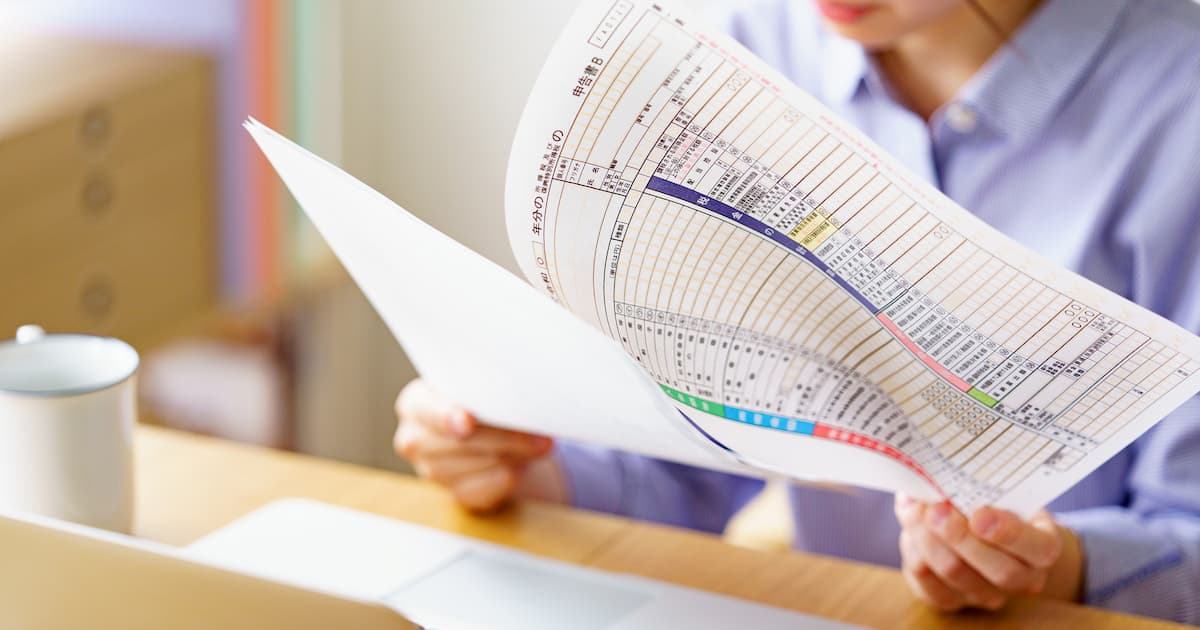
不動産投資の還付金とは
会社員が不動産投資をおこなうことで、還付金を受け取れるケースがあります。還付金とは、いうなれば「払い過ぎた税金」です。
還付金を受け取るためには、正しい手続きを踏むことが重要です。まずは、不動産投資における還付の仕組みと条件、不動産投資で発生する税金について解説します。
還付とは
還付とは、「払い過ぎた税金が返ってくる」ことです。対象となるのは所得税(※)です。
不動産投資で損失が発生した、すなわち不動産所得がマイナスになった場合、給与所得や事業所得といったほかの所得と相殺できます。これが「損益通算」という仕組みです。
会社員は給与所得の額に応じて、所得税や住民税が差し引かれます。しかし、不動産投資で赤字が生じると、損益通算により総所得が下がります。毎月支払っている所得税や住民税が、所得に対して多過ぎる状態になってしまうわけです。
そのため、払い過ぎた税金が返ってきます。これが還付です。
※住民税は還付ではなく、所得が少なくなった分、翌年の納税額が減額されます。また、消費税にも還付はありますが、不動産投資において消費税還付の対象となるケースは稀です。後ほど詳しく紹介します。
還付には確定申告が必要
不動産所得がマイナスになったからといって、自動的に還付を受けられるわけではありません。確定申告をおこない、損失が出ていることを証明する必要があります。
会社員の場合、会社が年末調整をおこない、給与や賞与から差し引かれた源泉徴収税額と本来払うべき税額を計算し、差分を調整してもらえます。
しかし、不動産所得は自身で確定申告をしなければなりません。確定申告を怠ると還付金が受け取れないだけではなく、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されるおそれがあります。
確定申告に慣れていない会社員にとっては、ハードルが高く感じられるかもしれませんが、不動産投資をおこなううえで必ずしなければならないことです。
税務署の確定申告相談コーナーや、専用のフリーソフトなどを上手に利用して、正確に確定申告の手続きをおこないましょう。
関連記事:不動産収入があっても確定申告が不要なケースを解説【20万円以下から?】
不動産投資にかかる税金
不動産投資には多種多様の税金がかかります。税額の算出法や発生のタイミングも税金の種類によって異なるため、投資初心者は混乱してしまうかもしれません。
まずは、不動産投資にかかる税金を、発生するタイミングに分けて紹介します。
不動産購入にかかる税金
不動産購入にかかる税金は以下の3種類です。
- 不動産取得税
- 印紙税
- 登録免許税
不動産投資の初年度は、不動産購入に加え以下のような税金がかかるため、赤字になる危険性が非常に高いです。
| 税種 | 内容 | 税率・税額 | 納税のタイミング |
|---|---|---|---|
| 不動産取得税 | 不動産の購入時や贈与時に発生する税金 | 課税標準額×4%※1 | 購入から約4カ月後 |
| 印紙税 | 不動産購入時の各種契約書に課される税金 | 契約金額によって異なる※2 | 契約書に印紙を直接貼る |
| 登録免許税 | 不動産登記(名義変更)をする際に発生する税金 | 登記の種類によって異なる | 登記申請書に印紙を直接貼る |
※1:税率は地方自治体によって異なる場合があります。また、2026年3月31日までは軽減税率3%が適用されます。
※2:2026年3月31日までは軽減税率が適用されます。
不動産運用にかかる税金
不動産運用にかかる税金は以下の5種類です。
- 固定資産税
- 都市計画税
- 所得税
- 住民税
- 個人事業税
種類が多いうえ、不動産運用をおこなう限り定期的に発生するため、キャッシュフローを悪化させてしまう原因になります。税額や納税のタイミングをしっかり把握しておきましょう。
| 税種 | 内容 | 税率・税額 | 納税のタイミング |
|---|---|---|---|
| 固定資産税 | 土地や家屋に対して課される税金 | 課税標準額×1.4%※ | 自治体によって異なる |
| 都市計画税 | 市街化区域内にある土地や家屋に対して課される税金 | 課税標準額×0.3%※ | |
| 所得税 | 不動産所得に課される税金 | 所得により異なる
(他の所得と合算したうえで税率が決定)
|
確定申告時 |
| 住民税 | 不動産所得に課される税金 | 課税所得×10%+5,000円 | 特別徴収:翌年6月より給与から天引き
普通徴収:納付書に従い、年4回もしくは一括で支払い
|
| 個人事業税 | 不動産投資が事業規模に達した場合、不動産所得に対して課される税金 | (不動産所得-290万円)×5% | 原則として、8月、11月の年2回 |
※自治体によって税率は異なります。
不動産売却にかかる税金
不動産の売却益には所得税・住民税が課されます。ここで注意したいのが、保有期間により税率が異なる点です。
売却した年の1月1日時点の保有期間が5年以下(短期)と5年超(長期)で税率が異なり、
5年以下で売却すると税率が高くなります。保有期間を意識して売却のタイミングを見極めることが重要です。
| 税種 | 内容 | 税率・税額 | 納税のタイミング |
|---|---|---|---|
| 所得税 | 売却益に課せられる税金 | 長期:15.315%※ | 不動産売却翌年の確定申告時 |
| 短期:30.63%※ | |||
| 住民税 | 長期:9% | 特別徴収:翌年6月より給与から天引き
普通徴収:納付書に従い、年4回もしくは一括で支払い |
|
| 短期:5% |
※復興特別所得税(令和19年12月31日まで)を含む
不動産投資の確定申告で受け取れる還付金はいくら?
それでは、不動産投資の確定申告で受け取れる還付金を、例を挙げて紹介します。
例
- 給与所得:600万円
- 各種所得控除:200万円
- 不動産所得:▲100万円
上記の例における課税所得額は以下のとおりです。
(A)確定申告をおこなわなかった場合:400万円(給与所得-各種所得控除)
(B)確定申告をおこなった場合:300万円(給与所得-各種所得控除-不動産所得)
確定申告をおこなった場合、どの程度還付を受けられるのか、計算してみましょう。
所得税の還付額シミュレーション
確定申告をおこない、損益通算をすることで課税所得が400万円から300万円に減少しました。それぞれの課税所得における税額は以下のようになります。
(A)400万円の場合
(400万円×0.2-427,500円)×1.021=38万322円
(B)300万円の場合
(300万円×0.1-97,500円)×1.021=20万6,752円
※税額の計算法は国税庁の「所得額の計算」を参照。復興特別所得税率2.1%を考慮して計算
(A)-(B)=17万3,570円となり、確定申告をおこなうことで17万円程度の還付を受けられることがわかります。
住民税の還付額シミュレーション
住民税は所得が減少した分、翌年に支払う住民税が減額されます。還付ではありませんが、損益通算によって税金が安くなるという点では共通しています。
確定申告をおこない、損益通算することで住民税がどの程度安くなるかを見てみましょう。
住民税は以下のように計算されます。
住民税=課税所得×10%+5,000円
(A)400万円の場合
400万円×0.1+5,000=40万5,000円
(B)300万円の場合
300万円×0.1+5,000=30万5,000円
(A)-(B)=10万円となり、翌年度の住民税が10万円安くなることがわかります。
消費税の還付を受けることは難しい
支払った消費税が受け取った消費税を上回る場合、還付を受けられます。しかし、不動産投資においては消費税の還付を受けられるケースはほとんどありません。
過去においては、不動産購入時に多額の消費税を支払うため、多額の還付を受けることができました。しかし現在では、税制改正により不動産投資における消費税還付の条件が厳しくなったのです。
不動産投資で消費税還付を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 課税事業者であること
- 事業用物件であること
会社員が副業で不動産投資をおこなう場合、免税事業者として居住用物件を購入・運用することがほとんどです。そのため、消費税の還付を受けることはほぼ不可能であるといってよいでしょう。
不動産投資の還付金を受け取る流れや時期
不動産投資の還付金を受けるためには確定申告が必要です。確定申告において準備すべきものや手続きの方法、還付を受けられる時期について解説します。
確定申告の準備
確定申告は、毎年2月16日〜3月15日に申請可能です。
1カ月の申告期間は長いようですぐに期限がきてしまいます。とくに初めて確定申告をおこなう場合は、早めに準備をしておきましょう。
申告の方式を決める
確定申告には、「青色申告」と「白色申告」があります。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 青色申告 | 経費に計上できる項目が多く、節税効果が高い | 手続きが複雑 |
| 白色申告 | 手軽に申告できる | 青色申告と比較して節税効果が低い |
税制優遇の面では青色申告が有利ですが、事前申請や会計処理などの手間がかかるため、副業として不動産投資をおこなう会社員には負担が大きいかもしれません。
投資の規模や投資目的などを考慮して、自分に合った方法を選びましょう。
申告の方法を決める
申告の方法は以下の3種類です。
- 郵送
- 税務署に持参
- e-Tax
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 郵送 | 税務署に行かなくてもよい |
|
| 税務署に持参 | 不明点を直接質問できる |
|
| e-Tax |
|
ICカードリライタやスマホアプリ、マイナンバーカードなどが必要になる |
それぞれにメリット・デメリットがありますので、自身に合った方法を選びましょう。また、e-Taxは事前準備が必要になるため、早めに確認しておくことが重要です。
書類を準備する
確定申告の書類を準備します。基本的に、所得に関する書類はすべて必要であると考えておくとよいでしょう。とくに必要な書類としては以下のようなものがあります。
- 帳簿
- 領収書やレシート
- 各種控除に関する証明書
- 源泉徴収票
確定申告の方法
必要書類をもとに確定申告書を作成します。作成する書類は以下のとおりです。
- 確定申告書(第一表・第二表)
- 収支内訳書(白色申告)/青色申告決算書(青色申告)
- 固定資産台帳
申告書の作成が難しい場合は、税務署の相談コーナーや確定申告専用ソフトを利用するとスムーズです。
最も確実なのは税理士に確定申告を依頼することです。とくに事業規模が大きく、青色申告をしている場合は検討するのもよいでしょう。
なお、確定申告の代行は税理士のみが可能です。税理士以外の第三者に確定申告を依頼すると、税理士法違反に抵触するおそれがあります。
還付はどのように受けられる?
所得税は確定申告から1カ月~1カ月半後(e-Taxを利用した場合は3週間後)に還付されます。
受け取り方法は以下の2つから選択可能です。
- 預貯金口座への振り込み
- 郵貯銀行各店舗もしくは郵便局で受け取る
住民税は6月以降の住民税に反映され、支払うべき住民税が減額されます。
不動産投資の収支管理はビズアナオーナー
不動産投資の収支管理はビズアナオーナーが便利です。
ビズアナオーナーとは、管理会社から提供される収支報告書をアップロードすることにより、各部屋の賃貸料や出費を視覚的に表示するサービスであり、物件の財務状況を明らかにして稼働率を理解しやすくなります。
また、不動産投資にまつわる税金の疑問を税理士が詳しく説明しているセミナー動画などをご視聴いただくことも可能です。
登録は完全無料です。お気軽にご利用ください。
【不動産投資の確定申告にも役立つ!ラクラク収支管理!】
- 収支報告書を事務局に送るだけ!毎月カンタンに収支管理ができる
- 確定申告対策など不動産オーナーのためのセミナーアーカイブ動画が無料で視聴できる
- AI賃料査定レポートサービスなど不動産投資に役立つメニューがお得に利用できる
ビズアナオーナーは、毎月ラクして収支管理を行いながら確定申告にも慌てず備えたい不動産オーナー様におすすめです!
\ビズアナオーナーで確定申告対策も万全!/