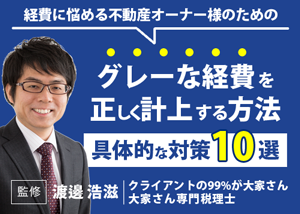賃貸経営の家賃収入に消費税はかかる?税金を抑える方法も紹介

賃貸経営には、消費税や所得税、法人税(法人所有の場合)など、さまざまな税金が発生します。
オーナーが受け取った消費税についても、一定期間中の売上が高い場合は国に納める必要があるため、注意が必要です。
本記事では、賃貸経営でオーナーが受け取る、さまざまな収入に関する消費税について解説します。また、節税する具体的な方法についても詳しく説明するので、賃貸経営のご参考になれば幸いです。
家賃収入には消費税がかかる?
家賃収入には消費税がかかるのでしょうか。消費税の基本的な知識から理解しておきましょう。
消費税とは
そもそも消費税とは、以下の4つの要件を満たす取引に対して課される税金です。
-
- 国内において行われる取引
- 事業者(個人と法人のどちらでも)が事業として行う取引
- 対価を得て行う取引
- 資産の譲渡や貸付け、または役務の提供である取引
以上4つの要件を満たす取引であれば消費税が発生し、顧客が負担します。売上を上げた事業者側が、顧客に代わって国へ納める間接税です。
消費税の免税事業者とは?
売上の少ない事業者側には、顧客から収受した消費税を納めなくともよい免税の制度があります。消費税の免税事業者とは、免税制度を利用できる事業者のことです。
免税事業者になるには、以下2つの基準を満たす必要があります。
|
基準 |
個人事業者 |
法人 |
|---|---|---|
|
前々年の売上が1000万円以下 |
前々年の1月1日~12月31日までの期間 | 前々事業年度の1年間 |
|
その年の最初6カ月間の売上が1000万円以下 |
前年の1月1日~6月30日までの期間 | 前事業年度開始の日以後6カ月間 |
つまり、おととしの年間売上や今年の前半6カ月間の売上が、1,000万円以下であれば免税事業者として認められます。
課税売上の多い法人の経営者は、節税のために法人を複数作って課税売上を分散し、免税事業者で居続けるケースもあります。それほど、免税事業者でいることのメリットは大きいということです。
家賃収入は非課税
賃貸経営では、どういった収入が課税売上や非課税売上となるのでしょうか。
不動産投資においては、以下2つの収入は非課税です。
-
- 土地の譲渡、貸付け
- 居住用建物(住宅)の貸付にかかる家賃
どちらも、「対価を得て」「資産の譲渡、貸付」を行っているため、本来であれば課税取引です。
しかし、消費税は消費者に負担を求める税としての性質があります。土地の譲渡や貸付、住宅の家賃収入は、課税対象としてしっくりきません。そのため、政策的配慮から非課税と定められています。
賃貸アパートやマンションのオーナーは、家賃に関する消費税を受け取っておらず、納める必要はありません。
前述したとおり、一定期間の売上が1,000万円以下であれば免税事業者となります。そもそも消費税がかからない家賃収入は、1,000万円を超えても課税対象者にはなりません。
ただし、居住用ではない以下のような建物の賃貸を行っている場合は、家賃が課税対象になるため注意しましょう。
-
- 駐車場
- オフィス
- 物流倉庫
- 店舗
- ホテル
家賃収入以外のお金は?
家賃収入以外の収入についても、課税対象かどうかを確認してみましょう。
非課税
非課税となるのは、以下のケースです。
- 敷金
- 敷金や保証金はオーナーが入居者から担保として受け取るお金です。そのため、退去時に入居者に返還する必要があり、事業の対価とはされません。
- 礼金
- 礼金は敷金と異なり、オーナーが入居者に返還せずに収入にできます。
- 更新料
- 賃貸借契約の更新時にオーナーが収受します。礼金と同じくオーナーが入居者に返還せずに収入にできます。
- 共益費
- 清掃や点検などの費用として、家賃とは別途オーナーが収受する収入です。
礼金や更新料、共益費は家賃と同じとみなされるため非課税です。
課税対象
課税対象となるのは、以下のような居住用とはみなされない収入です。
- 駐車場代
- その他、入居者が支払う費用
- 仲介手数料や引っ越し代など、入居者が業者に対して支払う費用があります。
ただし駐車場代は、住戸と駐車場がセットになっており、駐車場代が住戸の家賃に含まれている場合は非課税です。
節税方法はある?
賃貸経営のオーナーは、工夫をすれば、節税をして手取り収入を増やすことができます。具体的な方法を説明します。
消費税を抑える
前述したとおり、消費税は前々年に年間1,000万円の課税売上を計上した、個人と法人が対象です。そのため、非課税である居住用建物の賃貸だけを行っている場合は、売上の大部分が非課税となるため、超えることはほぼないでしょう。
課税売上が1,000万円を超えるオーナーは、以下の方法で免税事業者になることをおすすめします。
それは、法人を作り所得を分散させることです。たとえば年間家賃700万円、800万円の2つの物件を所有している場合、単独の個人と法人が売上を計上すると、1,000万円を超えてしまいます。
しかし、法人を作りどちらかの物件をそちらに移せば、それぞれの課税売上が1,000万円を下回ります。そのため、どちらも免税事業者となることができます。
所得税と住民税を抑える
オーナーが特に対策が必要なのは、不動産所得にかかる所得税と住民税です。不動産所得が多いほど、高い税金がかかります。
不動産所得の金額は、以下で計算できます。
不動産所得=不動産収入-必要経費
そのため、日々の支出のうち、賃貸経営に関わる部分の経費をきちんと計上することが重要です。
具体的には、以下のような費用が経費として計上できます。
|
費用 |
概要 |
|---|---|
|
交通費 |
賃貸経営に関わる電車代などの公共交通機関利用、ガソリン代、駐車場代 |
|
書籍代やセミナー代 |
賃貸経営に関わる書籍代やセミナー代 |
|
固定資産税・都市計画税 |
賃貸経営に関わる物件の固定資産税・都市計画税 |
|
損害保険料 |
賃貸経営に関わる投資物件で加入する火災保険の保険料 |
|
消耗品費 |
賃貸経営に関わる文房具やソフトなど各種消耗品の購入費用 |
|
交際費・会議費 |
不動産仲介業者や入居者、税理士との打ち合わせにかかる食事代 |
|
減価償却費 |
投資物件(建物や設備)の取得費を法定耐用年数の期間に渡り少しずつ経費計上する |
|
大規模修繕費 |
投資物件の修繕費用 |
|
管理委託費 |
投資物件の定期清掃や定期メンテナンスなどを委託する費用 |
|
管理費 |
投資物件の管理委託をしている場合、管理会社に支払う費用 |
|
借入金利子 |
投資物件の購入時にローンを借りた場合、その利子分を経費として計上する |
経費計上できるのは、賃貸経営に関するもののみです。プライベートの支出は計上できないため注意しましょう。
関連記事:家賃収入にかかる税金の計算。所得額で違う税率や控除について解説
各種控除を活用する
各種控除を活用することで、所得を圧縮する方法もあります。
たとえば、サラリーマンでも取り組みやすい控除として以下が挙げられます。
-
- iDeCo
- 生命保険料控除
- ふるさと納税
- 医療費控除
会社に勤めているサラリーマンオーナーの場合、生命保険料控除やiDeCoは年末調整で申請できます。一方、医療費控除やふるさと納税を活用するためには、確定申告が必要です。
中でも、使う方が少ないものの、医療費控除はおすすめです。年間10万円を超える治療費や市販薬を支払った場合に、超過分を所得控除できます。対象は「家計を同一にする家族」ならば仕送りしている両親なども含むことができます。
どの控除も、申請するだけでお金が節約できる仕組みのため、積極的に活用しましょう。
自分で収支を管理することが重要
今回は、消費税の仕組みやその対象、具体的な節税方法について説明しました。上手に節税し、手取り収入を増やしましょう。
しかし、手取り収入を増やすために一番重要なのは、賃貸経営における支出と収入をオーナー自身が把握することです。収支を可視化することで、むだな支出があることに気づけるかもしれません。
賃貸経営のオーナーは、管理業務をすべて管理会社に任せてしまいがちです。管理会社からもらった、収支報告書を管理できていない方も多いのではないでしょうか。
収支を管理するためには、ビズアナオーナーを利用することがおすすめです。ビズアナオーナーは、収支データを登録するだけで、一括で管理できます。毎月の収支をスマートフォンなどで気軽に確認して、賃貸経営に役立てましょう。
まずは、無料のプランで試してみるのはいかがでしょうか。
【めんどうな入力は一切不要で収支管理が可能に!】
- 収入・支出状況を分析するためのデータ入力は事務局が代行
- 月額利用料&登録料が0円だから経費が抑えられる
- PCやスマホからいつでも賃貸経営の状況をチェックすることができる
ビズアナオーナーは、毎月の収支管理を無料で自動化したい不動産オーナー様におすすめです!