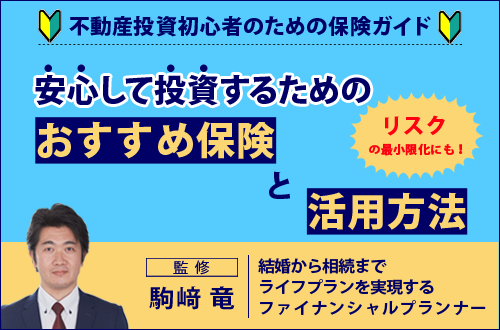賃貸物件が地震で倒壊!?大家はどうするべき?初動対応と事前対策を解説

所有している賃貸物件が地震で倒壊した場合、自然災害による倒壊は不可抗力とされるため、大家さんの責任追及は基本的にありません。
ただし、建物の耐震性不足や瑕疵(かし)によって入居者にケガをさせた場合は、賠償金が発生するケースもあります。
いざというときに大家さんが慌てずに対応できるよう、初動対応の手順、賠償リスクを回避するポイント、事前に行える耐震対策の3ステップを解説します。
地震で賃貸物件が倒壊した場合に大家はどういった対応が求められる?
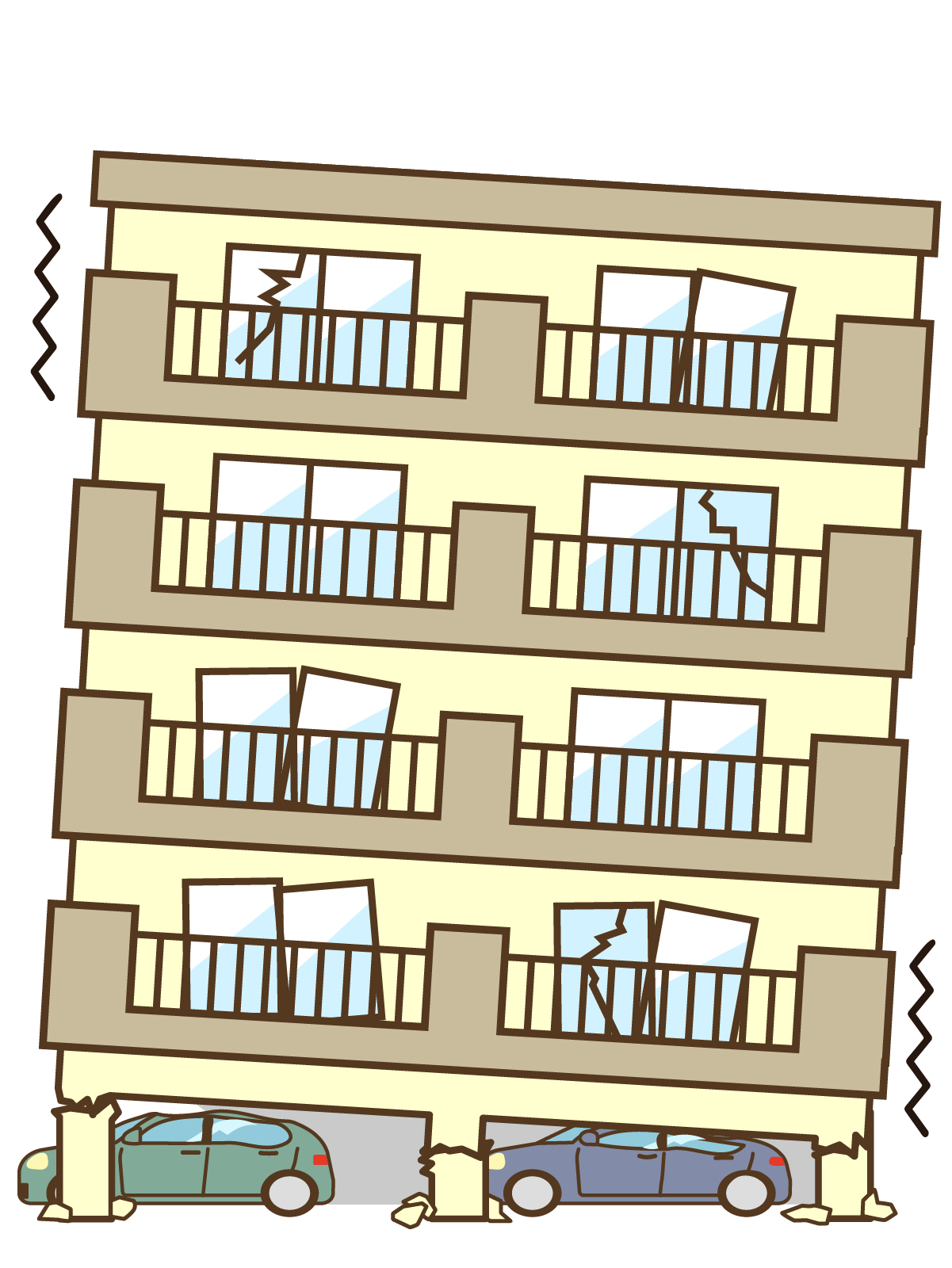
前提として、地震により保有している賃貸物件が倒壊しても、その原因が大家さんになければ不可抗力とみなされます。そのため、基本的には大家さんの責任は問われません。
とはいえ、大家としてやるべきことは多々あります。賃貸物件が地震で倒壊した場合の大家さんの責任や、対処すべきことについて詳しく解説しますので、参考にしてみてください。
現地の状況を確認して関係機関に連絡する
地震が起きたとき、大家さんが最初に行うべきことは現場の状況の確認です。
まずは入居者の安否確認を行い、それから建物や設備の被害状況を目視しましょう。
ただし、倒壊直後は二次被害の恐れもあるため、可能な限り安全な方法で現場の状況を確認することが大切です。まずは、自分や入居者の安全を最優先に行動してください。
なお、地震などの災害による被害は保険で補償できるケースがあります。倒壊直後の状況を示す詳しい資料があると補償手続きを進めやすくなるため、安全に配慮しつつ可能な限り写真や記録を残すのが理想です。
状況確認が一段落したら関係機関に連絡しましょう。管理会社や不動産仲介会社のほか、被害状況によっては消防署・警察への連絡も必要です。
賃貸借契約が終了するため精算を行う必要になる
賃貸物件が地震によって倒壊した場合、原則として賃貸借契約は終了となります。倒壊の時点で賃貸借の目的、すなわち提供できる建物が滅失するためです。
建物が倒壊・全壊には至らなくても、安全に住める状態でなくなった場合でも賃貸借契約が終了となります。
賃貸借契約の終了に伴い、前払いで受け取っている家賃や敷金の返還などの精算が必要です。
建物に瑕疵があった場合は大家が賠償金を支払う
最初に、地震によって建物が倒壊しても原因が大家さんになければ不可抗力とみなされ、責任追及をされないと紹介しました。
しかし倒壊の直接的な原因が地震でも、建物に瑕疵があり、入居者に負傷させてしまった場合は賠償金の支払義務が生じます。
根拠となるのは、民法717条「土地の工作物等の占有者及び所有者の責任」の以下の条文です。
「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」
出典:e-GOV法令検索「民法 第七百十七条」
大家側に賠償責任が生じるケースとして以下の例が挙げられます。
- 耐震基準を満たしていない
- 建築基準法に違反している
- 建物や設備の老朽化を放置し、十分な修繕が行われていない
倒壊した賃貸物件が通常の安全性を有していなかった場合に、損害賠償責任を負うことになると考えておくとよいでしょう。
関連記事:アパート修繕のタイミングや修繕費の相場を紹介!手間や費用を削減するには?
不可抗力による倒壊でも入居者へのサポートは必要?
建物に瑕疵がない場合、最低限必要な対応は「現地の状況確認」「関係機関への連絡」「賃貸借契約の終了に伴う精算」の3つになります。
避難場所の案内や仮住まいの手配など、入居者へのサポートについて法的な義務はありません。
しかし、親身なサポートが入居者との良好な関係の維持や、後の不動産経営における利益につながる可能性はあります。
「サポートをしてはいけない」という決まりもないため、可能であれば入居者へのサポートを実施すると良いでしょう。
とはいえ、大家さん自身の安全や負担を考慮した上で、無理のない範囲で行うことが大前提です。
地震により賃貸物件が倒壊する原因や要因

同じ強さの地震でも、地震によって倒壊する物件と大きな被害はみられない物件が存在します。
地震により賃貸物件が倒壊する原因や要因を4つご紹介します。
新耐震基準を満たしていなかった
新耐震基準を満たしていない物件は、地震による倒壊リスクが高いといわれています。
日本の建築基準法では建築物への耐震設計が義務付けられており、耐震基準が設定されています。はじめて耐震基準が定められたのは1950年11月ですが、その後2度にわたり改正が行われています。
以下は、耐震基準における制定と改定の流れです。
- 1950年11月に建築基準法が制定※現在の「旧耐震基準」
- 1981年6月に「新耐震基準」へと改正
- 阪神・淡路大震災を受けて、2000年6月に「新・新耐震基準」へ改正
新耐震基準は震度6強〜7程度の大地震でも倒壊・崩壊の恐れがないとされる基準です。
それより前の基準である旧耐震基準で設計された建物は、震度5程度までの地震を想定しているため、大地震による倒壊リスクがあります。
参考:国土交通省「Ⅰ 住宅・建築物の耐震化に関する現状と課題」
賃貸物件の建築時に施工不良があった
建築時に施工不良があった賃貸物件は、地震による倒壊が起こりやすいため注意が必要です。
単純な欠陥や不適切な素材の利用のほか、設計面・構造面の問題がみられる場合もあります。
施工工事や設計に問題があるケースとして以下の例が挙げられます。
- 強度の弱い素材や部材を使っている
- 柱や梁が細い
- 壁の数が少ない
- 壁の配置バランスが悪い
- 耐力壁が設置されていない
- 屋根が重い
このような建物は完成直後の時点ですでに欠陥を抱えた状態といえるでしょう。小さな施工不良でも倒壊リスクを大きく引き上げる恐れがあるため、不安な場合は耐震診断を受けるのも1つの方法です。
建物の築年数が古く老朽化していた
耐震基準や施工自体に問題がなくても、建物の築年数が古く老朽化していると地震による倒壊が起こりやすいです。
前述したように、建物に瑕疵がある場合は大家さんに賠償金の支払義務が生じます。築年数が古く老朽化が明らかな建物で修繕が不十分とみなされた場合、賠償責任を問われる可能性が高いです。
液状化しやすい土地の上に建っていた
液状化しやすい土地の上に建っている建物は、そうでない建物に比べて地震による倒壊リスクが高いです。建物の耐震性自体に問題がなくても倒壊する恐れがあります。
2024年1月に起きた能登半島地震でも、杭基礎をしっかり打ち込んでいたものの、液状化によって倒壊した建物が存在します。
地震で賃貸物件が倒壊するのを防ぐための対策

予期せぬ地震によって賃貸物件が倒壊した場合でも、瑕疵があるとみなされると大家さんに責任が問われます。
大家さんの責任が問われないケースでも、現地の確認や賃貸借契約の終了などさまざまな対応が必要です。これらのリスクや手続きの手間が発生しないよう、そもそも地震による賃貸物件の倒壊が起こらないようにするのが最善です。
この章では地震で賃貸物件が倒壊するのを防ぐための対策を3つご紹介します。
耐震性に不安があるときは補強工事を行う
賃貸物件の耐震性に不安がある場合は補強工事を行いましょう。特に新耐震基準を満たしていない場合は、なるべく早く補強工事を行うのが理想です。
国や自治体では、耐震改修工事に関する補助金や助成金制度を運営しています。
例えば東京都では、区市町村の耐震化促進事業に係る助成制度や、耐震化工事・リフォームに関する「耐震化助成制度」を設けています。助成金額や要件は市区町村によって異なるため、詳しくは自治体の公式サイトなどをご確認ください。
また、一定の耐震改修工事を行うことで、所得税の税額控除や固定資産税の減額を受けられます。住宅金融支援機構によるリフォーム融資を受けられる可能性もあるため、費用対効果も期待できるでしょう。
耐震のための補強工事には時間がかかるため、なるべく早く対応することをおすすめします。
定期的に賃貸物件の点検を行う
建物の老朽化による倒壊リスクを抑えるため、定期的に賃貸物件の点検を行う必要もあります。
年に数回程度の定期点検のほか、不安があれば耐震診断も行いましょう。建物や設備の劣化が見つかれば、なるべく早く修繕を行うことが大切です。
地震保険や火災保険に加入する
建物の倒壊を防ぐ対策ではなく、倒壊による損害に対する備えではありますが、地震保険や火災保険への加入は必須です。
地震に対してどれほど入念な対策を行なっても、倒壊リスクを完全に抑えることはできません。
建物の倒壊を招くほどの大地震が起こる確率は低いものの、万が一起きてしまったときの損害は甚大なものとなります。そのため、大家さんは保険に入っておくとよいでしょう。
なお、地震保険単体での加入は原則としてできません。また、火災保険単体では地震が原因の火災は対象外となります。したがって地震保険と火災保険にセットで加入する必要があります。
ちなみに、当社が提供している賃貸経営オーナー向け無料収支管理サービス「ビズアナオーナー」では、「ビズアナ会員」に登録いただくと、会員特別価格や特典が付いている「提携サービス」をご利用いただけます。
ファイナンシャルプランナーへの無料相談もそのひとつで、保険の選定やマネープランなどをお得に専門家に相談することができます。
災害時に備えるための情報も入手できる「ビズアナオーナー」
「ビズアナオーナー」は、賃貸物件オーナー様に向けて無料で提供している収支管理サービスです。
毎月管理会社から送られてくる収支報告書をアップロードすると、各部屋の賃料や支出状況などをわかりやすく視覚的に表示することが可能で、収支状況などを簡単に把握することができます。
また、賃貸経営をサポートする様々なサービスを、ビズアナオーナー会員様限定の特別プランでご用意しています。
賃貸経営に関するお悩みや課題解決は、「ビズアナオーナー」にお任せください。
【ハザードマップ・賃料査定などのレポートも入手可能!】
- 物件周辺のハザードマップや商業施設・教育施設などの情報が得られる
- 物件周辺エリアの家賃相場や将来の賃料予測が分かる
- 不動産オーナーがスマサテのレポートを受け取れるのはビズアナ会員だけ!
ビズアナオーナーは、リサーチデータを上手に活用してリスクに備えたい不動産オーナー様におすすめです!