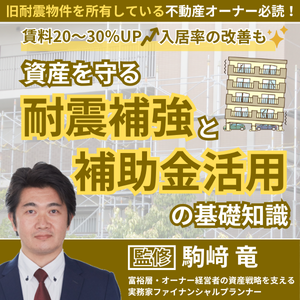【賃貸オーナー必見】補助金対象になる耐震補強工事と適用条件

地震による建物の被害は、完全に防ぐことはできなくても大きく減らすことはできます。特に1981年(昭和56年)以前に建てられた建物は、旧耐震基準のため倒壊リスクが高く注意が必要です。
近年は、国や自治体が耐震補強を促すために補助金制度を整備し、支援を拡充しています。高額になりがちな工事費用の負担を抑えたい方に、賃貸物件で利用できる補助金制度について詳しく解説します。
耐震補強で使える補助金の基礎知識

耐震補強工事とは、主に倒壊する危険性がある建物の耐震性能を向上させる工事です。現在多くの自治体では、耐震補強工事を対象とした補助金制度を設けています。
最初に耐震補強工事で補助金が出る理由や、耐震補強をしない場合のリスクについてわかりやすく解説します。
耐震補強で補助金が出る理由
耐震補強で補助金が出る理由は、地震による建物の倒壊防止や防災意識を向上させることで、国や自治体にとっても大きなメリットがあるためです。
日本は海のプレートが陸のプレートに潜り込んだときに起こる「海溝型地震」と、活断層による「内陸型地震」の両方が起こりやすい国です。たとえば、「宮城県沖の陸寄りの地震」では30年以内の発生確率が70%〜90%、南海トラフ地震の発生確率は60%〜90%程度といわれています。
内陸型地震については、「糸魚川-静岡構造線断層帯」で30年以内に大地震が起こる確率は、14%〜30%の予測です。
地震による被害は建物の耐震性能によって大きく左右されます。同じ規模の地震であっても、多くの建物が倒壊した場合と建物の損壊が少ない場合では、後者の方が被害は小さいでしょう。
地震の発生を完全に防ぐことはできませんが、建物の耐震性能を高めることで被害を最小限に抑えることは可能です
そうはいっても、耐震補強工事には高額の費用がかかるため賃貸オーナーには負担が重く、後回しにしてしまう方もいます。そのため、国や自治体は耐震補強に対する補助金を設けているのです。
参考:地震調査研究推進本部(文部科学省)|「地震発生確率」について解説します
南海トラフの地震活動の長期評価(第二版一部改訂)について
今までに公表した活断層及び海溝型地震の長期評価結果一覧
物件の耐震補強をしないとどうなる?
所有する物件の耐震補強をしない場合、以下のようなリスクがあります。
- 物件の損壊によって住める状態ではなくなり、家賃収入が得られなくなる
- 外壁に傷やヒビが発生、基礎部分や設備の破損により資産価値が低下する
- 高額な修繕費用の支出が発生する
- 入居者のケガ・死亡による損害賠償責任を問われる
- 資産価値の下落に伴って家賃の引き下げが必要になり、家賃収入が減少する
物件の耐震補強をしなければ地震による被害が大きくなり、家賃収入の低下および支出の増大が起こる恐れがあります。耐震補強工事に高額の費用がかかるとはいえ、工事をしないリスクの方が高いといえるでしょう。
【最新版】賃貸物件でも利用可能な耐震補強の補助金制度

前述したように、物件の耐震補強工事は地震による被害を抑える上で必要不可欠です。そのため、国や自治体は工事を促進する目的で、耐震補強に関する補助金制度を設けています。
賃貸物件でも利用可能な耐震補強の補助金制度について詳しく解説します。
長周期地震動対策の補助制度
国は南海トラフ地震による大きな被害が想定されるエリアに対して、賃貸物件を対象とした補助金制度を行っています。
| 制度の概要 | 巨大地震による長周期地震動の対策が必要なエリア内にある物件(※1)のうち、以下のいずれかの要件を満たした場合に、耐震補強にかかる費用の一部を補助する制度
|
|---|---|
| 助成対象 | 詳細診断、改修設計、改修工事 |
| 補助率 | 詳細診断に要する費用:3分の1 改修設計に要する費用:3分の1 改修工事に要する費用:11.5% |
| 改修工事の補助限度額 | 次のうちいずれか低いほうの額が適用
|
出典:国土交通省|長周期地震動対策の補助制度のご紹介
東京都品川区:耐震化支援事業
東京都品川区の耐震化支援事業は、木造・非木造・分譲マンションと、種類によって要件や助成額などに違いがあります。
| 制度の概要 | 一定の要件を満たす物件の耐震補強工事について、工事費用の一部を助成する制度 |
|---|---|
| 助成対象 | 耐震改修工事 |
| 助成率 | 【木造物件】 耐震改修工事のみ申請する場合:2分の1 補強設計と耐震改修工事の同時申請する場合:3分の2 |
| 改修工事の助成限度額 | 【木造物件】 共同住宅:450万円 補強設計+耐震改修工事の同時申請では最大600万円 |
参考:品川区|木造住宅の補強設計・耐震改修工事のご案内
埼玉県:建築物耐震改修など事業
埼玉県は多数の人が利用する施設の耐震工事を助成しています。学校や病院のほか、3階以上かつ1,000㎡以上の共同住宅も利用可能です。
| 制度の概要 | 多数の者が利用する建築物の耐震改修に要する費用の一部を助成 (所管行政庁12市を除く) |
|---|---|
| 助成対象 | 耐震改修工事・建替工事・除却工事 |
| 助成率 | 一般建築物:23% |
| 補助対象事業費 | 【共同住宅(マンションを除く)】34,100円/㎡ 【マンションの場合】50,200円/㎡ |
| 改修工事の助成限度額 | 一般建築物:1,300万円(設計+工事) |
参考:埼玉県|埼玉県内の住宅・建築物の耐震診断・耐震改修に関する補助制度などのご案内
神奈川県川崎市:耐震改修補助
神奈川県はさまざまな市町村で耐震診断や耐震改修の補助制度を設けています。中でも川崎市は小規模アパートなどでも利用できる制度を用意しているため、多くの賃貸経営者が該当する可能性が高いでしょう。
| 制度の概要 | 神奈川県内の市町村で、耐震診断、補強設計、耐震改修などに要する費用の一部を助成 |
|---|---|
| 助成対象 | 【小規模アパートの場合】 精密診断、補強計画、工事整理、補強工事 【マンションの場合】 設計、工事 |
| 助成率 | 【小規模アパートの場合】 精密診断・補強計画:5分の4(部分改修工事の場合3分の2) 工事監理・補強工事:5分の4(部分改修工事の場合3分の2) 【3階以上のマンションの場合】 設計:3分の2 工事:15.2% |
| 改修工事の助成限度額 | 【小規模アパートの場合】 1棟につき工事監理・補強工事:85万円 (部分改修工事の場合は60万円) 【3階以上のマンションの場合】 1戸あたり設計5万、工事30万円 |
参考:神奈川県|県内市町村における耐震診断・改修および1部屋耐震補助一覧
耐震補強で補助金制度を利用するときの注意点

補助金制度は無条件で利用できるものではありません。利用する際はいくつか注意すべき点が存在します。耐震補強で補助金を活用するときの注意点について詳しく見ていきましょう。
補助金を申請する流れを理解する
まずは、補助金を申請するときの流れを確認しましょう。以下は、東京都中央区で耐震補強の申請を行うときの大まかな流れです。
- 区の担当者に相談※中央区の場合は職員が現地で確認
- 交付申請書を提出
- 交付決定通知書を受け取った後、施工業者と契約
- 耐震改修工事の着手
- 工事の完了報告書類の提出、助成金の支給
耐震改修工事の補助金制度は、耐震診断で耐震性に問題があると判明した場合のみ対象としているケースがほとんどです。事前に無料相談会や耐震診断を受けるケースもあるため、必ず担当者に確認しましょう。
また、耐震補強に限らず、補助金や助成金の対象となるのは一般的に「制度の申請後に決定・支出した費用のみ」です。補助金の交付が決定する前に施工業者と契約してしまうと、補助や助成を受けられない可能性があるため注意してください。
制度によっては、手続きに細かいルールが定められていることがあるため、補助金が交付されるまでの流れについて確認しておくと安心です。賃貸物件の場合は、耐震改修工事を行うにあたって入居者に対する説明や対応を考えなくてはいけません。
参考:中央区|中央区耐震助成制度パンフレット
補助金の要件に該当するか確認する
補助金の要件に対して、所有する賃貸物件が該当しているかの確認も必須です。要件は自治体によって異なるため、利用を検討している段階で詳細を確認しましょう。
特に確認すべきポイントとして以下の3点が挙げられます。
- 対象とする物件の種類(共同住宅、店舗、学校、施設など)
- 対象とする物件の構造(木造と非木造に分かれているケースがあるため)
- 物件の築年数、耐震診断の結果に関する条件
耐震改修の補助・助成制度の中には、店舗や学校など住宅以外の建築物のみを対象とした制度も存在します。共同住宅が利用できる場合でも、木造物件のみを対象としたケースも多いです。
また、新耐震基準の適用前に建設された物件のみを対象とする制度も少なくありません。制度の要件は細かく定められているため、所有物件が対象かどうかを慎重に確認することが大切です。
補助金に対応できる施工会社か確認する
耐震改修工事における補助金を活用するには、施工会社の協力が必須です。制度の利用に対応できるところかを確認しましょう。
施工会社への相談・報告は、補助金の交付が決定した後ではトラブルにつながる恐れがあります。まずは、制度の利用を検討している段階で問い合わせをすると安心です。
耐震補強は、建物の安全性と資産価値を守るための投資です。国や自治体の補助制度を活用し、信頼できる施工会社や管理会社に相談しながら、無理のないスケジュールで進めましょう。
賃貸経営に役立つ情報を知るなら「ビズアナオーナー」
当社が提供している無料の収支管理サービス「ビズアナオーナー」は、賃貸経営を行っているオーナーが利用する無料の収支管理サービスです。
月々の収支データを無料で簡単に自動でデータ化し、わかりやすいビジュアルで経営状況を把握することができます。
また、ビズアナオーナーの会員限定で、補助金や節税、空室対策に関する最新の情報やダウンロード資料なども随時配布しています。
その他にも、賃貸経営に役立つサービスも特別価格や無料で利用いただくことが可能です。
是非、「ビズアナオーナー」を無料登録してみてください。
【賃貸経営にも役立つコンテンツをラインナップ!】
- 収支報告書を事務局に送るだけで毎月の収支管理ができる!しかも無料!
- AI賃料査定レポートで設備による賃料の増減を簡単に把握できる
- 統計調査レポートで周辺の商業施設・教育施設やハザードマップなどの情報が得られる
ビズアナオーナーは、賃貸経営の最新情報を知りたい不動産オーナー様におすすめです!