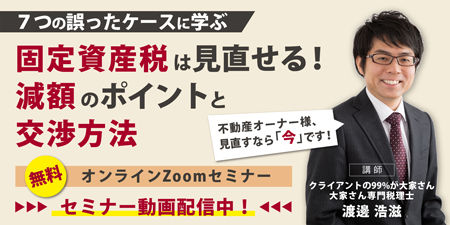アパート経営を法人化したい!具体的なタイミングやデメリットを解説
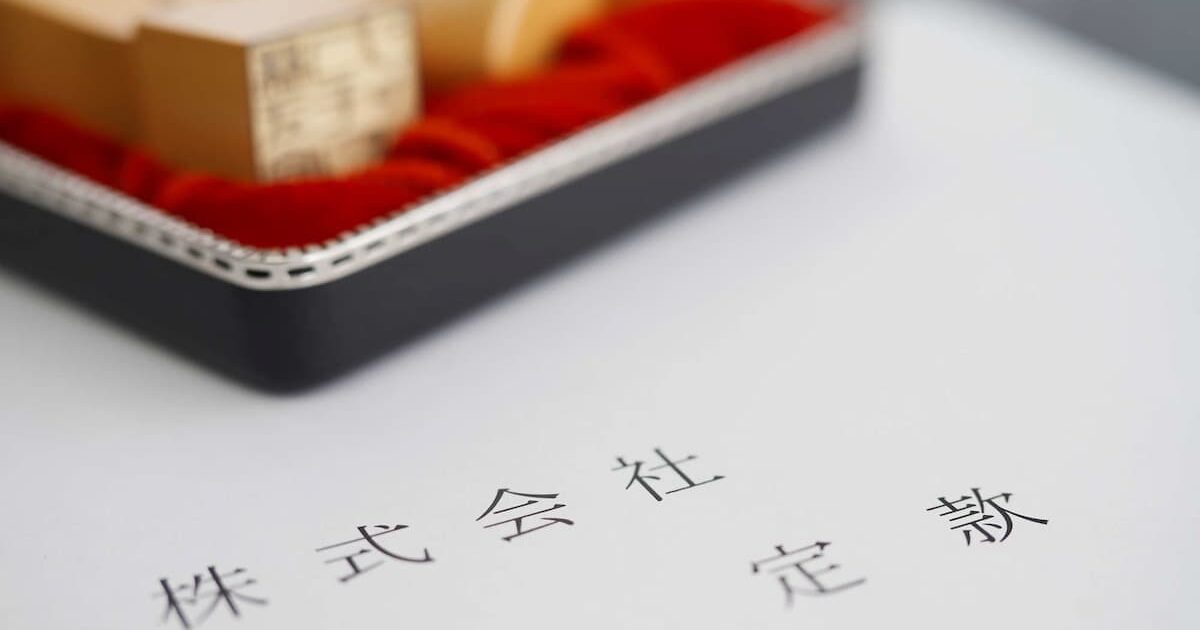
アパート経営をスタートさせ安定した収入が継続できるようになると、法人化に対する意識が生まれてきます。
法人化すると、いままでのアパート経営と具体的に何が変わるのでしょうか。経営や収支の状況によっては、メリットよりもデメリットのほうが大きいかもしれません。
アパート経営の法人化による影響を理解し、適切なタイミングを検討しましょう。
アパート経営の法人化による影響
法人化とは、個人事業ではなく会社を設立してアパート経営を行うことです。法人化により、アパート経営にはどのような影響が生じるのかをみていきます。
個人事業主と法人の違い
アパート経営を個人事業で行うか法人化して行うかで、経営の内容に大きな違いはありません。違いがあるのは、税金です。
個人で行うアパート経営による所得は、不動産所得といいます。個人の不動産所得に対して、ほかの所得と合わせて所得税が課税されます。
それに対して、法人が行うアパート経営による所得は法人所得です。こちらもアパート経営以外の事業による所得も合わせたトータルの所得に対し、税金が課税されます。これを、法人税といいます。
| 個人事業主 | 法人 | |
|---|---|---|
| 所得 | 不動産所得 | 法人所得 |
| 所得に対して課せられる税金 | 所得税 | 法人税 |
所得税と法人税は課税の方法が違い、これが税金面での違いを生んでいます。
所得税は累進課税方式といい、所得が高いほど税率が高くなります。しかし、法人税は累進課税方式ではなく一定の税率です。
そのため、法人化するべきかしないほうがよいかは、所得の額によって異なるといえます。
法人化のメリット
法人化すると、主に税金面に関するメリットがあり、収益性の高い経営が可能になります。その具体的な内容を解説します。
税金を抑えられる
個人の場合、所得が多くなるほど税率が高くなる累進課税方式です。具体的には、所得金額によって、以下のように税率が決められています。
| 所得金額 | 所得税率 | 控除額(円) |
|---|---|---|
| 1,000~194万9,000円 | 5% | 0 |
| 195万~329万9,000円 | 10% | 9万7,500 |
| 330万~694万9,000円 | 20% | 42万7,500 |
| 695万~899万9,000円 | 23% | 63万6,000 |
| 900万~1,799万9,000円 | 33% | 153万6,000 |
| 1,800万~3,999万9,000円 | 40% | 279万6,000 |
| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000 |
参考:国税庁「No.2260 所得税の税率」
ここでは例として、個人の所得金額が500万円と1,000万円の場合の税額をそれぞれ計算してみます。
不動産所得が500万円の場合の税額=500万円 × 20%-42万7,500円=57万2,500円
不動産所得が1,000万円の場合の税額=1000万円 × 33%-153万6,000円=176万4,000円
つまり、所得金額に対して500万円の場合は11.45%、1,000万円の場合は17.64%の税金がかかります。
なお、説明の都合上、東日本大震災からの復興のために課税される復興特別所得税は加味していません。
法人の場合は、累進課税方式ではありませんが、資本金の額と所得金額によって区分があります。アパート経営などの法人で資本金が1億円以下の場合、所得金額が800万円以下の部分は15%、800万円を超える部分は23.2%の税率です。
法人税の税率は、普通法人、一般社団法人等又は人格のない社団等については23.2%(資本金1億円以下の普通法人、一般社団法人等又は人格のない社団等の所得の金額のうち年800万円以下の金額については15%)とされています。
法人の所得金額が、500万円と1,000万円の場合の税額をそれぞれ計算してみます。
不動産所得が500万円の場合の税額=500万円 × 15%=75万円
不動産所得が1,000万円の場合の税額=800万円 × 15%-200万円 × 23.2%=166万4,000円
つまり、所得金額に対して500万円の場合は15%、1,000万円の場合は16.6%の税金がかかります。なお、こちらも説明の都合上、復興特別所得税は考慮していません。
個人の場合と法人の場合の計算結果を以下にまとめました。
| 所得金額(円) | 税額(円) | 所得金額に対する税額の割合(%) | |
|---|---|---|---|
| 個人事業主 | 500万 | 57万2,500 | 11.45 |
| 1,000万 | 176万4,000 | 17.64 | |
| 法人 | 500万 | 75万 | 15 |
| 1,000万 | 166万4,000 | 16.6 |
※ただし復興特別所得税を考慮しない場合
この結果から、所得金額が500万円程度であれば個人事業のほうが税率は低くなり、1,000万円を超えると法人のほうが、税率が低くなることがわかります。
つまり、不動産所得が1,000万円に近づいてくると法人化をするメリットがあるといえるでしょう。個人と法人の税率のどちらが高いかは、所得金額が約800万円で逆転します。
関連記事:賃貸経営の家賃収入に消費税はかかる?税金を抑える方法も紹介
相続対策になる
また、アパートなどの不動産を法人所有にすると、相続対策になります。
個人事業のまま相続が発生すると、アパートの土地と建物は相続人が相続します。相続税は原則的に現金納付のため、相続人は納税目的で不動産を売却しなければならないケースがあります。
しかし法人化するということは、不動産を会社に売却するということです。つまり個人事業主は会社に売却した代金を相続税の納税資金として確保できます。
また、複数の相続人がいる場合、アパートを分割できず遺産分割が難しくなるケースがあります。しかし法人化すると、不動産の相続ではなく株式の分割相続になるため、簡単に遺産分割ができます。
赤字によるダメージを低減できる
アパート経営で赤字が出た場合、赤字分を翌年以降に繰り越せます。
アパート経営で行う確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。白色申告の場合は繰り越しができませんが、青色申告の場合は個人で3年間、法人では10年間、赤字分の繰り越しが可能です。
法人は、赤字によるダメージを長期間にわたって穴埋めできます。そのため、キャッシュフローの改善効果などを行い、事業の維持がしやすくなります。
大きな赤字は経営破たんや、アパートの売却といった予期せぬ決断を迫られるリスクがあります。法人化はそのようなリスクを軽減するメリットがあります。
法人化のデメリット
法人化にはメリットが多いですが、デメリットもあるためよく理解してから検討しましょう。
アパート売却時の税率が高い
法人が不動産を売却して得た利益は、譲渡所得ではなく法人所得になります。
個人の場合は、不動産の保有期間により長期譲渡と短期譲渡に分けられ、税率が変わります。法人の場合は、保有期間による課税の方法に違いはありません。
- 長期譲渡
- 不動産の保有期間が売却した年の1月1日時点で5年を超える
- 短期譲渡
- 不動産の保有期間が売却した年の1月1日時点で5年以下
復興特別所得税は考慮しない場合、長期譲渡に該当する不動産を個人が売却すると、不動産売却の税率は15%です。しかし、法人の場合は所得金額が800万円を超えると23.2%となり、個人よりも法人のほうが所得に対する税金は高くなります。
経営上の負担が大きい
法人化すると、経営上で以下の負担が発生します。
- 事務経費の負担
- 赤字の繰り越しを行うには青色申告が必要なため、会計事務の負担は白色申告に比べて大きくなる
- 税金の負担
- 法人は仮に赤字であっても法人住民税の均等割を納税する必要がある
- 社会保険の加入
- 個人事業の場合は社会保険加入が免除されるケースがあるが、法人になると社長ひとりの会社であっても社会保険加入が原則
なお、社会保険には大きく分けて次の4つの種類があります。
- 健康(介護)保険
- 厚生年金
- 労災保険
- 雇用保険
いずれも保険料という形で、会社が支払う必要のある経費です。
アパート経営を法人化するタイミング
法人化は、一定の収入と後述する所得がなければ法人化しても意味がありません。また、法人化には個人から会社へのアパートの譲渡が伴うので、時期や譲受資金の検討も必要です。
ここでは、アパート経営を法人化するのに適したタイミングを具体的に紹介します。反対に、当てはまらない場合は法人化を見送る判断も必要です。
所得が継続して増加しているとき
アパートからの収入が安定して増加し、経費を除いた所得金額が800万~1,000万円を見込めるころが法人化のタイミングです。
所得金額が800万円未満であれば個人事業のほうが所得税は安くすむため、法人化のメリットはありません。
また、1年間のみ入居率が高く、翌年には所得が800万円未満となる見通しの場合など、所得が継続して800万円を超えない状態であれば、法人化を急ぐ必要はないといえるでしょう。
アパートの所有期間が5年を経過しているとき
個人事業から法人事業に移行するには、アパートの土地と建物を会社に譲渡します。
譲渡により譲渡所得があれば個人に対し税金が課され、短期譲渡の場合は高い税率になります。そのため、譲渡所得の有無と、アパート取得からの所有期間が5年を経過しているかの確認が必要です。
また、譲渡所得が発生しない金額で譲渡した場合、譲渡時点での市場価格や評価額と比較して贈与とみなされる場合もあります。譲渡時期により税負担が多くなる場合があるので注意が必要です。
譲受資金が確保できているとき
アパートの土地と建物を個人から会社へ譲渡するには、会社に資金が必要です。ほとんどの場合で、会社が保有する現預金だけでは資金が足りず、金融機関からの借入が必要になるでしょう。
一般的に、設立したての法人は事業の実績もないため、不動産の取得資金として多額の融資を受けることはかなり難しいです。
個人事業の時点における経営状態がよく、代表者本人の人間性や信頼感などによっては可能な場合もあります。しかし、アパートを譲受できる資金のめどが立たなくては法人化が難しいといえるでしょう。
アパート経営を法人化するときの注意点
法人化にはさまざまな手続きが必要です。自身で手続きを進められますが、司法書士や社会保険労務士に依頼するケースもあります。
ここではアパート経営を法人化する際に注意したいポイントを紹介します。
手続き漏れがないようにする
アパート経営を法人化するには、次の手順で進めていきます。
- アパートの土地と建物の所有形態を決める
- 会社の形態を決め印鑑を作成
- 定款の作成と認証(認証は株式会社の場合)
- 資本金の払い込み
- 会社の設立登記
- 社会保険関係・税務関係の手続き
それぞれの手続きに漏れがないように気をつけましょう。
アパートの土地と建物の所有形態を決める
アパートの土地と建物は両方とも法人名義にするか、建物のみを法人名義にするかのどちらかです。
建物のみを法人所有とした場合、アパート経営を行う会社は土地の所有者である個人との間で貸借関係が生まれます。
貸借関係には、以下2つのケースがあります。
- 賃貸借
- 使用貸借
賃貸借の場合は、借地権認定課税を回避するために「土地の無償返還に関する届出」が必要です。
使用貸借の場合は、土地を将来相続することになったとき、貸宅地としての相続税評価額減額や小規模宅地等の特例が適用できません。そのため、相続税の節税ができないことに注意が必要です。
会社の形態を決め印鑑を作成
設立する会社の形態には次の4つの選択肢があります。
- 株式会社
- 合同会社
- 合名会社
- 合資会社
合名会社と合資会社の一部は、会社が倒産した場合に負債の全額を債権者に支払う無限責任を負います。そのため、不動産賃貸事業を行う会社の形態は、限度が決まっている有限責任である、株式会社または合同会社がよいでしょう。
会社設立にかかる費用や手間は合同会社のほうが安いため、アパート経営では合同会社を設立するケースが多くみられます。
株式会社と合同会社の会社設立に必要な費用は、それぞれ以下のとおりです。
| 株式会社 | 合同会社 | ||
|---|---|---|---|
| 定款印紙代 | 4万円 電子定款はなし |
4万円 電子定款はなし |
|
| 定款認証 | 資本金:100万円未満 | 3万円 | なし |
| 資本金:100万円以上300万円未満 | 4万円 | ||
| 資本金:300万円以上 | 5万円 | ||
| 定款謄本交付料 | 1枚250円 | なし | |
| 登録免許税 | 15万円または資本金の0.7% | 6万円または資本金の0.7% | |
印鑑は最低限、会社の実印としての代表印を1個作成する必要があります。それ以外に必要に応じて角印・銀行印を作成します。代表印については、後日登記時に印鑑届書を法務局に提出します。
定款の作成と認証(認証は株式会社の場合)
株式会社の場合は、定款認証が必要です。定款認証とは、会社の規則などを記載された書類が正当な手続きで作成された証明のことです。
合同会社の場合は定款認証が不要なので、会社設立登記申請の準備ができたら払い込みをします。
資本金の払い込み
資本金の払い込みは所定の銀行口座にします。所定の銀行口座とは、会社設立発起人の口座です。発起人あるいは発起人代表者が使用している個人口座でかまいません。
発起人が複数の場合は、それぞれが会社設立発起人の口座に振り込みします。つまり、会社設立に関する発起人会議事録に記載された、発起人の氏名と資本金額が明確にわかるように、振り込みによる払い込みが必要です。
発起人がひとりの場合は、振り込みは行わず、資本金額と一致する金額を預け入れします。すでに銀行口座に資本金分の残高がある場合は、一度資本金額分を引き出してから同額分を預け入れし、資本金の払い込みであることをわかるようにします。
払い込みを行ったら、資本金の払込証明書を次の手順で作成します。
- 銀行口座預金通帳の表紙と裏表紙、そして払い込みされたページの分をコピーする。インターネットバンキングの場合は必要な情報が記載された部分をプリントアウトする。
- 払込証明書には次の必要な項目を記載し、証明書の左上と代表取締役氏名の右に「代表者印」を押印。
- 払込証明書をまとめる。
なお、払込証明書に必要な項目は、以下のとおりです。
- 払込総金額
- 払い込んだ株数
- 1株当たりの払込金額
- 払い込んだ日付
- 会社の本店所在地
- 会社名
- 代表取締役の氏名
また、払込証明書は、以下の順番でまとめます。
- 払込証明書
- 通帳表紙コピー
- 通帳裏表紙コピー
- 通帳払込ページのコピー
- まとめたあとに各ページの境に代表印を押印
会社の設立登記
会社の設立登記は一般的には司法書士に依頼することが多いですが、自分でも法務局に赴き申請できます。
必要な書類は次のとおりです。
- 登記申請書
- 登録免許税納付用台紙
- 定款の謄本
- 発起人会議事録
- 代表取締役の就任承諾書
- 監査役の就任承諾書(監査役を設置した場合)
- 取締役の印鑑証明書
- 資本金の払込証明書
- 印鑑届書
- 登記すべき事項を記載した書面または保存したCD-R
社会保険関係・税務関係の手続き
法人設立をすると、従業員がいない社長ひとりの会社であっても、社会保険関係の手続きが必要です。また税務署関係にも手続きが必要です。
労災保険と雇用保険は従業員を雇用するまでは不要ですが、健康(介護)保険と厚生年金の手続きは必ず行います。
手続きを行う機関と必要書類は以下のとおりです。
| 所管機関 | 必要書類 | |
|---|---|---|
| 健康(介護)保険 | 社会保険事務所 |
|
| 厚生年金 | 社会保険事務所 |
|
| 労災・雇用保険 | 労働基準監督署 |
|
現在の収支を正確に判断する
アパート経営を個人事業から法人事業に変える場合にまず検討したいのは、変えるタイミングです。
そしてもっとも大きなポイントは、所得が800万円を超え、その状態が今後も継続するかどうかの判断です。
その際、所得であり、収入ではないことに注意しましょう。所得は収入から必要経費を差し引いたものです。アパートローンの返済がある場合は、必要経費に算入できるのは返済金ではなく利息分だけです。
ほかにも、所得を求めるには減価償却費の算出も必要です。
このようにアパートのオーナーは現在の収支を正確に判断する必要がありますが、リアルタイムでいつでも明確にすることは難しいものです。
そこで活用したいのは、収支管理ツールです。無料で会員登録ができるビズアナオーナーであれば、毎月の収支情報を送るだけでアパート経営の収支や稼働状況を手軽に管理できます。
法人化するか悩んでいる方はまず、ビズアナオーナーを活用して収支を正確に把握することから始めましょう。
アパート経営の法人化を検討している方におすすめ!無料の「ビズアナオーナー」
ビズアナオーナーは、不動産オーナー様のアパート経営をトータルサポートする会員制のWEBサービスです。
所有する物件の収支・稼働状況をカンタンに可視化できる収支・稼働管理機能(無料)をメインとし、不動産関連セミナーへの無料招待、AI 賃料査定・統計調査レポートサービスの他、アパート経営に役立つオプションメニューを多数ラインナップ!
【めんどうな入力は一切不要のラクラク収支管理!】
ビズアナオーナー会員になると、次のようなメリットがあります。
- 収支報告書を送るだけ!しかも月額利用料&登録料0円で収支管理ができる
- アパート経営のお悩みを専門家に相談できるセミナーや勉強会にご招待
- 個人がオーダーできるのはビズアナ会員だけ!AI賃料査定レポートが受け取れる
ビズアナオーナーは、毎月の収支管理を無料で自動化したい不動産オーナー様におすすめです!