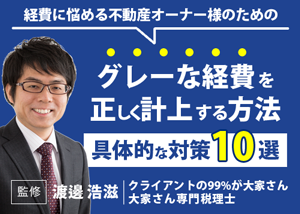自然災害時に大家の責任はどこまで?取るべき対応やリスクへの備えも解説

賃貸物件が自然災害によって被害を受けた場合、原則として大家の責任で修繕を行うべきとされています。
一方、室内にある家財や人的な被害については、一般的に入居者自身の責任で対応しますが、場合によっては例外もあります。
自然災害時に大家が取るべき具体的な対応や、自然災害リスクへの備えを紹介します。
自然災害による損害は大家の責任?
自然災害による損害の種類別に、責任の所在を確認しましょう。
原則、建物の被害は大家の責任
自然災害によって賃貸物件の建物に被害が出た場合、その修繕は誰が行うべきでしょうか。原則として、これは大家の責任で行うこととされています。
民法で、賃貸人(大家など)は、「賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」(民法第606条)と定められています。つまり、建物が被害を受けて、住む人が困るような状態になった場合、速やかにそれを回復させる必要があります。
また、住めない状態になった場合、その期間の家賃の減額請求に応じなければならないこともあります。
ただし、大家の責任が問われるのは、損害が不可抗力である場合です。
通常、台風などの際は、雨戸を閉めるなどの対策を行います。入居者がこれらを怠ったために生じた被害については、修繕義務を負わなくてよい可能性があります。
また、大家の責任は「住める物件を貸す」ことであって、入居者の生活そのものを保証することではありません。そのため、「部屋が住めない状態なので、その間のホテル代を負担してほしい」などといった要求は、必ずしも応じる必要はありません。
なお、賃貸借契約で、修繕義務を入居者に負わせる特約を設けるケースもあります。しかし、この場合の修繕は日常的なものを指し、災害による被害などの責任を負わせるのは現実的でないため、特約によって大家の修繕義務を免れるのは難しいでしょう。
室内にある家財の被害は入居者の責任で対応する
室内にある入居者の家財が自然災害で被害を受けた場合、入居者自身の責任で対応するのが一般的です。入居者が加入する家財保険(火災保険の一部)で補償を受けるのが適切でしょう。
ただし、大家に過失があって被害が出たとなると話は変わってきます。主に、修繕義務違反が過失にあたります。
たとえば、屋根が老朽化しているのを大家が放置しており、大雨の際に雨漏りが生じ、入居者の家財が被害を受けた場合、大家の責任が問われることが考えられます。
関連記事:施設賠償責任保険を大家におすすめする理由は?保険料や注意点も紹介
人的被害は基本的に責任を問われないが、例外も
人的被害についても、考え方は家財の被害と同様です。つまり、基本的には、大家に責任はなく、入居者が自分自身で対処すべきと考えられます。
例外は、大家が果たすべき責任を果たしていなかったために被害が生じたとみなされる場合です。
代表的なものは、耐震性能や火災対策の不足が挙げられます。たとえば、火災報知器の故障を修理せずに放置しており、火災発生時に入居者が逃げ遅れた場合などがあてはまります。
人的被害の責任を問われると、多額の賠償責任となることも珍しくありません。人の生命に関わる内容は、しっかりと対策を講じておきましょう。
自然災害時に大家がすべき対応
法的な責任や義務の有無は別として、自然災害が発生したときに、大家が行うべき対応を整理します。
入居者の安否確認
まずは、入居者の安否確認を優先させます。
その後のさまざまな対応をスムーズに行うためにも、入居者の状態を確認し、もし避難などが必要な状況であれば、その後も連絡が取れるようにしておくべきです。
建物と設備の確認
物件そのものにどの程度の被害が出たのかを確認します。自身の安全に配慮したうえで、可能な限り、現地で確認をしたほうがよいでしょう。見た目だけでなく、設備などが実際に問題なく機能するかも確認します。
建物や設備の確認には、大きく以下3つの意味があります。
- 今後の修繕の必要性を見極める
- 保険で補償を受ける際の情報収集
- 入居者の生活への影響を確認する
修繕は大家の義務のため、今後、修繕が必要かを見極めることは重要です。
また、物件が自然災害により受けた被害は、加入している保険で補償できるケースが多いです。この手続き時に、被害状況を保険会社に報告する必要があります。
保険会社の調査などもありますが、できるだけ被害直後の様子を写真に撮るなどして残しておくと、スムーズに手続きができます。
そして、入居者の生活への影響を確認して、サポートやケアが必要かを検討します。
修繕の対応
建物や設備に修繕が必要であれば、その手配を行います。これは大家の義務であり、主要な災害対応といえるため、できるだけ速やかに対応しましょう。
必要に応じて、入居者に一時的に物件から離れてもらうなどの対応をお願いする場合もあります。
なお、修繕が大家の義務であると同時に、この修繕行為を入居者は拒めないと決まっています。そのため、修繕に必要で出された指示に入居者は従う必要がありますが、スムーズに事を運ぶためには、コミュニケーションに気を配るべきでしょう。
入居者へのサポート
そのほか、入居者へのサポートを実施するかを検討しましょう。たとえば、仮住まいの手配といった、代替物の提供などです。
法律上は、そこまでの義務は大家にはないため、行わなくても問題はありません。しかし、親身になってサポートをすれば、その後の退去率などに影響するかもしれません。ムリのない範囲で行っておくと、結果的に不動産経営上の利益にもつながります。
自然災害リスクに備える
実際に自然災害が起こる前に、対策をしておきましょう。効果的な方法を紹介します。
公的な制度について情報収集しておく
大規模な自然災害の被害を受けたとき、国や地方公共団体(自治体)による公的な支援制度を利用できる可能性があります。
たとえば、「被災者生活再建支援制度」は、自然災害によって住居に多大なる被害を受けた世帯に対し、支援金を支給する制度です。
地方公共団体ごとに独自の支援制度が用意されていることもあります。こうした情報を事前に収集しておけば、いざというときに、被災した入居者に速やかに情報提供ができます。
保険に加入する
火災保険などの保険への加入は、重要な対策です。
自然災害のように、起こる確率は少なくても、いざ起こってしまったときの損害が大きいリスクは、保険を活用して備えるのが最も適しています。
数多くの保険会社が、さまざまな保険商品を販売しているため、物件とリスクに見合った保険に加入しておきましょう。
保険は大切ですが、必要のない補償を厚くしても保険料がかさむだけです。たとえば、高層階のワンルームなら、水害への備えはさほど気を使わなくてもよいかもしれません。ジャストサイズな補償内容にしておくと、保険料も抑えられます。
迷うようであれば、保険に詳しいファイナンシャルプランナーや、さまざまな事例を見てきている不動産会社の担当者など、専門家にアドバイスを求めてみましょう。
また、保険は、実際に被害にあったとき、適切に手続きを行って保険金請求を行う必要があります。そういった実務面でも、専門家のサポートが得られれば心強いでしょう。
関連記事:賃貸オーナーにおすすめの保険とは。火災保険の特約や保険料の相場も紹介。
物件周辺の環境を把握しておく
物件周辺の地域について、災害リスクに関する情報を集めておきましょう。
近年は、公的機関から公表されている地域のハザードマップなどから、災害リスクを知ることができます。
河川が近い地域では「洪水浸水想定区域図」、山が近い場所では「土砂災害警戒区域」の情報を確認します。台風や大雨の際に、被害が発生するリスクがどの程度あるのか、把握しておくとよいでしょう。これは、保険に加入する際に補償内容を検討する参考にもなります。
また、大規模な災害が起きたときに、地方公共団体が避難場所として指定する場所はどこなのかも事前に確認しておきます。必要に応じて、入居者に情報提供などを行っておくこともおすすめです。
大家は、数多くある情報を取捨選択する能力が求められますが、判断に悩む方もいるでしょう。
不動産経営での収支管理ができるWebサービス「ビズアナオーナー」のオプションメニュー「スマサテ」では、査定住所周辺のハザードマップをレポートとして受け取れます。また、それ以外にもAI賃料査定や統計調査のレポートもまとめて入手できるため、自然災害リスクだけでなく、空室リスクの対策としても有効です。
ビズアナオーナーは登録無料ですので、まずは登録してみて、利用を検討してみましょう。
【ハザードマップ・賃料査定などのレポートも入手可能!】
- 物件周辺のハザードマップや商業施設・教育施設などの情報が得られる
- 物件周辺エリアの家賃相場や将来の賃料予測が分かる
- 不動産オーナーがスマサテのレポートを受け取れるのはビズアナ会員だけ!
ビズアナオーナーは、リサーチデータを上手に活用してリスクに備えたい不動産オーナー様におすすめです!
\ビズアナ会員なら「スマサテ」レポートがお得に!/