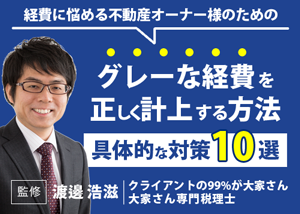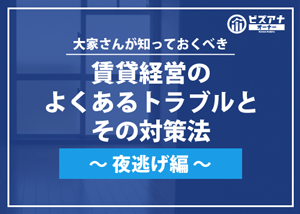事故物件になったら大家はどう対処する?部屋の清掃方法や告知義務とは。

賃貸経営をする中で、人が亡くなるほどの事件や事故が起こると、その物件は「事故物件」として取り扱われます。事故物件に対しては強い抵抗感を持つ人が多く、きちんと対応しなければ、長期間の空室になったり、大幅な家賃減額などが発生することもあります。
もし自ら所有する不動産が事故物件となってしまった時、大家はどのように対処すべきなのでしょうか。
今回は、2021年10月に発表された事故物件の告知義務に関するガイドラインも紹介しながら、事故物件への対処方法を紹介します。
事故物件の基礎知識
まずは、事故物件についての基本的な知識を確認しましょう。
事故物件とは
一般的に事故物件とは、その不動産の専有部分、あるいは共有部分において入居者が亡くなった物件のことを指します。
亡くなった理由により「殺人」「自殺」「自然死」の3つに分けられます。殺人や自殺については、特に告知することを強く義務づけられています。
事故物件に告知義務があるのは、賃貸・購入する側が強い抵抗を感じるためです。これを、「心理的瑕疵」と言います。大家や不動産仲介会社は物件の瑕疵について、物理的・心理的問わず告知する義務があります。
最近では、高齢者の増加や新型コロナウイルス流行により、家族同士の交流が減少しています。それに伴い、孤独死の事例が増えています。どのような物件でも、発生する可能性がある問題です。
大家には告知義務がある
もともと事故物件に関する告知義務は、明確な指標がありませんでした。しかし、令和3年10月8日、国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を発表しました。
それによると、賃貸借取引において事故物件の事実を告げなくてもよい場合として、以下3点が挙げられています。
-
- 物件の損害リ取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)
- 取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死が発生し、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)から概ね3年間が経過した後
- 取引の対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死
つまり、老衰や病死などの自然死については、告知が不要です。また、専有部や通常使用する共用部で殺人や自殺などが起こった場合においても、発生から3年を過ぎれば告知が不要です。
ただし、これは原則であり、以下のような場合は告知の必要があるともされています。
-
- 買主・借主から事案の有無について問われた場合
- 社会的影響の大きさから、買主・借主において把握しておくべき特段の事情がある場合
告知が必要なほどの事故物件になった場合、新たな入居者を見つけるハードルが高まります。詳しい対処法については、後ほど解説します。
事故物件処理には費用がかかる
事故物件の処理には、特殊清掃やリフォームの費用が発生します。
特殊清掃にかかる費用は、ワンルームで約10万円~、3LDKで約30万~80万円が目安です。
リフォームにかかる費用は、素材などにより多少の差異がありますが、次のとおりです。
リフォームの種類費用相場(円)壁紙(クロス)の張り替え約1,000〜2,000/㎡フローリングの張り替え約3,000〜4,000/㎡クッションフロアの張り替え約2,000〜4,500/㎡トイレの便器交換+内装リフォーム約200,000〜300,000風呂場(ユニット入れ換え)約900,000〜1, 000,000
これ以外にも、新しい賃借人が現れるまでの家賃の逸失も発生するため、大家は素早い対応が求められます。
事故物件に対する大家の対処方法
事故物件発生時の大家の対処方法を、手順を追って具体的に説明します。
まずは警察と遺族に連絡を
遺体を発見したら、まずは警察に連絡します。
警察官が物件内を実況見分し、事件性の有無の判断や、身元の確認を行います。ご家族の連絡先が分かる場合は、ご家族にも連絡しましょう。
物件内の清掃
警察による立ち入り制限が解除された後は、室内の片付けを行います。
遺体の状態が悪化している場合もあるため、なるべく専門の業者に依頼し、特殊清掃を行ってもらいましょう。
賃借人が亡くなった後、不動産の賃貸借契約による各種権利や義務、室内の遺品はすべて相続人へ相続されます。そのため、遺品の整理は、相続人と相談しながら進める必要があります。
相続人の方は、葬儀などで対応が厳しい場合もあります。スムーズに事を運ぶためには、費用を敷金から差し引く旨のみ、相続人に事前了承を得ておきましょう。その上で、特殊清掃などの発注は、自ら手配するのも良いかもしれません。
なお、もし相続人がいない場合は、清掃や遺品整理作業は、大家の負担で行います。
相続人に対して解約手続きと家賃・原状回復費用の精算
物件内の清掃が完了した後は、相続人に対して賃貸契約の解約手続きを行います。
物件の賃貸借契約は、権利関係を相続した相続人との間で継続しています。そのため、大家は相続人に対し、部屋を明け渡すまでの家賃や原状回復費用などを請求できます。
事前に預かっている敷金があれば、それらの費用を差し引き、物件引き渡しを受けた後、残額を返還しましょう。
なお、借主が自殺により亡くなった場合、大家は被害を被った側として、相続人に対して賠償請求できる可能性があります。たとえば、清掃費用や賃料収入減少などにかかる各種損害などがあります。
しかし、遺族との間で係争となり、物件が不良在庫になってしまうおそれもあります。
遺族側の協力があることで、原状回復などの手続きをスムーズに行うことができます。遺族の心中に配慮しながら、適切な対応を心がけましょう。
内装のリフォーム
特殊清掃が済み、物件の引き渡しを受けた後は、内装関係のリフォームを行います。
この際、工事業者に対しては、あらかじめ事故物件であることは伝えておきましょう。
もし、リフォーム工事が始まってから、近隣住民などから事故物件である旨が業者に伝わった場合、契約違反などのトラブルになる可能性があります。
リフォームが済み、物件がきれいな状態に戻れば、客付けを再開できます。
事故物件後の客付け
事故物件になった後、最も難しいのが客付けです。
前述したとおり、自殺や殺人による事故物件は3年間の告知義務があります。
その3年間、家賃収入が途絶えてしまうことを避けるため、以下の対応が考えられます。
家賃・初期費用を下げる
家賃や初期費用を一時的に下げることで、「事故物件であっても安く住めるならよい」と考える人に入居してもらうことが可能です。
不動産仲介業者と相談しながら、競合物件に打ち勝つことができるよう、以下のような条件を設定しましょう。
-
- 家賃を相場より安い価格にする
- 敷金・礼金を無料にする
- フリーレント(家賃1~3カ月無料)を導入する
なお、こういった減額措置は一時的なものです。告知義務がなくなった後は、価格を元に戻すことを忘れないようにしましょう。
リフォームして付加価値を付ける
通常より、付加価値が付くようなリフォームをするのもおすすめです。
借主のライフスタイルに寄り添ったリフォーム事例として、以下の例が挙げられます。
-
- 光回線引き込みなど、インターネット環境の整備
- 食器洗い機などの設備を導入
- 段差を取り除くなどのバリアフリー工事
追加の費用が発生しますが、付加価値の付いた部屋は告知義務が終了した後、さらに高い家賃で貸すことができる可能性もあります。
発生する前なら孤独死保険への加入を検討する
事故物件になってしまうと、清掃や工事の費用がかかるだけではありません。その後も、家賃が減少するなどの損害が発生します。
こういったリスクに備える商品として、「孤独死保険」があります。
孤独死保険とは、所有する物件で発生した入居者の死亡事故に対して、各種補償を受けられる商品です。遺品整理費用や原状回復費用、事故後の家賃損失が含まれています。
保険料支払いの分、不動産の利回りは低下するので、一概におすすめとは言えません。しかし、事故物件のリスクが高い高齢者が多く入居している場合などは、加入を検討してもよいでしょう。
高齢者が増加している日本において、事故物件とどう向き合うかは、大家にとって継続的な課題です。
告知義務のガイドラインが整備されたことにより、自然死であれば早期に発見ができれば、告知をせず新たな客付けを行うことができるようになりました。
事故物件となるリスクは、各種見守りサービスや入居者との連絡体制を整えることでも回避できます。引き続き、情報収集を怠らないようにしましょう。
【賃貸経営に役立つ無料セミナーを定期開催!】
- 賃貸経営のお悩みを専門家に相談できるセミナーや勉強会にご招待
- いつでも無料で過去のセミナー動画を視聴できるのはビズアナ会員だけ!
- さらに不動産マーケット情報などビズアナ会員だけが利用できる賃貸経営に役立つメニューをラインナップ
ビズアナオーナーは、賃貸経営のお困りごとやお悩みの解決策を知りたい不動産オーナー様におすすめです!