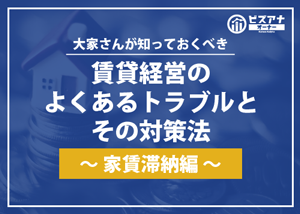【2024年最新】賃貸経営の入居者トラブルまとめ!適切な対処方法も
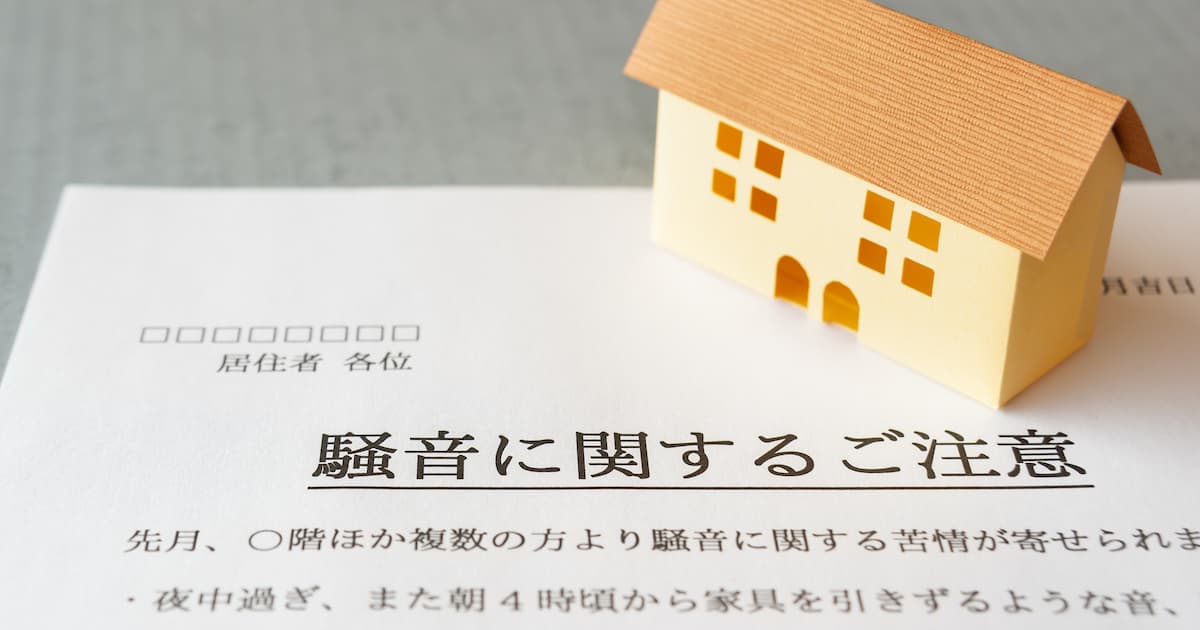
賃貸経営において、入居者トラブルは避けて通れない課題です。賃貸経営のトラブルとして、原状回復問題や修繕に関するトラブル、管理会社の不適切な管理、契約解除時の騒音問題などが挙げられます。
これらのトラブルに適切に対応することは、賃貸経営を円滑に行うために不可欠です。入居者トラブルに対処するための情報や、消費者センターなどの相談先の情報を得ることが、賃貸経営においてとても重要です。また、これらの問題に適切に対処するには、専門的な知識と経験が必要です。
入居者トラブルの対処法と防止策について具体的なアドバイスを提供します。
賃貸アパートで最近多い入居者トラブル
賃貸アパート経営で遭遇する入居者トラブルは多岐にわたり、これらに効果的に対処し予防する方法はアパートのオーナーにとって非常に重要です。賃貸アパート経営で遭遇する主なトラブルは次の通りです。
- 原状回復や敷金礼金のトラブル
- 修繕・改善のトラブル
- 管理会社の管理状況が悪いなどのトラブル
- 契約解除のトラブル
以下にそれぞれ詳しく解説していきます。
原状回復や敷金礼金のトラブル
「独立行政法人国民生活センター」によると、「賃貸住宅」に関する相談のうち、「敷金ならびに原状回復トラブル」に関する相談が約3割を占めています。
オーナーと借主の敷金に関するトラブルは、法律やガイドラインを軽視した契約などにより発生します。
敷金は退去時に汚れや傷などを初めの状態に回復させる「原状回復費用」を差し引いて返還されますが、原状回復の範囲を明確に定めないことによるトラブルが多発したため、2020年の法改正で「経年劣化」や「通常の生活でできる消耗」は「原状回復費用」として差し引けなくなりました。
この原則を守ることが、トラブルを避けるためには重要です。
敷金の返還は、原状回復費用を引いた後の残額が基本ですが、費用が敷金を超える場合、追加請求することもあり得ます。通常の郵便などで請求しても支払ってもらえない場合は、送付日が証明される内容証明郵便で請求するのも一つの手段です。
内容証明郵便は訴訟になった場合、訴訟に先立って請求した証拠となります。
ただし、その内容も証拠として残るため不利に働く可能性もあります。内容証明郵便を送る段階から弁護士に相談するのがおすすめです。
関連記事:敷金償却に関する特約とは?原状回復をめぐるトラブルを避けるための注意点
原状回復における敷金返還問題の具体的なケース
日ざしによる日焼けで退色した壁紙の張り替え費用を「原状回復の義務がある」と、敷金から差し引いたところ「経年変化だ」と入居者が反論したなどのケースなどが事例としてあります。
入居者が通常通りに物件を使用していれば、敷金は原則全額返還されます。家賃の滞納や物件の故意の損傷の場合は、敷金からその分を差し引くことが可能です。
ただし、単に入居期間が長いからと言って返金する敷金を自動的に減額できるわけではありません。経年による劣化は賃借人に請求できないため、アパートオーナーは敷金を返さなければなりません。
具体的にどのようなケースが「経年変化」や「通常損耗」に該当するのかは、国土交通省が公表するガイドラインで確認できます。
敷金や原状回復の費用をめぐるトラブルが発生した場合、まずは賃貸契約書の条項を確認します。他の法令に反しないなら当事者同士の契約が最優先されるため、契約書に明記した原状回復義務についてのルールを確認しましょう。
契約書に明記がない場合には、国土交通省のガイドラインを参考にしましょう。
修繕・改善のトラブル
賃貸物件で発生する修繕・改善のトラブルは、貸主と借主間で頻繁に発生します。
借主の故意や過失による損害があった場合、貸主は修繕義務を負いません。借主の故意や過失には、同居している借主の家族の故意や過失も含まれます。
逆に、物件の自然な老朽化や災害による損害で、借主に責任がない場合は、貸主が修繕を行う必要があります。貸主が修繕義務を負うのは次の条件に当てはまる場合です。
- 契約上、貸主が提供すべき設備であること
- 借主に壊れたり汚したりした原因がないこと
- 壊れたり汚れたりしたことにより、建物の利用に支障をきたすこと
- 修繕が可能であること
ただし、物理的もしくは経済的に非現実的な修繕は要求できません。
また、賃貸借契約書に修繕特約の記載をする場合、ふすまの貼り替えなどの「一定範囲の小修繕」のための費用については、貸主の修繕義務は免除できると考えられています。
しかし、建物の主要構造部分に関わる修繕などの「大修繕」については、修繕特約は無効であると解されています。なお、一定範囲の小修繕の修繕をしないまま契約が終了した場合、借主が修繕義務を負うことはないため、敷金から差し引けません。
修繕・改善のトラブルを回避するには、貸主と借主が契約時に修繕義務や条件を明確にすることが重要です。具体的には、物件の状態を入居時に詳細に記録し、どのような状況で費用を負担するかを契約書に記載します。また、定期的なメンテナンスの合意や、小さな問題を早期に解決するためのコミュニケーションのルールを設けることも有効です。
設備の一部滅失による賃料減額
2020年4月1日から適用された改正民法では、賃貸物件の一部が利用できなくなった場合に賃料を自動的に減額するルールが新たに設けられました。この改正により、賃借人は自分の責任でない理由で物件の一部が使用できなくなった際、賃料の減額を受けることが可能になります。
たとえば、水道設備の故障により水が使えない状況では、賃料の減額が認められます。これは、以前は賃借人が減額を請求できる状況だったものが、改正で自動的な権利に変わった点が大きな変更です。
管理会社の管理状況が悪いなどのトラブル
賃貸経営での物件管理は、資産価値と入居率維持に欠かせません。しかし、管理業務は煩雑であり、多くのオーナーはこれらの業務を管理会社に依頼しています。
ただし、中には入居者のニーズに対応しない管理会社も存在し、これが資産価値の低下や入居率の悪化につながる場合があります。適切な管理会社を選び、早急な対策を講じることが重要です。
具体的に、管理会社の管理状況が悪い場合、アパートオーナーはどのような対処を取ればよいのでしょうか。
問題を解決するためには、管理会社とのコミュニケーションを密にする、定期的な物件の点検を行う、入居者のフィードバックを積極的に収集するなどの対策が有効です。
管理会社と管理受託契約しているのは貸主です。借主から管理費を徴収している場合であっても、管理会社に対して管理改善の要求を出せるのは貸主です。
もし管理改善の要求をしても問題が解決しない場合は、管理会社を変更することも一つの選択肢となり得ます。
管理会社とのトラブルを避けるためには、事前に管理会社との明確な契約を結ぶことが重要です。契約では、物件の定期的なメンテナンスや修繕の責任範囲、緊急時の対応手順などを詳細に定めるべきです。
また、入居者からのクレームや要望に対する迅速な対応体制の構築も必要です。入居者との良好な関係を維持し、彼らの声に耳を傾けることも大切です。これにより、問題が発生した際に迅速に解決し、トラブルの発生を未然に防ぐことができます。
サブリース会社の物件管理における問題
サブリース事業では不動産業者が物件所有者から賃貸し、その後入居者に再賃貸します。
サブリース事業の中でも、一棟を丸ごと借り上げる「一括借り上げ」や転貸のある家賃保証契約には、借地借家法が適用されます。したがって、賃料の減額請求ができないという条文があったとしても、サブリース業者は賃料の減額請求権を有します。
また、貸主からの一括借り上げや転貸のある家賃保証契約の更新拒絶などには、正当事由が必要です。
また、契約を解除するためには、信頼関係の破壊が必要です。サブリース契約は固定収入が得られたり、手間が少なくなったりするといったメリットがありますが、賃料の減額請求権や家賃保証契約更新を拒絶する際のデメリットをしっかり理解して契約することが重要です。
契約解除のトラブル
アパート経営における契約解除や立ち退きは、将来の建て替えなどでトラブルの原因となり得ます。賃貸借契約の契約形態として普通借家契約が一般的です。
しかし、この契約下では借主の権利が強く守られ、貸主は簡単に契約を解除できません。契約解除を進めるには、正当な理由と立ち退き料が必要となり、解約するための手続きは複雑で時間を要することがあります。
契約解除や立ち退きをスムーズに行うには、法律の知識が必要であり、場合によっては専門家の助けを求めることが賢明です。
契約解除の具体的な例を次に解説します。
関連記事:入居者の契約違反があった場合、契約解除はできる?オーナーの対処方法を解説
騒音問題
賃貸物件における騒音問題は、入居者間のトラブルとして非常に多く発生しています。この問題は、生活音やペットの鳴き声、楽器の演奏など、多岐にわたる原因で発生し、時には契約解除の理由にもなり得ます。
賃貸経営を成功させるためには、このような入居者トラブルに適切に対処することが不可欠となります。
騒音に関するトラブルは、一定の基準を超える場合、契約解除の対象となる可能性があります。特に、夜間における騒音や長期間にわたる反復的な騒音は、他の入居者の生活を著しく害するため、深刻な問題として扱われます。このような状況では、不動産管理会社や物件のオーナーは、法的措置を含めた対応を検討する必要があります。騒音問題への適切な対処方法を紹介します。
関連記事:騒音トラブルは大家の責任?賃貸アパートの騒音について義務や対処手順を解説
予防策の導入
騒音トラブルを未然に防ぐために、契約時に騒音に関する規定を明確に設定します。賃貸借契約締結時に規定を借主に書面にて確認するのも一つの手です。
迅速な対応
騒音トラブルが発生した場合は、速やかに両者の話を聞き、事実関係を確認することが重要です。可能であれば、調停による解決を目指し、双方が納得のいく形で問題を解決します。
法的措置
事態が改善されない場合は、契約書に基づいた契約解除を含む法的措置を検討することも必要です。このプロセスでは、専門家のアドバイスを仰ぐことが推奨されます。
騒音問題の対応に際しては、不動産管理会社や宅地建物取引業協会の支部、そして法的支援を提供する弁護士(法テラスなど)が有効な相談先です。これらの機関は、トラブル解決のための適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。
管理会社が原因の入居者トラブルと対処法
賃貸経営において、管理会社の役割は非常に大きいです。しかし、管理会社の不適切な対応や管理不足が原因で入居者トラブルが発生することも少なくありません。ここでは、そうしたトラブルの原因と対処法を紹介します。
管理会社が原因のおもな入居者トラブルは、次の通りです。
コミュニケーション不足
管理会社と入居者間のコミュニケーションが不十分な場合、誤解が生じやすく、トラブルの原因となります。
メンテナンスの遅れ
設備の修理や定期的なメンテナンスが適切に行われない場合、入居者の不満が高まります。
不透明な経費請求
管理経費の内訳が不明瞭であると、入居者からの信頼を失います。
管理会社が原因の主な入居者トラブルへの対応として、次の対処法を管理会社へ徹底させることが挙げられます。
定期的な情報提供
物件の状況やメンテナンス計画などを定期的に入居者に情報提供することで、信頼関係を築くかせる。
迅速な対応
故障や不具合の報告があった場合は、速やかに対応する体制を整えさせる。
定期的なメンテナンス
物件の長期的な価値を維持するためにも、定期的なメンテナンスを行う。
管理会社は、入居者からの信頼を得るために、常に透明性を持ち、コミュニケーションを大切にすることが求められます。さらに、トラブルが発生した際には、迅速かつ公正に対応することで、問題を最小限に抑えることができます。
賃貸経営における管理会社の役割は非常に大きく、その対応一つで入居者との関係が大きく変わります。賃貸経営を成功させるためには、管理会社としての責任を認識し、質の高いサービスを提供させるようにしましょう。
入居者によるトラブルの相談先は3種類
賃貸住宅における入居者トラブルは多種多様であり、その解決方法も一つではありません。トラブルの性質や状況に応じて、適切な相談先を選択することが重要です。
不動産の管理会社に相談するメリット
不動産管理会社は、賃貸物件の運営に関わるあらゆる事項をサポートします。入居者からのクレーム対応や設備トラブル、契約違反など、オーナーが直接対応するには専門知識が必要な場合や、時間と労力がかかる作業を代行してくれます。
対応可能なトラブル例は以下のとおりです。
- 設備トラブル:水漏れ・電気の不具合・冷暖房の故障など
- 入居者間の問題:騒音・ごみ出しルール違反・ペットの飼育問題など
- 契約違反:無断での部屋の改造・遅延家賃の回収などメリット
- 専門スタッフが常時対応可能な体制を整えているため、トラブルが発生した際に迅速に対処できます。
- 賃貸管理に必要な法的知識を持つ専門家が対応するため、法律を遵守した適切な対応が可能です。
- トラブル対応の時間と労力を大幅に削減し、オーナーの負担を軽減します。
アパートオーナーにとって入居者トラブルは避けられない問題ですが、不動産管理会社を上手く活用することで、これらの問題を効果的に解決し、賃貸経営を安定させることが可能です。
トラブル発生時の迅速な対応はもちろん、日常的な管理業務の効率化、法的トラブルの未然防止にもつながります。オーナー自身の負担を軽減し、賃貸物件の価値を長期にわたって維持するためにも、信頼できる不動産管理会社との良好な関係構築を心がけましょう。
宅地建物取引業協会の支部に相談するメリット
宅地建物取引業協会は、不動産取引を安全かつ適正に行うためのルールを定め、その実施を促進することを目的とする団体です。全国各地に支部を持ち、不動産に関するさまざまな相談に応じています。特に、賃貸経営においては、入居者とのトラブル解決における貴重なリソースとなり得ます。
アパートオーナーが相談できること
- 家賃の遅延や未払い・無断改造などの契約違反事項
- 入居者間の騒音問題・共用部の利用ルール違反などのトラブル解決
- 賃貸契約・立ち退き交渉・敷金返還問題などの法的アドバイス
メリット
- 不動産取引に関する豊富な知識と実績を有する専門家からのアドバイスを受けることができます。
- 中立的な立場から問題解決を支援してくれるため、公正な解決が期待できます。
- 必要に応じて法的な支援や仲介を提供してくれるため、複雑な問題にも対応可能です。
宅地建物取引業協会の支部は、アパートオーナーが直面する入居者トラブルに関して、専門的かつ中立的な支援を提供してくれる貴重な相談先です。彼らのサポートにより、法律を遵守した上で、かつ効率的に問題を解決する道を見い出すことができます。
弁護士(法テラス)に相談するメリット
法テラスは、日本法律支援センターの通称であり、国が設立した法的支援を提供する公的機関です。経済的な理由で弁護士費用を負担できない人々に対して、法的相談や訴訟の支援を行います。
アパートオーナーも、入居者とのトラブルに関して法テラスを通じて弁護士に相談することが可能です。当事者間の話し合いで解決しない場合や、管理会社や宅地建物取引業協会の支部に相談しても解決できない場合、弁護士(法テラス)に相談するとよいでしょう。
アパートオーナーが相談するメリット
- 不動産法や契約法など、賃貸経営に関連する複雑な法律問題について、専門知識を持った弁護士からアドバイスを受けられます。
- 法テラスを利用することで、比較的低コストで法的支援を受けることが可能です。経済的負担を抑えながら、専門家のサポートを得られます。
- 法的手続きを適切に行うことで、トラブルを根本的に解決し、再発防止につながります。
相談方法
- 法テラスに電話やウェブサイトを通じて問い合わせます。相談内容に応じて、適切な支援方法を案内してもらえます。
- 法的支援が必要と判断された場合、弁護士との相談の予約を行います。この時点で、相談内容の概要や必要な書類について確認しておきましょう。
- 予約した日時に弁護士と面談し、具体的な相談を行います。トラブルの状況、これまでの経緯、解決を望む形など、詳細を伝えましょう。
入居者トラブルに直面した際、弁護士(法テラス)を通じて専門的な法的支援を受けることは、経済的な負担を抑えつつ、問題を適切に解決するために有効です。専門知識を持った弁護士からのアドバイスやサポートにより、トラブルを公正かつスムーズに解決できます。
賃貸経営のトラブル解決には「ビズアナオーナー」
「ビズアナオーナー」は、賃貸物件オーナー様に向けた無料の収支管理サービスです。
管理会社などから送られてくる収支報告書をアップロードするだけで、賃貸経営における収支状況などを視覚的に表示することができます。
また、ビズアナオーナー会員様には、賃貸経営に関するトラブルや税金に関するセミナー動画を無料で公開しており、賃貸経営にまつわるノウハウや事例を簡単に学ぶことも可能です。
賃貸経営のトラブル解決には、「ビズアナオーナー」をご活用ください。
【賃貸トラブルの回避にも役立つ!】
- 収支報告書を事務局に送るだけで収支管理を完全自動化
- 不動産経営のプロが講師を務めるセミナーに無料招待
- AIによる賃料査定・統計調査などのレポート提供
ビズアナオーナーは、トラブルを回避して賃貸経営を効率よく行いたい不動産オーナー様におすすめです!