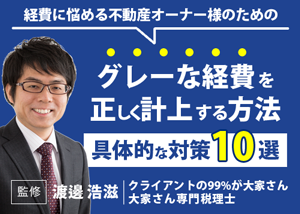自動販売機の設置はどのくらいの利益を見込める?最大化する方法は?

空きスペースの活用や土地活用のひとつとして自動販売機の設置があります。自動販売機は身近なものですが、土地活用の側面から見ると不明な点が多いのではないでしょうか。
どのような理由で、自動販売機の設置を選ぶのでしょうか、またどのくらいの利益が見込めるのでしょうか。
土地活用として自動販売機の設置はどうなの?
自動販売機は管理を委託できるため、初心者でも取り組みやすいスペース・土地活用です。自動販売機を設置して利益を上げる仕組みやメリット・デメリットについて紹介します。
自動販売機の運用方式は2種類
自動販売機の運用方式は2種類あります。それぞれの特徴は以下のとおりです。
| 運用方式 | フルオペレーションタイプ | セミオペレーションタイプ |
|---|---|---|
| 管理の特徴 | 事業者が管理する | 自分で管理する |
| 利益の特徴 | 管理会社に販売手数料を支払うため、利益は少なくなる | 売上のすべてが自分の利益になる |
管理を委託するフルオペレーションタイプは、初心者でも安心できるため人気です。
自動販売機を設置するメリット3選
自動販売機の設置にはさまざまなメリットがあります。3つのメリットを紹介します。
- 管理の手間がかからない
- ほかの土地活用と一緒に始められる
- 移設しやすい
管理の手間がかからない
自動販売機は管理業務を委託できるため、手間がかかりません。
セミオペレーションタイプの場合はオーナーが管理をする必要がありますが、ほかの土地活用と比べると手間は少ないです。
- 商品管理および補充
- 釣り銭の補充
- 不具合や故障時の対応
自動販売機は上記の管理作業が必須ですが、管理を委託する場合はすべての作業を任せられます。管理を委託する場合、オーナーの主な仕事は以下のとおりです。
- 事業者との打ち合わせ
- 契約締結
- 電気代の支払い
このように、管理業務を削減できます。管理に手間がかからないだけでなく、プロに管理を任せられるので安心です。
ほかの土地活用と一緒に始められる
自動販売機の運用は、ほかの土地活用と一緒に始めやすく相乗効果が期待できます。小規模な土地でも設置できますし、集客にも役立てられます。
たとえば、以下の土地活用と合わせると効果的です。
- アパートや駐車場の賃貸物件
- 飲食店の経営
自動販売機の設置により利便性が向上すると、利用客の満足度があがります。継続的な利益も見込めるため、相乗効果が大きいです。
移設しやすい
自動販売機は広いスペースがなくても設置でき、場所の制約が少ないため移設がしやすい土地活用です。
たとえば、アパートやマンションなどの賃貸物件は移設ができません。
- 諸事情により、居住地を変更したい
- 周辺に商業施設ができたので、自動販売機の設置場所を変えたい
という場合でも、移設を検討できるのは自動販売機の特徴です。生活スタイルに合わせた運用を行えるのは大きなメリットだといえます。
自動販売機を設置するデメリット3選
自動販売機の設置にはデメリットも存在します。リスクを減らすために、事前に把握しておくとよいでしょう。
自動販売機の設置によるデメリットを3つ紹介します。
自動販売機が原因で騒音トラブルになるおそれがある
利用客の行動によって、騒音トラブルに発展するおそれがあります。具体的には以下のようなトラブルに注意が必要です。
- お酒に酔った利用客が騒ぐ
- 複数人の利用客が大声で会話する
自動販売機は24時間稼働するため、夜間にも利用客が訪れます。日中は問題がなくても、夜間にトラブルが起きることもあるでしょう。
リスクを下げるためには、周辺地域や客層を事前に確認しておきましょう。
立地によっては自動販売機の管理を委託できない
事業者が集客の見込みを検討した結果、自動販売機の管理が委託できないことがあります。
事業者が利益を見込めると判断し、審査がおりないと設置はできません。自分で自動販売機を買い取るなら設置は可能ですが、管理は自分で行う必要があります。
設置審査がおりやすい土地は以下のとおりです。
- 人通りの多い土地
- オフィスの近く
- 集合住宅の近く
土地を所有していても、立地次第で管理を委託できない点には注意が必要です。
周辺環境の影響を受けやすい
自動販売機は周辺環境の影響を受けやすく、利益に影響が出ることがあります。
設置したときは周辺にコンビニがなかったのに、数年後に開店することもあるでしょう。近隣に品揃えの豊富な店舗ができると、利用者はそちらに流れます。しかも、環境の変化は自分でコントロールできません。
環境変化の予測をして、設置場所を深く検討する必要があるでしょう。
自動販売機の設置、利益はどのくらい?
自動販売機の設置で得られる利益は、多くて月に数万円程度です。しかし、利益は運用方式によって変わります。
自動販売機の利益は数千〜数万円
自動販売機の設置で得られる利益は月に数千〜数万円です。幅があるのは運用方式によって手数料が発生するからです。
フルオペレーションタイプは売上のうち、20~30%がオーナーの取り分になります。利益が3万円だった場合は、6,000〜9,000円がオーナーの利益です。
反対にセミオペレーションタイプは、売上のすべてがオーナーの取り分です。うえの例だと3万円すべてがオーナーの利益として残ります。
月の利益は運用方式で大きく変わるので、どちらを選択するかは重要です。
関連記事:不動産投資の平均利回りは何パーセント?最低ラインや利回りを高くするコツを紹介
自動販売機の設置に必要な初期費用は?
初期費用も運用方式によって差があります。フルオペレーションタイプは初期費用がかからないのが特徴です。
| 運用方式 | フルオペレーションタイプ | セミオペレーションタイプ |
|---|---|---|
| 初期費用 | 無料の場合が多い |
|
フルオペレーションタイプは本体および設置工事の費用を事業者が負担します。代わりに、オーナーは電気代のみを負担する契約が多いです。
セミオペレーションタイプは初期費用の負担が大きいです。設置後に利益が見込めるか、深く検討する必要があるでしょう。
自動販売機を運用するためのランニングコスト
自動販売機にはランニングコストがかかります。主な内訳は商品代や冷却・保温、ライトアップに必要な電気代です。
| 運用方式 | フルオペレーションタイプ | セミオペレーションタイプ |
|---|---|---|
| 電気代 | 2,000~4,000円 | |
| 商品代 | 負担なし | 商品によって変動 |
フルオペレーションタイプは電気代だけの負担になるため、月に2,000~4,000円です。セミオペレーションタイプは商品によって仕入費用が異なります。どれだけ安く仕入れるかが重要です。
自動販売機の利益を最大化する方法とは
自動販売機は単体では大きな利益は見込めません。しかし、土地活用をする以上は利益の最大化を図りたいものです。
自動販売機の利益を最大化する方法を紹介します。
自動販売機を差別化して利用者を増やす
自動販売機の差別化を行い、利用者を増やしましょう。特にセミオペレーションタイプで効果があります。
利用客によって商品の需要は異なるため、需要に合わせた商品を選びましょう。また、特色のある自動販売機は話題性やリピート客の獲得にもつながります。
自動販売機のラインナップは以下のようなものがあります。
- 飲料
- カップ麺
- お菓子
- 軽食
主流は飲料ですが、珍しい商品を扱うと利用者の興味を引きやすいです。商品の差別化は誰でもできるので、挑戦しやすい方法です。
自動販売機の設置事業者を厳選する
自動販売機の設置事業者を厳選し、条件がよい相手を探しましょう。これはフルオペレーションタイプで効果があります。
フルオペレーションタイプは契約内容でオーナーの収益が決まるため、よい条件の設置事業者を見つけることが大切です。初めての方は、Webサイトから資料を取り寄せることから始めるとよいでしょう。
賃貸物件と併設して相乗効果を狙う
広い土地を所有している場合は、賃貸物件の建築と合わせて併設することで利益を最大化できます。
アパートや駐車場などの人が集まりやすい場所に設置すると安定した利益を得られます。また、自動販売機の設置で利用者の利便性も高められます。その結果、賃貸物件の満足度アップにつなげられるでしょう。
集客効果が期待できるうえ、賃貸物件との相乗効果で利益を増やせます。効果的に土地活用ができるため、賃貸物件との併設を検討してはいかがでしょうか。
賃貸経営をはじめる方におすすめ!無料の「ビズアナオーナー」
ビズアナオーナーは、不動産オーナー様の賃貸経営をトータルサポートする会員制のWEBサービスです。
所有する物件の収支・稼働状況をカンタンに可視化できる収支・稼働管理機能(無料)をメインとし、所有物件周辺の環境情報が詰まった統計調査レポートサービス、不動産関連セミナーへの無料招待の他、賃貸経営に役立つオプションメニューを多数ラインナップ!
【賃貸経営に役立つメニューが満載!】
ビズアナオーナー会員様には、次のようなメリットがあります。
- 初めての方も簡単に収支管理できる しかも登録料&月額利用料は無料!
- 所有する土地や物件周辺の地域特性がわかる調査レポートを受け取れる
- 固定資産税対策など過去のセミナー動画をいつでも無料で視聴できる
ビズアナオーナーは、賃貸経営に役立つ情報を効率的に収集したい不動産オーナー様におすすめです!
▼この記事を見ている方にはこちらの資料がおすすめ!▼
家賃収入を長期に渡って安定的に得ることは容易ではありません。
賃貸経営のリスクに対してどのように備えるべきかを解説します。